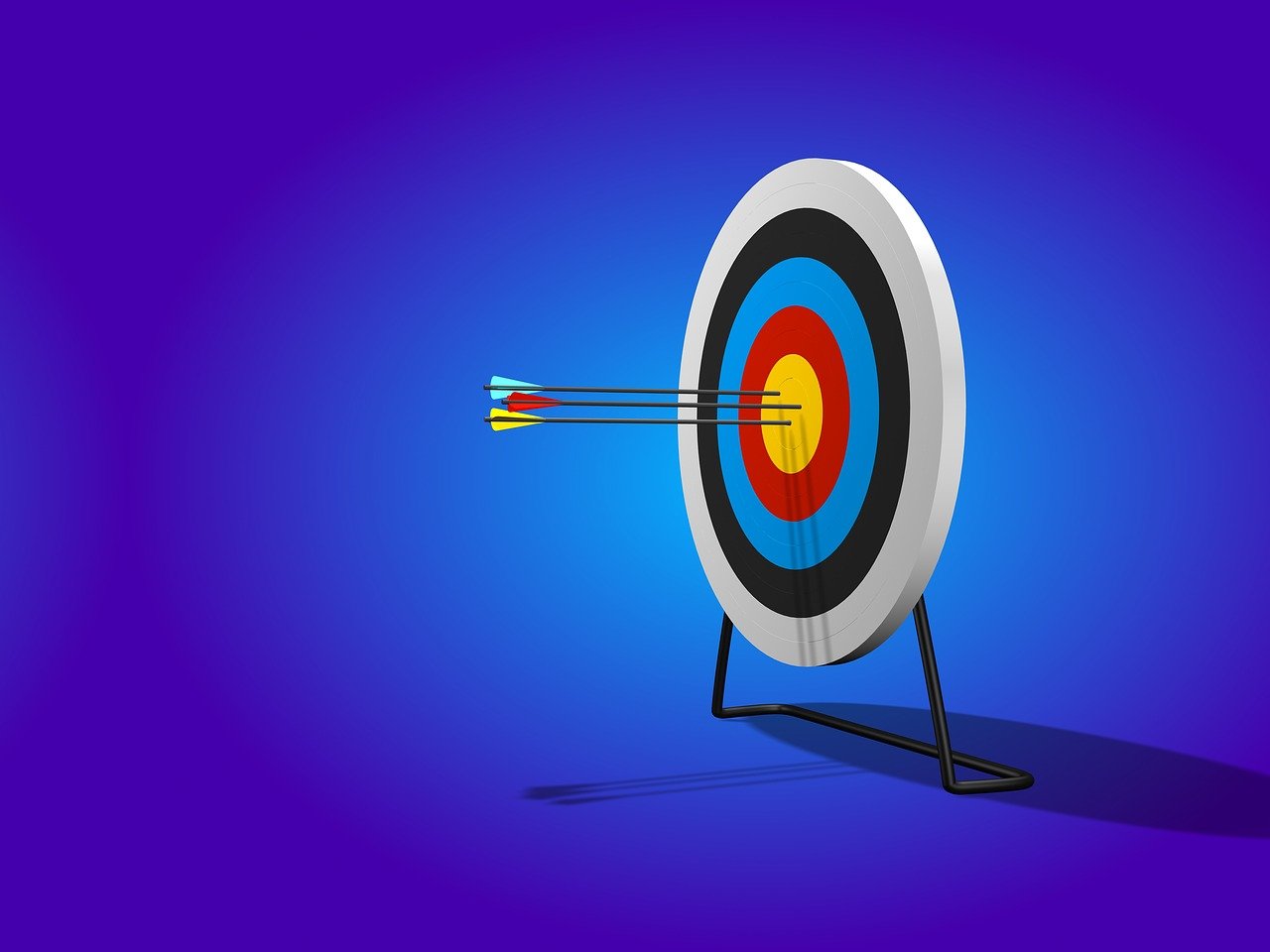現代のマーケティング手法におけるトレンドは、ユーザーに自ら見つけてもらう「コンテンツマーケティング」と言えます。ユーザーの行動・ニーズ分析が必要なため、無計画に取り組んでも成功は難しいです。これから実践する場合、まずはコンテンツマーケティングの目的から正しく理解しましょう。
この記事では、コンテンツマーケティングの目的を詳しく解説します。コンテンツの種類と認知手法ごとの、加えて目的を定める必要性などを深堀りしていきます。
コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
コンテンツマーケティングの目的とは?

コンテンツマーケティングはそもそも、「ユーザーに有益な情報を発信して見込み顧客を育て、利益を向上する」一連の手法です。したがって、どのような企業であれ最終目標は利益の向上です。しかし、最終目標に至るまでの過程を見ていくと、細かな目的は以下4つに分類できます。
- 商品・サービスの購買
- リード獲得
- ブランディング・ファン化
- 認知拡大・人材獲得
商品やサービスの購買で直接的な利益向上を図る企業もあれば、ブランディングによって中長期的な利益向上を狙うところもあるでしょう。もちろん全てを目的に据えて、短期・長期のどちらでも利益向上を図るパターンも考えられます。
4つの目的の詳細について、それぞれ説明します。
1.商品・サービスの購買
定番の目的となるのが、自社商品・サービスの購買です。コンテンツを通して見込み顧客との接点を増やし、商品・サービスを購入してもらいます。宿泊施設やサービスの予約といった行動も購買の1つです。
見込み顧客は、ターゲットの状態によって非認知層・潜在層・顕在層の3段階に分けられます。効果的に購買行動へ誘導するためには、それぞれの段階に合ったコンテンツの制作・発信が大事です。なお、段階ごとに適したコンテンツの種類については次の章で解説します。
2.リード獲得
BtoB企業に多い目的は、リード獲得でしょう。将来的な見込み顧客を効率的に得るため、コンテンツを作成します。リード獲得の窓口となるのは、資料請求やダウンロード、問い合わせ、申し込みなどです。
獲得したリードに対しては、興味関心や購買意欲を高める「リードナーチャリング」をマーケティング部門が実施します。育成されたリード情報を営業部門に引き継ぎ、商談に繋げる流れが一般的です。
3.ブランディング・ファン化
自社ブランディングや顧客のファン化は、長期的な施策として行われます。獲得したファンをさらに「ロイヤルカスタマー」へと育てることも目的になるでしょう。ロイヤルカスタマーとは、自社製品に愛着を持ち、良い評判をシェアしてくれる存在です。
技術競争のピークを過ぎた成熟市場では、競合他社の製品と品質差がなくなる傾向があります。結果的に市場全体が価格競争を始めるわけですが、ファンやロイヤルカスタマーは価格を下げずとも自社製品を選んでくれます。成熟市場でも価格競争に巻き込まれづらくなり、長期的な利益拡大が見込めるわけです。
4.認知拡大・人材獲得
認知拡大は、これまで紹介した購買やリード獲得、ファン化に繋がるため、多くの企業が目的の1つとするでしょう。良質なコンテンツを公開して、自社を知らない非認知層まで接点が広がります。
自社の知名度が求職者にも広がれば、人材獲得に有利に働きます。労働人口が減少しつづける現代で優秀な人材を獲得するには、求職者への積極的な接触が必要です。単純な知名度アップだけでなく、自社の魅力や働く環境がわかるコンテンツを発信すると、より多くの応募が期待できます。
コンテンツ制作における目的|9種類のコンテンツ

コンテンツマーケティングそのものの目的は伝えた通りですが、制作するコンテンツごとに目的設定の向き・不向きがあります。下記9種類のコンテンツごとに、それぞれに適している目的を見ていきましょう。
- 記事(ビジネスブログ)
- 導入事例
- 動画
- 音声
- LP(ランディングページ)
- セミナー(ウェビナー)・イベント
- 雑誌・書籍
- カタログ
順番に解説します。
1.記事(ビジネスブログ)
記事(ビジネスブログ)の主な目的は、集客や購買、リード獲得です。記事の種類によって多様な目的に対応できるため、多くの企業が制作しています。そのため、コンテンツマーケティングで制作されるコンテンツの中でもポピュラーな存在です。
記事には、お役立ち情報、疑問解決、評価・レビュー、製品比較・紹介、インタビュー、専門家監修のコラムなどの種類があります。むやみに記事を作るのではなく、目的に応じた記事を制作しましょう。たとえば、集客目的ならお役立ち情報や疑問解決の記事が向いています。
2.導入事例
導入事例の目的は、BtoB向けサービス・製品の訴求、リード獲得、信頼性の向上です。導入事例があると、読者は「自社でこのサービスを使うとどうなるのか?」とイメージしやすくなります。実際の事例なので情報の信頼性も高く、お問い合せや資料請求といったリード獲得に適しているコンテンツです。
また、読者と類似する状況の成功事例があれば、前向きな判断材料にしてもらえるでしょう。ターゲット層となる企業に近い導入事例をできる限り多く揃えると、より多くの読者への訴求が可能です。
3.動画
動画の内容は目的によって異なり、主に認知拡大やブランディング、既存顧客のアフターフォローがあります。テキストのみでは伝えきれない内容を、映像で詳しく伝えられる点が強みです。
たとえば、自社製品の使い方を解説する動画はユーザーのアフターフォローに適しており、購入検討中の視聴者へも訴求できます。潜在層に興味を持ってもらいたいのであれば、自社ブランドのティザー動画が良いでしょう。気軽に投稿できる上に、ユーザーも多いYouTubeなどの動画配信サイトが登場したことで、動画を取り入れる企業が増えています。
4.音声
音声コンテンツの目的は、認知拡大、ファン獲得、ブランディングです。ポッドキャストを使った「音声マーケティング」が近年増えており、注目されつつあります。ポッドキャストは審査をクリアすれば、どのような企業でも録音したコンテンツを配信できます。
音声コンテンツの魅力は、「ながら視聴」ができる点です。目でテキストや映像を確認する必要がなく、日常生活の中で自然と自社の認知度向上やファン化を図れます。審査基準の中で自由に内容を決められるので、自社のターゲット層に好まれるコンテンツを構成すると良いでしょう。
5.LP(ランディングページ)
LP(ランディングページ)の目的は、製品・サービスの購買とリード獲得です。なお、ここでのLPとは「購買やリード獲得に特化したWebページ」を指しており、広義の「ユーザーが最初に閲覧する自社のWebページ」ではありません。
多くのBtoCのLPは、購買が目的になります。BtoCのLPを閲覧するのは一般消費者ですので、個人判断のみで商品を購入してもらえるからです。一方、BtoBのLPは企業の担当者が閲覧し、「この製品・サービスは自社に有用か」と総合的に判断して稟議にかけます。衝動的な購入は考えられないため、メインの目的は問い合わせや資料請求といったリード獲得です。
6.ホワイトペーパー
ホワイトペーパーの目的は、BtoBのリード獲得や信頼性の向上です。主に、BtoB向けにアプローチするコンテンツとなります。ユーザーがホワイトペーパーをダウンロードする際は、会社や役職などの情報を入力する形が一般的です。潜在顧客や、自社にある程度興味を持つ「ホットリード」の情報を効率的に取得できるでしょう。
よく制作されるのは、課題解決型のホワイトペーパーです。ターゲット層が抱えている課題を仮説立て、要因と解決策を提示し、自社の製品・サービスを紹介する流れで構成します。その他、レポート・調査型、事例紹介型、用語集などの種類があります。
7.セミナー(ウェビナー)・イベント
セミナー(ウェビナー)・イベントの目的は、リード獲得、直接的な信頼関係の形成、ファン獲得です。セミナーやイベントの内容は、商品説明やレクチャー、研修といった種類があります。
中でも商品説明やレクチャーを行うセミナーの参加者は、ある程度自社に興味関心がある層です。効率良く集客できる上に、セミナーを通して信頼関係を築いた状態で商談に持ち込めます。また、既存顧客に対しても、定期的なセミナー・イベントによるアフターフォローが可能です。満足度を上げてファン化できれば、リピーターの増加が期待できます。
8.雑誌・書籍
企業出版による雑誌・書籍発行の目的は、ブランディング、認知拡大、信頼性の向上です。企業出版とは、企業がマーケティングの一環で本を発行する出版形式を指します。出版社による校正などのサポートを受け、企業が自費で本を出版する作り方です。
注意点として、出版社が費用を出して全国的に流通する「商業出版」は、本の売上による利益を目的とします。企業出版は、前述の通りあくまでブランディングなどが目的です。専門知識やノウハウを活かした内容でのファン獲得や、「本を出版している企業」のイメージによる信頼性の向上を図ります。
9.カタログ
カタログもコンテンツの1つであり、購買、見込み顧客へのアプローチ、リピーターの獲得が目的です。カタログは冊子で作られ、自社の商品やサービスを網羅的に紹介します。購買意欲の高い顕在層に向けたコンテンツであり、基本的に潜在層や非認知層は狙いません。
カタログから注文受付もできる場合が多く、直接購買に繋げられます。QRコードやURLを掲載することで、Web上のオウンドメディアへの誘導も可能です。
【一覧表】コンテンツの種類ごとの目的
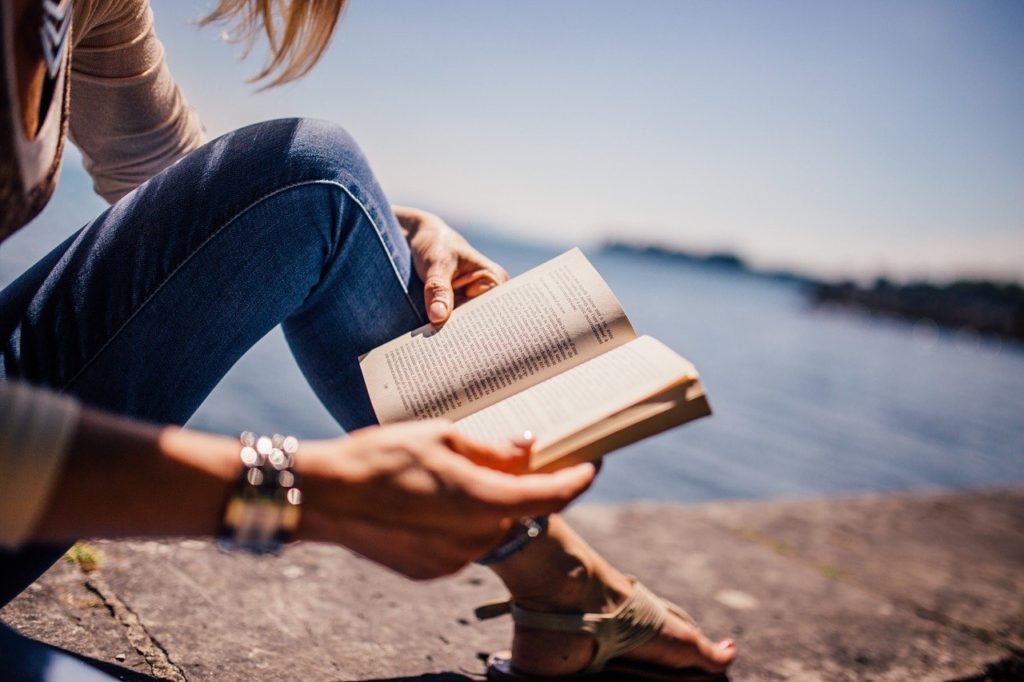
ここまで紹介した9種類のコンテンツについて、目的や特徴を下記の一覧表にまとめます。
| コンテンツ | 主な目的 | 特徴 |
| 記事(ビジネスブログ) | 集客、購買、リード獲得 | さまざまな種類の記事を制作可能。目的に合わせて内容を構築できる |
| 導入事例 | BtoB向けのサービス・製品の訴求、リード獲得、信頼性の向上 | BtoB向けのリード獲得に向いており、実際のユーザーによる信頼性の高い情報を届けられる |
| 動画 | 認知拡大、ブランディング、既存顧客のアフターフォロー | テキストや画像よりも詳しくわかりやすい内容を伝えられる |
| 音声 | 認知拡大、ファン獲得、ブランディング | ポッドキャストによる配信が主流。ターゲットに合わせた構成が重要 |
| LP(ランディングページ) | 製品・サービスの購買、リード獲得 | BtoCのLPは購買が主な目的。BtoBのLPはリード獲得が主な目的 |
| ホワイトペーパー | BtoBのリード獲得、信頼性の向上 | 課題解決型のホワイトペーパーが多い。ホットリードの情報を効率的に取得できる |
| セミナー(ウェビナー)・イベント | リード獲得、直接的な信頼関係の形成、ファン獲得 | ある程度興味関心がある層に効率良く接触可能。信頼関係を築いて商談できる |
| 雑誌・書籍 | ブランディング、認知拡大、信頼性の向上 | マーケティングの一環で行う「企業出版」を指す。本の売上は目的に含めない |
| カタログ | 購買、見込み顧客へのアプローチ、リピーターの獲得 | 購買意欲の高い顕在層にアプローチ。冊子で自社商品・サービスを紹介する |
コンテンツを選ぶ際は、コンテンツマーケティングの目的と一致しているかに気をつけましょう。ファン獲得やブランディングを目的とするなら、購買が目的のLPばかり制作しても意味がありません。目的に合うコンテンツの制作が重要です。
コンテンツマーケティングの認知拡大における目的|6つの手法
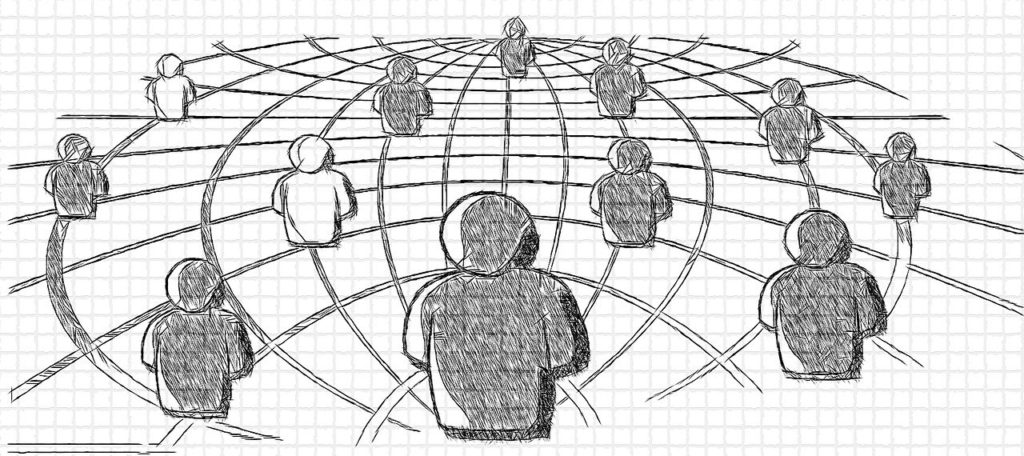
制作したコンテンツは、さまざまな手法によって認知を拡大させます。認知拡大の目的は、当然ながら自社コンテンツやサービス・商品への誘導、ひいてはコンテンツマーケティングそのものの目的達成です。ただし、手法ごとに適した目的設定があるため、次の順番で確認しましょう。
- 広告
- SEO
- SNS
- プレスリリース
- メルマガ(メールマガジン)
- DM(ダイレクトメール)
それぞれのポイントを説明します。
1.広告
広告による認知拡大の目的は、購買、リード獲得、コンテンツへの流入、知名度向上です。広告は直接的に製品販売ページやLPにアクセスしてもらえるため、購買やリード獲得を目的に含められます。
広告の中でも、Web広告の種類は多種多様です。たとえば、検索キーワードに連動して顕在層にアピールする「リスティング広告」、記事型コンテンツと同じように作り込み、潜在層にも届く「ネイティブ広告」などの種類があります。それぞれターゲットが異なるため、広告媒体の見極めが大切です。
2.SEO
SEOの目的は、Googleなどの検索エンジンからの集客です。購買やファン獲得といった目的で集客する記事もありますが、SEO自体の目的は自然流入による集客のみとなります。SEOの強みは、制作した記事のキーワードによって、非認知層や潜在層、顕在層まで幅広くアプローチできる点です。検索エンジン最適化とも呼ばれ、記事などのテキストコンテンツで重要視されています。
検索結果で上位表示させるために必要な要素の1つが、コンテンツの質です。読者が知りたい情報を提供している記事は上位表示されやすく、高品質な記事作りが欠かせません。質の良い記事は何年経っても集客してくれるため、長期的に取り組むほど恩恵が大きくなる手法と言えます。
3.SNS
SNSは、ファン獲得、ブランディング、コンテンツへの流入が目的です。直接的な目的ではありませんが、SNS経由の購買やリード獲得も狙えるでしょう。Twitter、Instagram、Facebookは「3大SNS」と言われますが、近年はTikTokもコンテンツマーケティングに採用する傾向が見られます。
いずれのSNSも、定期的な投稿やユーザーとの交流を通し、距離感の近いコミュニケーションが可能です。ファン獲得の場に適しており、自社コンテンツの拡散や流入も図れます。SNSによって年齢層や拡散力が違うので、運用する場合は自社のターゲット層ともっとも相性が良い媒体を選びましょう。
4.プレスリリース
プレスリリースを配信する目的は、非認知層や潜在層へのアプローチ、知名度向上です。プレスリリースとは、自社の新商品・サービスの発表、経営情報、新規事業の情報といった企業活動をまとめた資料です。
注目度の高いプレスリリースは第三者のメディアに報道され、自社を全く知らない非認知層まで情報を届けられるでしょう。プレスリリース配信サービスもあり、たとえ大手メディアに取り上げられずとも多くの読者に直接読んでもらえます。幅広い認知拡大を狙うのでれば、定期的なプレスリリースの発表は効果的です。
5.メルマガ(メールマガジン)
メルマガ(メールマガジン)は目的が多く、販促活動、リピーター獲得、見込み顧客へのアプローチ、コンテンツへの流入が挙げられます。受信者の状態によって、目的が変化する点が特徴です。
受信者が既存顧客であれば、サービスや商品の継続利用に繋がるメルマガを送り、リピーター化を目指すと良いでしょう。製品の便利な使い方や導入事例などのコラムは、メルマガに無料登録している見込み顧客へのリードナーチャリングとして効果的です。さらに詳しい情報があるページのURLを埋め込むと、コンテンツへの流入増加も見込めます。
6.DM(ダイレクトメール)
DM(ダイレクトメール)を送付する目的は、販促活動、見込み顧客へのアプローチ、リピーターの獲得です。ユーザーへ直接届く特徴がメルマガと共通しており、目的も似ています。QRコードやURLを記載すれば、Web上のコンテンツへの誘導も可能です。注意点として、SNS上のDM(ダイレクトメッセージ)ではありません。
DMはハガキや封書で送るのが一般的ですが、封書にカタログや商品サンプルを同封するケースもあります。インターネットをあまり使わない層と接点を持てるため、オフラインの認知拡大手法として活躍しています。
▼コンテンツマーケティングのさまざまな手法については、あわせてこちらの記事もご覧ください。
【一覧表】認知拡大手法ごとの目的

下記表に、6種類の認知拡大手法ごとの目的と特徴をまとめます。
| 認知拡大手法 | 目的 | 特徴 |
| 広告 | 購買、リード獲得、コンテンツへの流入、知名度向上 | Web広告の種類が豊富。自社のターゲットに合わせた広告選びが必要 |
| SEO | 検索エンジンからの自然流入による集客 | 非認知層〜顕在層まで幅広くアプローチ可能。良質な記事コンテンツが必須 |
| SNS | ファン獲得、ブランディング、コンテンツへの流入 | ユーザーとの距離感が近く、ファン獲得やブランディングがしやすい |
| プレスリリース | 非認知層や潜在層へのアプローチ、認知拡大 | 企業活動をまとめた資料。配信サイトやメディアを通し、自社を全く知らない層にも情報が届く |
| メルマガ(メールマガジン) | 販促活動、リピーター獲得、見込み顧客へのアプローチ、コンテンツへの流入 | 受信者の状態によって目的が変化。コラムや商品の販売促進などのメールを送信する |
| DM(ダイレクトメール) | 販促活動、見込み顧客へのアプローチ、リピーターの獲得 | オフラインでユーザーの手元に直接届く。カタログや商品サンプルの同封も可能 |
コンテンツや商品・サービスの認知を広げる際は、上記の手法から検討してみてください。例を挙げると、記事コンテンツによる集客を考えるなら、SEOに優先的に取り組むべきでしょう。
コンテンツマーケティングの目的を定める必要性

コンテンツマーケティングを進める際は、初期の企画段階で施策の目的を決める流れが一般的です。早いうちに目的を定める必要があるのは、以下4つの理由によります。
- コンテンツの方向性がぶれない
- ターゲットに合った認知手法を選べる
- 外部連携がスムーズになる
- 成果が出ずに頓挫するリスクを抑える
具体的に解説します。
1.コンテンツの方向性がぶれない
コンテンツマーケティングを行う目的を理解しておくと、制作するコンテンツの方向性がぶれません。目的達成のためにコンテンツを作るわけですが、目的ごとに適したコンテンツは異なります。
「BtoB企業のリード獲得」を目的にしたと仮定すると、作るべきコンテンツは自社そのものや商品・サービスをアピールできるものです。具体的には、導入事例やホワイトペーパー、セミナーなどが該当します。記事や動画も、BtoB向けの内容であれば効果的でしょう。
反対に、集客目的の記事のみ量産しても効果は薄いです。コンテンツによって適性があるので、必ず最初に目的を決めましょう。
2.ターゲットに合った認知手法を選べる
コンテンツマーケティングの目的がはっきりしていると、ターゲットに合う手法で認知拡大を図れます。コンテンツマーケティングのターゲットは、設定した目的に合わせてペルソナを設計します。不明瞭な目的をもとに作ったペルソナだと、自社との本来の接点がわかりません。
例として、「頻繁にSNSを使う25歳女性」のペルソナを作ったとしましょう。自社の本来のターゲット層と合致しているペルソナであれば、SNSが接点の1つとなるのでSNS広告は有効な認知手法となります。
しかし、本来のターゲット層にSNSを使う人が極端に少ない場合、いくらSNS広告を展開しても意味がありません。こうした認知手法のずれを招く恐れがあるため、施策の軸となる目的設定が大切なわけです。
3.外部連携がスムーズになる
コンテンツマーケティングの一部または全てを外部委託する場合、目的が決まっているとスムーズな連携が可能です。委託先は自社との共通認識をもとに、さまざまなコンテンツや認知手法の中から最適な施策を行ってくれるでしょう。
仮に記事制作をコンテンツ制作会社に依頼するのであれば、自社メディアの目的やペルソナなどの方向性を伝えます。制作会社は方向性にもとづいて記事を作るため、チェック時に「うちのメディアのニーズと違う」と修正を繰り返す手間が減るでしょう。
全体的な運営代行を依頼するケースでも、ヒアリングでコンテンツマーケティングを行う目的を伝えれば、自社の要望に沿った具体的な提案が期待できます。外部連携をしようと思っている場合は、明確な目的設定が一層重要です。
4.成果が出ずに頓挫するリスクを抑える
ここまで「コンテンツの方向性がぶれない」といった3つの利点を説明してきましたが、言い換えれば目的がないコンテンツマーケティングは次のような事態を招くかもしれません。
- コンテンツの方向性が迷走する
- 認知手法を間違えてメディアが広まらず集客できない
- 連携に手間取ってコンテンツの公開スピードが遅い、読者が定着しない
こうした状況に陥ると、改善しない限りコンテンツマーケティングの成果は出にくいでしょう。施策にかかったコストの回収前に頓挫するリスクがあるため、目的は必ず設定しましょう。
目的の達成度はコンバージョンで確認しよう

設定した目的の達成度は、Webマーケティング全般で用いられる「コンバージョン」で適宜確認する必要があります。確認しないと、施策が上手くいっているのか改善すべきなのかの判断がつきません。
コンバージョンとは、Webサイトやメルマガで計測できる数値です。商品購入や問い合わせといったユーザーの行動をツールで数値化し、施策改善や継続の目安に活用します。「コンバージョン=コンテンツマーケティングの目的」と定義できそうですが、一概には言えません。ファン化やブランディングなど、目に見える数値がない目的もあるからです。
コンバージョンの例
具体的なコンバージョンは、以下の例をご覧ください。
- 商品購入
- 問い合わせ・資料請求
- サービス申し込み
- 予約
- 会員登録・メルマガ登録
- 無料トライアル・デモの申し込み
- イベント参加申し込み
一般的には、コンテンツやペルソナに合わせて複数のコンバージョンを設定します。「商品購入」が目的のコンテンツマーケティングで言えば、ユーザーが購入に至るまでに行う可能性がある「資料請求」「問い合わせ」「会員登録」もコンバージョンにすると良いでしょう。ユーザー視点で行動を分析し、適切なコンバージョンを考えてみてください。
コンバージョンの種類
コンバージョンの例を挙げましたが、発生条件やカウント方法によってさまざまな種類があります。施策の効果検証や改善を正しく行うには、コンバージョンの違いを理解することが大事です。ここでは、主な6種類のコンバージョンを紹介します。
1.直接コンバージョン
直接コンバージョンとは、広告から自社のWebサイトに訪れたユーザーが、そのままコンバージョンを起こした数値です。具体的には「リスティング広告をクリックしてLPに訪問し、離脱せずにLPから商品を購入」というケースで1回とカウントされます。
2.間接コンバージョン
間接コンバージョンとは、広告から自社のWebサイトに訪れたユーザーが、一旦離脱してから再訪問した際にコンバージョンした数値です。ユーザーが途中で訪れたチャネルを示す「コンバージョン経路」を把握すれば、「ユーザーはどのような行動を取りコンバージョンするのか」を明らかにできます。そのため、直接コンバージョンと間接コンバージョンはどちらも重要です。
3.ユニークコンバージョン
ユニークコンバージョンとは、コンバージョンしたユーザー数をカウントする数値です。つまり、1人のユーザーが「資料請求」と「商品購入」の2回コンバージョンを起こしても、ユニークコンバージョンは1件と数えます。ユーザー単位の数え方ですので、「コンバージョンした人数」を知りたい場合に使うと良いでしょう。
4.マイクロコンバージョン
マイクロコンバージョンは、施策の最終目的となるコンバージョンの中間に設定します。「商品購入」を最終目的とする場合、手前に「会員登録」「サンプル請求」「カートに商品を入れる」といったコンバージョンを設定するかと思います。これらすべての中間地点が、マイクロコンバージョンです。中間地点を計測することで、KPIの指標やユーザーの行動分析に活用できます。
5.クリックスルーコンバージョン
クリックスルーコンバージョンは、ユーザーが広告をクリックし、一定期間内にコンバージョンを起こすとカウントされます。広告クリエイティブの訴求力の高さを判断する際に役立つ指標です。
6.ビュースルーコンバージョン
ビュースルーコンバージョンは、広告を見ただけでクリックしなかったユーザーが、一定期間内にコンバージョンした場合に生じます。クリックスルーコンバージョンのみ計測すると「クリックされない広告=広告効果がない」と判断しがちですが、ビュースルーコンバージョンを見ることで広告効果を正しく評価できます。「その場ではクリックされなかったが、ユーザーが後から気になってコンバージョンした」という行動のきっかけになったとわかるからです。
▼コンテンツマーケティングの効果測定については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
コンバージョンの改善方法
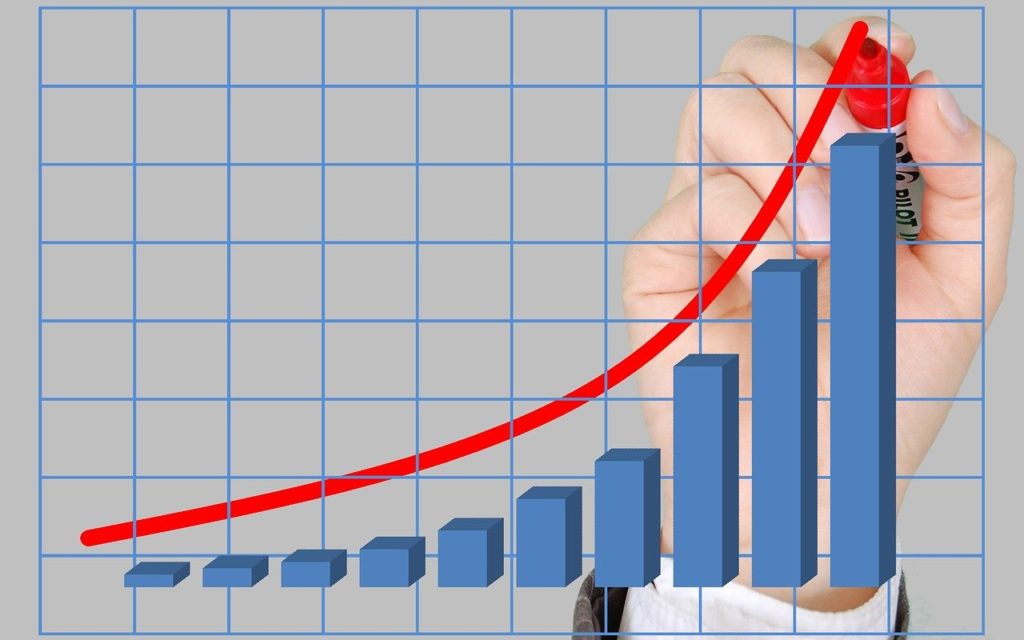
コンバージョンがうまく発生しない場合は、状況に合わせて改善しましょう。下記7つの改善方法を参考にしてみてください。
- 流入経路を増やす
- 導線設計を再構築する
- コンテンツの質を高める
- デザインを改善する
- 広告のターゲティング設定・バナーを変更する
- 複数のコンバージョンを設ける
- A/Bテストを実施する
以上について、考えられる原因と合わせて解説します。
1.流入経路を増やす
コンテンツマーケティングの初期段階によくあるのが、メディアへのアクセス数が少ないケースです。母数であるアクセス数が少なければ、比例してコンバージョンも少なくなります。アクセス数を増加させるために、まずは次の基礎的な施策でメディアへの流入経路を増やしましょう。
- 記事コンテンツのSEO対策を施す、改善する
- SNSを運用する、投稿頻度を上げる
- Web広告を出稿する、広告の種類を変える
- プレスリリース配信サイトで情報発信する
こうした方法でユーザーに見つけてもらえる機会を増やすと、アクセス数向上が見込めるでしょう。
2.導線設計を再構築する
導線設計の再構築は、コンバージョン率(CVR)改善に期待できます。アクセス数に比例してコンバージョンが伸びない「CVRが低いサイト」は、導線に問題があるかもしれません。せっかく集めたユーザーを離脱させないよう、コンテンツ同士の内部リンクを増やしたり、導線上に必要なコンテンツを作成したりしてコンバージョンに繋げましょう。
また、過剰なコンバージョン設置も、ユーザーが離脱する要因となります。たとえばリードを獲得したいからといって、記事に何度も資料請求リンクを貼るのはおすすめできません。不自然な設計にならないよう注意しつつ、導線を見直してみてください。
3.コンテンツの質を高める
コンテンツマーケティングにおいて重要なコンテンツの質は、コンバージョンに影響します。閲覧する価値の低いコンテンツばかり作っていると、ユーザーから信頼を得られずコンバージョンに至りません。コンバージョンを狙うコンテンツだけでなく、疑問解決や活用方法などの有益な情報も発信しましょう。
法律や医学といった専門分野のコンテンツであれば、専門家に監修してもらうのも1つの手です。ユーザーに信頼性が高いメディアと判断されれば、コンバージョンへ誘導しやすくなります。ペルソナを分析して、「誰がどのような情報をなぜ知りたいのか」を洗い出しましょう。
4.デザインを改善する
サイトのデザインやUIが見づらいと、コンバージョンを起こす前にユーザーが離脱してしまいます。現在のデザインおよびUIに問題点はないか、以下の改善例をチェックしてみてください。
- 過剰装飾や画像を減らしてページの表示速度を上げる
- 詰まりぎている文字間隔を開け、読みやすくする
- 入力フォームの項目を減らす
- レスポンシブデザインに対応してスマホからも見やすくする
- コンバージョンに繋げる「CTA」のボタンやリンクをわかりやすくする
ユーザーにとって見やすいデザインを心掛け、サイトを設計しましょう。
5.広告のターゲティング設定・バナーを変更する
Web広告を出稿しても成果が出ない場合、広告のターゲティング設定を再検討してみてください。広告を配信しているターゲットが、自社の顧客層とずれているかもしれません。
ターゲティング設定はユーザーの属性だけでなく、地域や時間帯、リマーケティング、デバイスといった項目を細かく指定できます。ペルソナとターゲティング設定を見直し、広告効果を改善しましょう。
加えて、バナー広告のデザインも重要です。バナークリエイティブの魅力が低いとクリックされないばかりか、興味すら持ってもらえません。クリックはしないものの別経路でコンバージョンする「ビュースルーコンバージョン」が発生しないのであれば、バナー広告の変更が必要と言えます。
6.複数のコンバージョンを設ける
コンバージョンを1つしか用意していない場合は、複数設けましょう。コンバージョンを設置する目的は、施策の成果を確認するためです。コンバージョンが1つしかないと判断材料が極端に少ないため、ユーザーのニーズを掴むのが難しくなります。間違った施策に走るリスクが高まるので、判断材料を増やすことが大事です。
新たにコンバージョンを追加する際は、ユーザーの状態に合わせて設定します。商品購入に近いユーザーは「サンプル請求」や「カート追加」、商品・サービスの調査段階のユーザーには「資料請求」など、細かくコンバージョンを作りましょう。
7.A/Bテストを実施する
コンバージョンの改善策が固まったら、A/Bテストを実施すると具体的な効果検証が可能です。A/Bテストとは、Webサイトや広告のデザインを2パターン作って効果を比較する検証方法です。ユーザーにはAパターンかBパターンをランダムで表示し、成果が高いほうを採用します。
A/Bテストのメリットは、2つのパターンを同時に検証できる点です。通常のデザイン変更の場合、変更後のコンバージョンが良くても「その時期にSNSで拡散された」といった外的要因で偶然向上した可能性を排除できません。A/Bテストは同時期に行うため、外的要因の影響を極力減らした状態で改善案を試せます。
コンテンツマーケティングは今後も続く?

従来のマーケティング手法からコンテンツマーケティングに移り変わりつつあるように、コンテンツマーケティングもいずれは廃れるのでしょうか。結論を先に伝えると、断言はできないものの今後もなくなる可能性は低いと言えます。
理由の1つが、コンテンツマーケティングの歴史の長さです。コンテンツマーケティングはインターネットが身近になるにつれて広まりましたが、手法自体は最新のものではなく以前から存在しています。一例が、1920年から販売されているグルメブック「ミシュランガイド」です。発行元はフランスのタイヤメーカーですが、自動車による旅行を促進してタイヤ販売へ繋げるために発行しました。つまり、ミシュランガイドは、タイヤメーカーによるコンテンツマーケティングとして始まったわけです。
コンテンツマーケティングは、その概念を示す言葉がない時代から存在し、有用な手段であり続けています。現代の消費者行動との相性も良いため、今後もコンテンツマーケティングは続いていくのではないでしょうか。
過去に流行したマーケティング手法
コンテンツマーケティングのように長年続く手法がある一方で、ピークが過ぎたマーケティング手法もあります。過去に流行したマーケティング手法を2つ見てみましょう。
1.フラッシュマーケティング
フラッシュマーケティングとは、期間限定セールなどで集客するマーケティング戦略です。日本国内では2010年ごろに「クーポン共同購入サイト」の形で流行しました。期間内に一定人数が商品を購入すると、割引クーポンをもらえる形式です。
企業にとってはリピーターを獲得しづらい上に負担が大きく、ブランディングに悪影響が出るリスクもある手法でした。次第に下火になり、現在のフラッシュマーケティングは、ECサイトが行う一般的なセールが中心です。
2.売り込み型マーケティング
売り込み型マーケティングとは、企業が主体となって消費者にアプローチする手法です。一時的な過去の流行ではなく、コンテンツマーケティング以前に主流だった方法と言えます。
インターネットが普及した現代は、消費者が主体となって知りたい情報を探せます。消費者の行動変化により、企業が知ってほしい情報を届けるだけの一方的な宣伝は通用しなくなりました。そのため、消費者が求める情報を伝えるコンテンツマーケティグにトレンドが移ったわけです。
マーケティング4.0とコンテンツマーケティングの関係性

2022年現在は「マーケティング4.0」の時代と呼ばれているとご存知でしょうか。コンテンツマーケティングとどのように関連するのかを解説します。過去との違いをわかりやすくするため、これまでの1.0〜3.0まで順番に確認しましょう。
1.製品中心の時代「マーケティング1.0」
マーケティング1.0は、大量生産・大量消費時代である1970年代以前のマーケティング概念です。当時は現代に比べてあらゆるモノが不足しており、供給が需要に追いついていませんでした。作った分だけ売れたため、製品中心の時代と言われています。
2.消費者主導の時代「マーケティング2.0」
1970年代から、消費者中心のマーケティング2.0が始まります。モノの供給量が増え、消費者が主導して商品・サービスを選べるようになりました。価格競争も生じ、企業は単に値段を下げるだけでなく「消費者が求めるモノは何か」を考える必要性が生まれた時代です。
3.付加価値の時代「マーケティング3.0」
マーケティング3.0の1990年代以降は、商品・サービスに付加価値が求められるようになります。市場にモノはさらに増えた上に、機能性が優れているのは当たり前になったからです。企業は環境保護や教育支援といった「社会的責任」を果たすことで、商品・サービスに機能性以外の価値を生み出しました。
4.自己実現の時代「マーケティング4.0」
2010年から現在まで続くのが、マーケティング4.0です。現在は、企業による社会貢献活動はさほど珍しくありません。付加価値があって当然の時代になり、さらにSNSの普及も受け、商品やサービスを使うことによるイメージが重視されるようになりました。端的に言えば「このブランドの製品を使うとおしゃれ」といったイメージです。
「なりたい自分」の姿を叶えるためにモノが選ばれることから、自己実現の時代と言われます。「なりたい自分」の実現に必要なモノと思われるために、コンテンツマーケティンによるブランディングやファンの育成が重要になるわけです。
コンテンツマーケティングを行う際は目的を理解してから戦略を立てよう
コンテンツマーケティングの目的は、「商品の購買」や「ブランディング」などさまざまです。目的が異なると、適しているコンテンツや認知拡大手法も変わります。
コンテンツマーケティングの目的が定まっていないと、最適な施策を選べないかもしれません。施策決定の基礎となる目的を最初に設定してから、具体的な戦略設計を行いましょう。