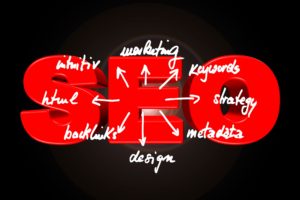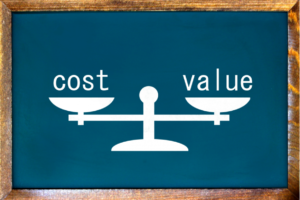オウンドメディアの運用には記事制作が欠かせません。しかし、手順や知っておくべき事前知識などを理解しないまま記事制作に取り組むと、大きな時間のロスや成果への回り道となってしまいます。
まずは、基本的な知識や流れを把握してから、記事制作に取り組むべきです。本記事では、Webマーケティング担当者に向けて、オウンドメディアの記事制作手順や知っておくべきポイント、記事作成を効率化する方法を分かりやすく解説します。
オウンドメディアについて知りたい方は以下の記事もご参照ください。
オウンドメディアの記事制作で知っておくべき3つの知識

オウンドメディア運用の目的は、Googleの検索画面に記事を上位表示させることです。Googleで上位表示を狙うためには、以下3つの知識をしっかりと理解する必要があります。
- SEOの本質
- Googleが掲げる10の真実
- 網羅的な記事が評価される理由
以下では、3つの知識について解説します。
SEOの本質
SEOに関する知識やテクニックは数多くあります。知識やテクニック以上に大切なのが、SEOの本質です。SEOの本質を理解していなければ、上位表示できる記事制作をするのは難しいです。
SEOの本質は、ユーザーの悩みや課題を解決することにあります。私たちがGoogle検索をするとき、「~について知りたい」や「~を買いたい」などのニーズを持っています。そしてGoogleは、ユーザーのニーズに応えられるサイトページを上位に表示するのです。
つまり、Googleで上位表示を狙うためには、ユーザーが抱えている課題を解決できる記事制作をする必要があります。
「このキーワードで検索したユーザーの悩みは? どのような役立ち情報を求めているのか?」のように、常にユーザー視点で記事制作をしましょう。
Googleが掲げる10の事実
オウンドメディアの記事制作に取り組む場合は、Googleが掲げる10の事実を理解しておくべきです。Googleが掲げる10の事実とは、Googleが大切にする理念となります。以下が10の事実の一覧です。
- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
- 遅いより速いほうがいい。
- ウェブ上の民主主義は機能する。
- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。
- 世の中にはまだまだ情報があふれている。
- 情報のニーズはすべての国境を越える。
- スーツがなくても真剣に仕事はできる。
- 「すばらしい」では足りない。
引用:Google「Googleが掲げる10の真実」
https://about.google/philosophy/?hl=ja
Googleが掲げる10の事実から分かることは、Googleはユーザーの利便性の向上に注力している点です。ユーザーが求める情報を含んだ記事を上位表示にするのは当然ながら、検索結果の表示時間や関連性の低い情報の排除など徹底的なユーザー視点で事業を行っています。
Googleが掲げる10の事実を理解すれば、ユーザー視点での記事制作やサイトスピードを向上させるべき理由が分かるはずです。オウンドメディアの記事制作においては、Googleと共にユーザーの利便性を高めるマインドセットが必要となります。
網羅的な記事が評価される理由
Google検索をしたとき、Webページだけではなく、YouTubeやGoogleマップなどが検索結果画面に表示されることがあります。例えば、「英語 シャドーイング」と検索すると、下記要素で構成された検索結果画面が表示されます。
- 広告(自然検索ではない結果)
- YouTube動画
- Webサイト
- 書籍
シャドーイングとは、お手本教材のすぐ後を追って発音する学習法を意味します。「英語 シャドーイング」と検索したユーザーニーズの1つに、「実際にシャドーイングをしたい」というものがあります。
シャドーイングの手順を紹介しつつ、実際にシャドーイングもできるコンテンツとして、GoogleはオウンドメディアよりもYouTubeが最適と判断しているのです。
この例のように、Googleは検索ワードに潜む複数ニーズに応えられる検索結果画面を構築します。そのため、ユーザーの様々なニーズを把握し、多くのユーザーの悩みを解決できる記事制作をしなければいけません。
こういった理由で、網羅的な記事が評価される傾向にあります。
上位表示されるオウンドメディアの記事の特長

ユーザーのニーズに沿った情報を含めるだけでは、Googleでの上位表示は難しいです。情報の網羅性に加え、以下3つのポイントもおさえる必要があります。
- 正確な情報
- 高い独自性
- 読みやすい文章
ここからは、上位表示される記事制作に必要な3つのポイントを解説します。
正確な情報
E-A-Tとは、Googleが公開しているコンテンツ評価基準の1つです。E-A-Tは以下3単語の頭文字を合わせた造語になります。
- E:Expertise(専門性)
- A:Authoritativeness(権威性)
- T:Trustworthiness(信頼性)
E-A-Tは記事の専門性と信頼性を測る重要な評価基準です。たとえユーザーニーズを正確に把握し、情報を網羅的に含んだ記事制作をしたとしても、情報が間違っていれば評価はされません。
E-A-Tを高めれば、記事は高く評価され、上位表示される確率は高まります。E-A-Tを高める方法は下記の通りです。
- サイト運営者(もしくは記事執筆者)の情報を明らかにする
- 専門家の協力を得る
- 専門家の実績や権威をプロフィールで伝える
- 一次情報で記事制作する
- 最新情報を含める
高い独自性
Google検索においては、同じワード検索でも多様な検索結果が上位表示されることがあります。特定のワードで検索したとき同じ内容の記事ばかり表示しては、ユーザーの利便性は向上しないからという理由である可能性が考えられます。つまり、競合と同じ内容の記事を制作するだけでは、上位表示は難しいといえるのです。
必要な情報を網羅的に含めることに加え、独自性も入れると高評価へとつながる可能性があります。独自性を出す方法としては、ユーザーヒアリングやアンケート調査などが有効です。調査にかける時間や費用がない場合は、参考にした情報を図解にしてまとめることをおすすめします。
読みやすい文章
とあるWebユーザビリティ調査の結果として、「ユーザーはWebページの20%程度のテキストしかしっかり読まない」というデータがあります。Web記事は丁寧に読んでもらえないからこそ、シンプルで分かりやすい文章を執筆しなければいけません。
少しでも読むのに負担がかかると、ユーザーは離脱してしまいます。最後まで記事を読んでもらうためには、読みやすい文章およびコンテンツ設計が欠かせません。読みやすい文章を作るポイントは以下の通りです。
- ひらがなの割合を多くする(例えばひらがな:漢字=7:3 など)
- 箇条書きを用いる
- 画像や図解を適宜挿入する
- 1文を短くする
また、ユーザーはWeb記事を深く読まない可能性がある点を踏まえると、優先順位の高い情報(=ユーザーが最も知りたい情報)から紹介するのも読了率アップに貢献します。
オウンドメディアの記事制作の手順
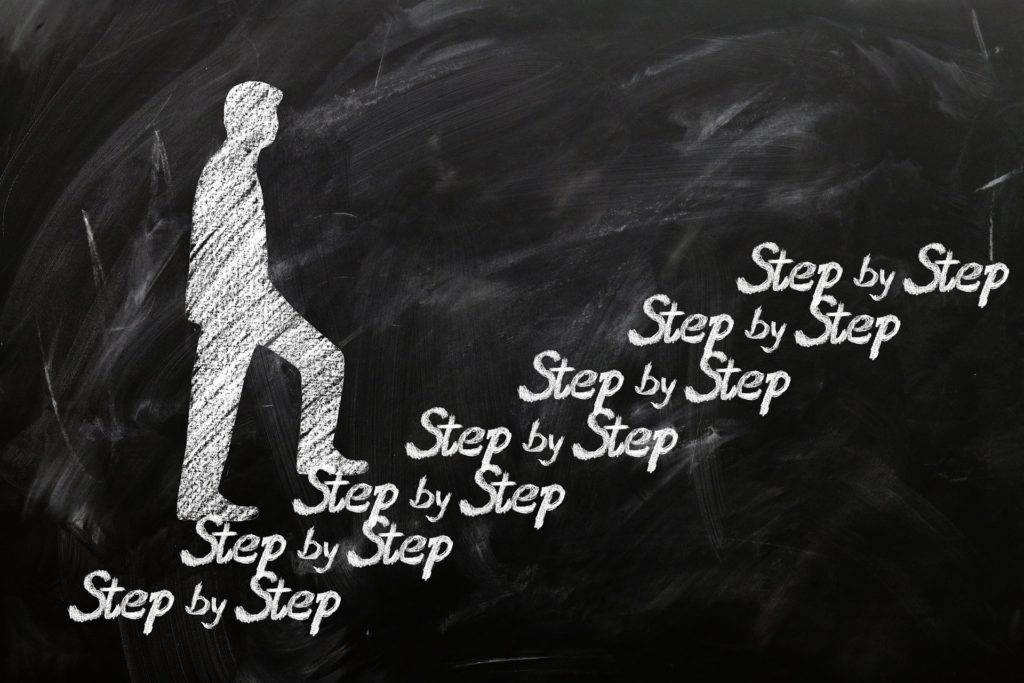
ここからは、オウンドメディアの記事制作の手順を解説します。制作手順を把握することで、効率よく記事制作を進められるようになります。
キーワード選定
まずは自社製品サービスと関連するキーワードを選定します。キーワード選定の手順としては、ビッグワード(1語からなる検索ボリュームが多い単語)を軸(=テーマ)にし、それに関連するキーワードを考えるのがおすすめです。
例えば、住宅ローンの相談会社がオウンドメディア運営に取り組むとします。この場合、軸となるキーワードは「住宅ローン」であり、以下のような類のワードが関連キーワードとなります。
- 住宅ローン おすすめ
- 住宅ローン 借り換え
- 住宅ローン 比較
- 住宅ローン 滞納
- 住宅ローン 滞納 何回まで
- 住宅ローン 滞納 差し押さえ
2語以上の単語を組み合わせたキーワードは、検索ボリュームが少ないです。しかし、ユーザーニーズが明確であり、競合も少ないことから、オウンドメディア運用初期には積極的に狙いたいキーワードでもあります。
ユーザーの悩みの把握
各キーワードに潜むユーザーの悩みや課題を把握します。ユーザーの悩みを正確に把握できれば、記事に必要な情報が判明するため、丁寧に行いましょう。
ユーザーの悩みを把握するには、競合分析が有効です。実際にキーワード検索を行い、上位10記事(もしくは20記事)の記事内容をエクセルやスプレッドシートにまとめましょう。そうすれば、共通する情報や必要なボリューム感が分かります。
また、BtoB企業の場合は、自社や他社の成功事例もユーザーの悩み把握に有効です。多くの事例には、ユーザーの課題が記載されています。事例で紹介されているユーザーの課題を参考に、必要な情報を考えましょう。
タイトルと構成案の作成
まずは構成案を作成してから、執筆に移ります。執筆前に構成案を設定することで、記事の方向性をチェックでき、イメージとかけ離れた記事制作を防止できます。特に外部ライターに依頼する場合は、必ず自社で構成案を作成する、もしくはライターに構成案を提出してもらいましょう。
執筆中に記事構成は多少変わるため、この時点では大まかな内容で問題ありません。しかし、タイトルは丁寧に作成するべきです。タイトルとは、記事で伝えたい内容をまとめたものです。タイトルが決まれば、記事の方向性が定まり、統一性のある記事制作を行えます。
情報収集
構成案にもとづいて必要な情報収集をします。必要な情報を網羅的に集めるのは当然ながら、一次情報や最新情報を入れる余地はないかまで確認しましょう。例えば、競合が古い情報を載せている場合、最新情報を加えるだけで大きな差異化となります。
インターネットや書籍、公表されている調査結果・資料、アンケート調査などを利用して、信頼性の高い情報を集めましょう。
記事制作
必要な情報を集めたら、記事制作へと移ります。すでに分かりやすい文章を書くポイントは説明しましたので、ここでは推敲の重要性を解説します。
まずは、思うがままに記事執筆をしましょう。記事が完成したら、推敲を重ねます。形容詞の削除や一文の短縮化、不要な文章の削除などをして、記事の精度を高めましょう。記事執筆の翌日など時間を空けて行うことで、客観的な視点で推敲できるようになります。
推敲を終えたら、必要に応じて画像や図表の挿入をして、記事制作完了です。
▼オウンドメディアにおける記事の制作手順については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
オウンドメディアの記事制作後にするべきこと

記事は公開して終わりではありません。定期的にリライトをする必要があります。例えば、公開から1年以上たっても上位表示されない場合、ユーザーが求める情報を提供できていない可能性があります。
また、ユーザーニーズや情報の鮮度は時間と共に変化するため、リライトで常に鮮度の高さを維持しなければなりません。
オウンドメディアの記事制作で必要なスキル
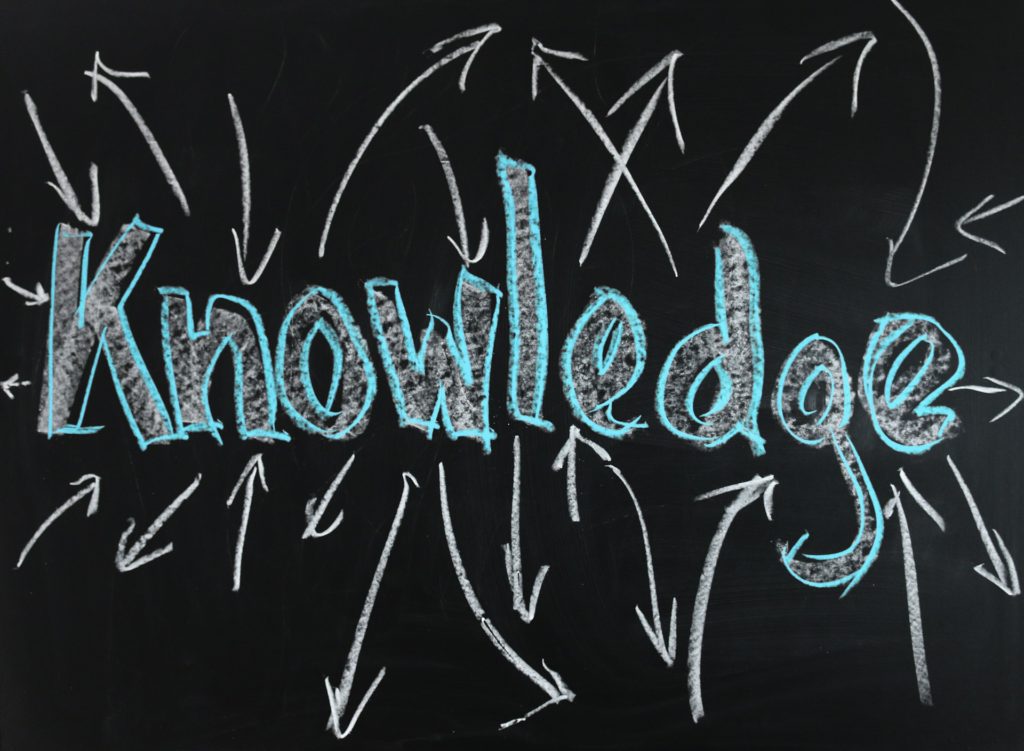
ここからは、オウンドメディアの記事制作で必要なスキルを紹介します。
Webライティング
Webライティングスキルとは、必要な情報を分かりやすい文章で執筆するWebスキルを示します。オウンドメディアの記事制作において、Webライティングスキルが必要な理由は、以下2つです。
- ユーザーはWeb記事を丁寧に読まないため
- ユーザーが悩みや課題を解決できる理由を求めるため
Webライティングスキルを身につければ、ユーザーが求める情報を端的に提示できるようになります。
SEOの知識
Googleで上位表示を狙う場合、SEO知識は欠かせません。SEO知識の具体例は以下の通りです。
- タイトルや見出しにキーワードを入れる
- 外部からのリンクを増やす
- 表示スピードを改善する
- 内部リンクの最適化
例えば、ユーザーニーズを満たした分かりやすい記事を制作しても、記事の表示スピードが遅ければ、ユーザーに読んでさえもらえません。このように、上位表示を狙うためには、オウンドメディアの最適化も必要です。
また、SEO知識を身につけることで、Googleに評価されやすい記事制作ができます。
オウンドメディアの記事制作は外注化するべきか

オウンドメディアの記事制作は、インハウス(社内)で行うことも可能です。しかし、SEO業務はキーワード選定や技術的な対応、分析と改善など多岐にわたります。これらの業務に加えて、記事制作まで社内で行うのは、社内メンバーに大きな負担がかかります。
そこで、記事制作を外部ライターに依頼することも検討しましょう。外部ライターに記事制作を依頼すれば、社員はより重要性の高いキーワード選定や分析改善などに注力できます。ライターに外注する際は、ノウハウやルールをまとめたレギュレーションを用意すると、記事の品質を保てます。
▼オウンドメディア制作時のライター募集手段については、こちらの記事で詳しく解説しています。
オウンドメディアの記事制作の外注費用相場
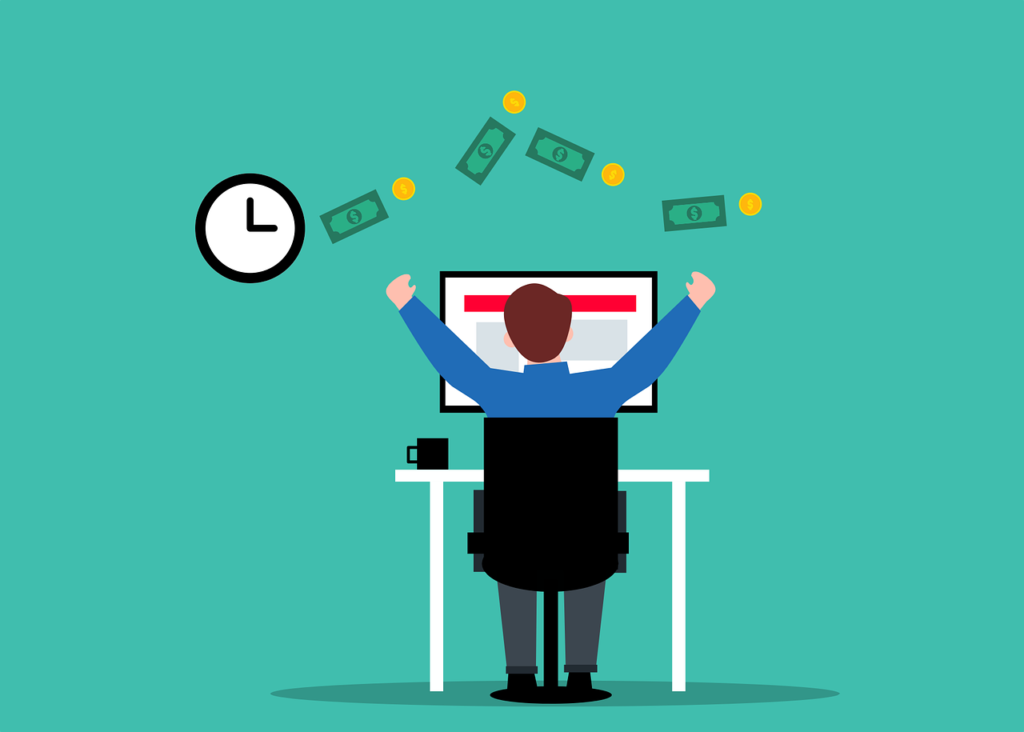
記事制作の外注費用は様々です。クラウドソーシングを使えば、1文字1円など比較的割安価格でライターに依頼できます。しかし、レベルが低いライターを採用した場合、多くの修正作業が発生するデメリットもあります。
編集会社に記事制作の代行を依頼した場合の相場は、1記事数万円です。しかし、質の高い良い記事を制作してくれるため、修正作業はほぼ発生しません。また、上位表示できる可能性も高くあります。
上位表示された記事は、長期間にわたって大きな集客効果を出すと考えると、コストパフォーマンスは高いです。
まずはオウンドメディア運営に割ける毎月の予算を出します。予算が決まれば、記事制作を外注化するのかどうか、外注化するのなら誰に依頼するのかを要検討しましょう。
▼オウンドメディア制作時の外注含むさまざまな費用については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
オウンドメディアの記事制作にはツールの導入がおすすめ

オウンドメディアの記事を1本完成させるためには、「キーワード選定→競合分析→構成案作成→記事執筆→分析改善」と複数のステップを踏みます。全てのステップを人間の手で行うのは、あまりにも時間がかかり、効率的ではありません。
現在は、多くの企業が無料を含むSEOツールを提供しています。SEOツールを導入すれば、キーワード選定や競合分析などの自動化・効率化が可能です。SEOツールを活用することで、スピーディーに高品質の記事制作ができるため、早い段階での成功にも期待できます。
費用対効果は高いので、SEOツールの導入を検討するのもおすすめです。
ユーザーの課題解決を意識した記事制作を!
オウンドメディアの運営で成果を上げるには時間がかかります。しかし、根気強く記事制作を続けることで、徐々にサイト訪問者数やSNSでのシェア数は増え、上位掲載される記事も出てくるはずです。
SEO対策は、リスティング広告とは異なり、クリックごとに費用は発生しません。それでいて上位表示できれば、大きな集客効果を見込めるため、費用対効果の高い施策と言えます。
オウンドメディアの記事制作では、常にユーザー視点を持つことが重要です。「ユーザーの課題は何か?この情報で課題を解決できるか?文章は読みやすいか?」などを自問自答しつつ、戦略的に記事制作に取り組みましょう。