近年、目や耳にする機会が増えた「オウンドメディア」。企業マーケティングの一つとして、さまざまな企業から注目を集めていますが、漠然としか理解できていないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、オウンドメディアの基礎知識を徹底解説。意味はもちろん、運営する目的や注目されている背景、活用する上でのメリット・デメリットなど、オウンドメディアへの理解が深まる情報をまとめています。オウンドメディアについて学ぶのに役立つ書籍も紹介していますので、合わせてチェックしてみてください。
オウンドメディアの意味とは?


オウンド(owned)とは、所有するという意味を持つ言葉です。これに、メディア(media)を組み合わせたオウンドメディアは、「企業が自分たちで所有するメディア」という意味を持ちます。では、具体的にどんなメディアをオウンドメディアと言うのでしょうか。
オウンドメディアとは?
オウンドメディアは、その意味の通り、自社で管理や運営をしているメディアのことを指します。多くの場合、企業が運営するWebサイトやブログなどを指す言葉として使われるため、オウンドメディア=企業所有のWeb媒体と認識している方もいるかもしれません。
もちろんこれも間違いではありませんが、より広い意味でオウンドメディアを捉えると、広報誌やパンフレットなどの紙媒体のメディアも含まれます。つまり広義では、企業が運営し、情報発信する媒体は、Webや紙を問わず、オウンドメディアであると言えます。
オウンドメディアとは?
企業が所有するWebサイトというと、会社の概要などが記載されたホームページを思い浮かべる方もいるでしょう。広義としては、こうした企業のホームページもオウンドメディアですが、一般的にオウンドメディアという言葉が使われるときは、より狭い意味を指していることが多いです。
企業のホームページが、事業内容やアクセス情報などといった変化が少ない基本的な情報を案内しているのに対し、狭義のオウンドメディアは、ユーザーに有益な情報を発信・更新し、それらを積み重ねているメディアのことを指します。
オウンドメディアは、使われている場面によって意味合いが異なるため、どのような意味で使われているのか考えることが大切です。以降では、狭義のオウンドメディアに関する内容を中心に紹介していきます。
コンテンツマーケティングとの関係性


オウンドメディアと関連して押さえておきたいのが、「コンテンツマーケティング」です。コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって有益となるコンテンツを配信することで、ファンの獲得や商品の販売、リピーターの育成などを行うマーケティング手法の一つです。
コンテンツマーケティングの一環として、オウンドメディアを活用する企業も少なくありません。さらに、オウンドメディアとそれ以外のメディアなど、目的に応じて複数のメディアを合わせて活用することもあります。
オウンドメディアとトリプルメディア・PESOモデル


オウンドメディアと合わせて取り上げられることが多い、「トリプルメディア」と「PESOモデル」。どちらも企業がマーケティングとして活用するメディアの分類に関する考え方で、オウンドメディアは、これらを構成するメディアの一つです。
トリプルメディアとは?
トリプルメディアは、オウンドメディアのほか、ペイドメディア、アーンドメディアという3つのメディアで構成されます。いずれも異なる特徴を持つメディアのため、状況に合わせて活用していくのが望ましいです。各メディアの特徴は次の通りです。
オウンドメディアが自社所有のメディアなのに対し、ペイドメディアは新聞やテレビ、雑誌など広告費が発生するメディア、アーンドメディアはTwitterやFacebookなどのSNSに代表されるような情報を拡散するソーシャルメディアなどのことを指します。
PESOモデルとは?
トリプルメディアに変わる考え方として注目されているのが、PESOモデルです。トリプルメディアが3つの分類だったのに対し、PESOモデルは、オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディア、シェアードメディアの4つに分類されます。
オウンドメディアとペイドメディアについては、トリプルメディアと同じですが、アーンドメディアはパブリシティ活動などを通して拡散するメディア、シェアードメディアはSNSなどのソーシャルメディアと、より細かく分かれているのが特徴です。
企業がオウンドメディアを運用する目的


さまざまな企業がオウンドメディアを運用していますが、その目的とは何なのでしょうか。オウンドメディアを運用する目的は、企業によって異なり、場合によっては複数の目的を持って運用しているケースもあります。ここでは、いくつかの目的を紹介します。
滞在顧客の認知・接触
自社の製品やサービスを購入してもらうためには、まずは顧客となる人たちにその存在を知ってもらう必要があります。そのため、滞在顧客の認知や接触を目的としてオウンドメディアを運用する企業も多いです。
さらに、接触した滞在顧客を見込み顧客、さらには顧客へと育てて、実際の購入へとつなげる目的を持っている場合もあります。滞在顧客にアプローチできるメディアは他にもありますが、オウンドメディアと合わせて活用することで、より多くの滞在顧客の認知や接触につながります。
リピーター・ファンの獲得
すでに顧客となっているユーザーを、リピーターやファンに育てる目的で運用している場合もあります。オウンドメディアで接触した滞在顧客がコンテンツを通じ、最終的にリピーターやファンになるということもあるでしょう。自社の商品やサービスのストーリーが伝わるようなコンテンツは、企業のブランディングになり、リピーターやファンの獲得につながります。
採用につなげる
オウンドメディアのなかには、採用を目的としているものもあります。採用を目的としたWebサイトというと、採用ページがありますが、オウンドメディアではより企業の魅力を自由に発信できるのが特徴です。社員のコラムやインタビュー、実際の社内の様子などを発信することで、企業の魅力を伝えることができます。
注目を集めるオウンドメディア、その背景は?


今や企業によるオウンドメディアは決して珍しいものではなく、多種多様なオウンドメディアが登場しています。現在のように多くの企業がオウンドメディアに注目し、実際に取り組むようになった背景にはいくつかの理由があります。
広告に対する消費者の反応が変化
一つ目の理由として挙げられるのが、これまでのような広告では、十分な効果を発揮できなくなってきているという点です。近年、スマートフォンが普及したことで、ユーザーを取り巻く環境が変化。SNSなどでユーザー自身が情報を発信することが当たり前の時代となりました。
その結果、情報量が大きく増加し、以前ほど広告による効果が得られなくなってしまいました。こうしたなか、従来の広告を補うものとして、企業主導で情報を発信できるオウンドメディアの価値が高まり、さまざまな企業が注目をしています。
質の高いコンテンツが重視される
第二の理由として挙げられるのが、検索エンジン最大手のGoogleが質の高いコンテンツを重視しているということです。スマートフォンが普及したことで、ユーザー自身が検索し、情報を取りにいくようになりました。
検索順位が上位に表示されるサイトほど、クリック率が高い傾向がありますが、Googleがコンテンツの質を重視したことで、コンテンツマーケティングを実施する企業が増加。その結果、施策の一つであるオウンドメディアにも注目が集まるようになりました。
企業がオウンドメディアを活用するメリットとデメリット
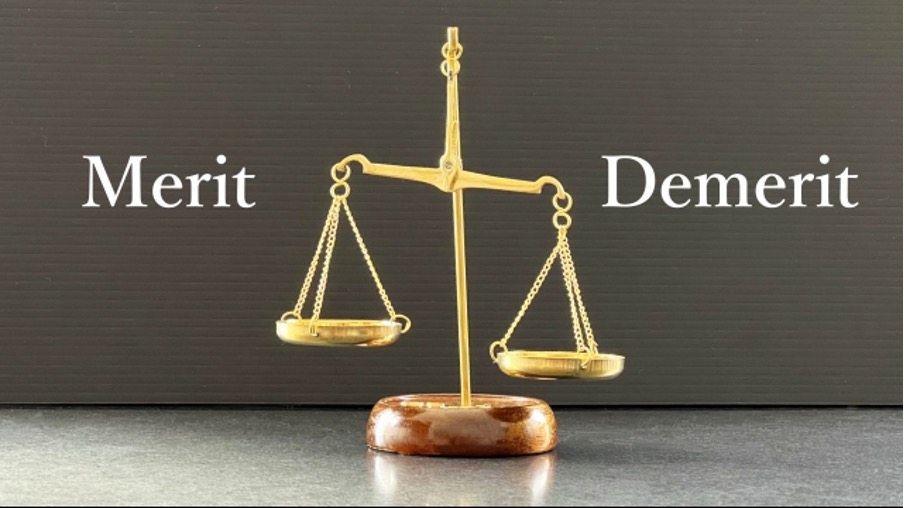
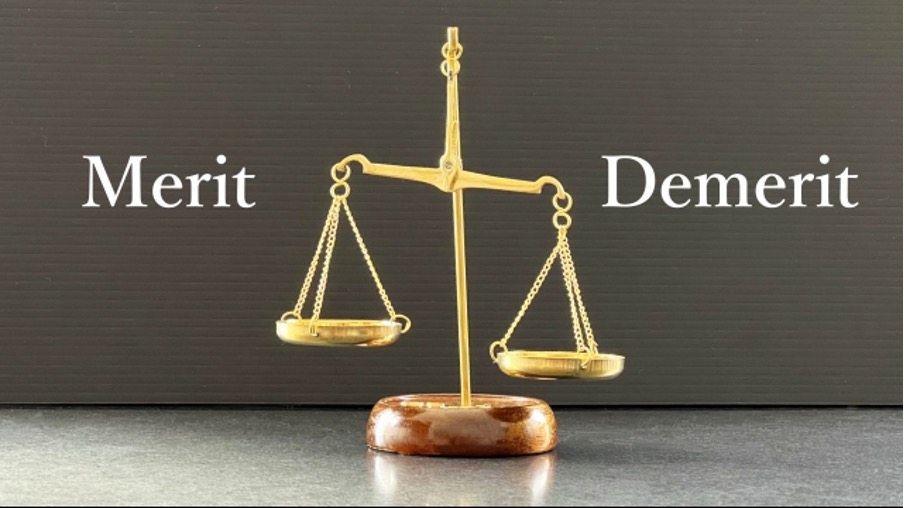
企業がオウンドメディアを活用することで得られるメリットは、次の通りです。前述した、企業がオウンドメディアを運用する目的と通じるところもあるなど、さまざまなメリットを得ることができます。
- コンテンツが資産になる
- 広告費の削減につながる
- 顧客のロイヤリティ向上
- 競合他社との差別化
ストック型メディアであるオウンドメディアの場合、積み重ねたコンテンツがそのまま企業の資産になるという点は大きなメリットです。その結果、オウンドメディア自体が広告の役割を担ってくれるため、広告費の削減にもつながります。
ただし、オウンドメディアには、上記のようなメリットがある一方で、デメリットもある点には注意しなければなりません。例えば、「効果が表れるまで時間がかかる」という点は、オウンドメディアのデメリットの一つと言えるでしょう。効果を得るには、質の高いコンテンツを積み重ねていく必要があるため、すぐに結果が付いてくるわけではありません。オウンドメディアには、時間をかけて取り組む必要があります。
また、「専門知識や費用負担が必要となる」こともあります。昨今、オウンドメディアに取り組む企業が多いため、より効果を実感するためには、ある程度の専門知識が必要となる場合があります。そのため、有料のツールを活用したり、プロに依頼したりする企業も珍しくありません。企業の取り組み方次第で、費用が発生するケースもあると覚えておきましょう。
オウンドメディアを運営するポイント


オウンドメディアを運営している企業は多いですが、その全てが成功しているとは限りません。なかには、残念ながらオウンドメディアの運営が上手くいっていない企業もあります。そこでここからは、オウンドメディアを運営する上でのポイントをご紹介します。
継続して運営する
オウンドメディアのデメリットでもお話しましたが、オウンドメディアは短期間で効果がでるものではありません。商品が購入されるなど、目に見えて効果が表れるようになるのには、時間がかかります。
そのため、効果が見えないからと言ってすぐに運営を辞めてしまうのは、賢い選択とは言えないでしょう。もちろん、ただ運営し続ければ良いというわけではなく、目的を明確にした上で、問題点を改善しながら運営を続けることが大切です。
最終的な目標やゴールの設定
先ほども少し触れましたが、ゴールを明確化した上でオウンドメディアを運営していくことも重要なポイントです。具体的な目標が定まっていないまま運営をしていくと、モチベーションの低下や、本来のゴールとはかけ離れたコンテンツの制作につながってしまいます。
オウンドメディアでは、ゴールに向けて運営ができているかの指標として、KPIを利用することも多いです。KPIとは、重要経営指標などと言われる指標で、目標に合わせてユニークユーザー数や、資料のダウンロード数、ページビュー数などを設定します。そうすることで、目標に向けて前進しているのか数値として判断することができます。こうしたKPIなども活用しながら、目的に合った運営をしていきましょう。
ユーザー目線を大切にする
オウンドメディアでは、ユーザーが求める情報を提供することも大切です。自社の製品やサービスをアピールしたいあまり、ユーザー目線が欠けたコンテンツを提供し続けてしまうと、ユーザーが離れてしまう可能性があります。対象とするユーザーがどんな情報を求めているのかということを意識した上で、コンテンツ制作に取り組むようにしましょう。
SEOやSNSの対策をする
いくらユーザー目線のコンテンツを作成したとしても、実際にユーザーがその情報にたどり着けなければ意味がありません。ユーザーに情報があることを知ってもらうための工夫をしていくことも重要です。
例えば、オウンドメディアのSEO対策をして、検索エンジンでの検索順位を上げるのもその一つです。さらに、TwitterやFacebookといった各種SNSでの拡散を狙うのも、ユーザーの目に触れる機会を増やすことにつながります。
オウンドメディアの意味や運用方法などを学べる本10選


本記事では、オウンドメディアの意味や目的などを解説しましたが、より理解を深めたいという方もいるのではないでしょうか。そこで最後に、オウンドメディアについて学ぶ際に役立つ書籍をピックアップしてご紹介します。
基礎知識を学びたい人に! オウンドメディアの入門書
まずは、オウンドメディアを始めるにあたって入門書を探しているという方や、オウンドメディアの基礎知識を振り返りたいという方に向けた書籍をご紹介します。
・マーケ企画部 四葉幸のハッピーオウンドメディア|インプレス
オウンドメディアの基礎知識を漫画形式で学べる書籍です。オウンドメディアの基本が全8話にまとめられており、可愛らしいイラストと共に、楽しみながら知識を付けることができます。主人公は、食品会社でスパイス&ハーブのマーケティングをしている、四葉 幸(よつば さち)。こちらの漫画では、彼女がオウンドメディアを立ち上げる様子を描いているため、どんな形でオウンドメディアの立ち上げが進んでいくのか、具体的にイメージしながら読むことができます。
▼インプレス 書籍紹介ページ
https://webtan.impress.co.jp/e/2012/12/10/14147
・オウンドメディアのやさしい教科書。|エムディエヌコーポレーション
こちらの本は、タイトルに“やさしい教科書”とある通り、「オウンドメディアとは」という基本的な内容からスタートしてくれる入門書です。オウンドメディアの制作やコンテンツの運用、さらに改善のポイントなど、オウンドメディアの活用に役立つさまざまな内容がまとまっています。最後には、書籍に登場した主要な用語の登場ページが一覧でまとめられているので、改めて用語の意味を確認したいときなどにも重宝しそうです。
▼エムディエヌコーポレーション 書籍紹介ページ
https://books.mdn.co.jp/books/3217203014/
・オウンドメディアのつくりかた|ビー・エヌ・エヌ新社
オウンドメディアを、知る・作る・育てるという章に分けて紹介しています。「知る」では、ケーススタディとして「サイボウズ式」などを扱っているので、事例を通してオウンドメディアについて学べます。「作る」では、コンテンツの制作だけでなく、チーム作りについても網羅。運用開始後のあり方についても書かれており、長いスパンで参考になる内容が乗っている書籍です。
▼ビー・エヌ・エヌ新社 書籍紹介ページ
http://www.bnn.co.jp/books/8769/
・自社のブランド力を上げる!オウンドメディア制作・運用ガイド|翔泳社
オウンドメディアの運用メリットや位置づけなど、基本的な内容を学べるのはもちろん、WordPressを用いたオウンドメディアの構築についても学べます。WordPressについては、インストールの段階から丁寧に紹介されているので、WordPressを使ってオウンドメディアを作成しようと考えている方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
▼翔泳社 書籍紹介ページ
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798147468
・オウンドメディアマーケティング|宣伝会議
全5章に分かれ、企業ウェブの進化から、オウンドメディア概論、さらにはオウンドメディアの構築や運用などについてもまとめられています。最後には、著者の井浦知久氏、大和ハウス工業株式会社の大島茂氏、花王株式会社の本間充氏による座談会も掲載。オウンドメディアで明らかになった課題など、興味深い内容を話しています。
▼宣伝会議 書籍紹介ページ
https://www.sendenkaigi.com/books/sp/detail.php?id=434
分析・改善・SEO対策などオウンドメディアの運用に役立つ本
ここからは、オウンドメディアを実際に運用していく上で役立つ本を5冊紹介していきます。オウンドメディアの改善やSEO対策に役立つ本などをピックアップしましたので、参考にしてみてください。
・オウンドメディアで成功するための戦略的コンテンツマーケティング|翔泳社
コンテンツマーケティング戦略家でコンテンツマーケティング協会の創設者であるジョー・ピュリッジ氏と、同協会の招聘戦略家であるロバート・ローズ氏が手掛けた書籍。オウンドメディアで成功するためのノウハウを学ぶことができます。2部構成になっており、第1部ではコンテンツマーケティングの戦略を、第2部ではコンテンツマーケティングのプロセスが書かれています。
▼翔泳社 書籍紹介ページ
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798130873
・現場のプロがやさしく書いたWebサイトの分析・改善の教科書|マイナビ出版
Webサイトの分析と改善について分かりやすくまとめた本です。ゴールとKPIの設計から始まり、分析、改善についても解説されています。オウンドメディアだけでなく、BtoCサイトやBtoBサイト、SNSなどさまざまなWebサイトの改善策やノウハウを掲載。Googleアナリティクスなどの解析ツールの使用方法も学べます。
▼マイナビ出版 書籍紹介ページ
https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=90593
・できるところからスタートする コンテンツマーケティングの手法88|エムディエヌコーポレーション
タイトルの通り「できるところから始められる」本で、コンテンツマーケティングの実践的な知識がまとめられています。コンテンツマーケティングに関する基本的な知識に加え、BtoB・BtoCごとのオウンドメディアのライティングノウハウや、Webサイト制作、文章執筆時におけるSEO対策など、幅広い内容を取り上げています。
▼エムディエヌコーポレーション 書籍紹介ページ
https://books.mdn.co.jp/books/3218203013/
・沈黙のWebライティング -Webマーケッター ボーンの激闘-|エムディエヌコーポレーション
SEOライティングについて、ストーリー仕立てで学ぶことができる本です。オウンドメディアのコンテンツ作成で悩んでいる方は、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。同じ著者による「Web沈黙のWebマーケティング -Webマーケッター ボーンの逆襲-」という本もあるため、Webマーケティングについて学びたい方は、こちらも合わせてチェックしてみてください。
▼エムディエヌコーポレーション 書籍紹介ページ
https://books.mdn.co.jp/books/3216203005/
・10年つかえるSEOの基本|技術評論社
オウンドメディアを運営する上で、SEO対策がポイントになるという話をしましたが、こちらの本は、SEOの基礎を学ぶことができる本です。トレンドに左右されない、SEOに関する考え方について書かれているため、SEOをこれから学ぶ初心者はもちろん、SEOについての知識があるという人も改めて読んでみてはいかがでしょうか。
▼技術評論社 書籍紹介ページ
https://gihyo.jp/book/2015/978-4-7741-7324-5
オウンドメディアを上手く活用して企業の強みに
オウンドメディアは、効果が得られるまで時間がかかるなど、大変な側面もありますが、上手く活用すれば、企業の財産となり、強みとなってくれる存在です。実際にオウンドメディアを立ち上げ、集客や購買につなげるなど、成功している事例も少なくありません。
本記事を参考に、企業の強みとなるようなオウンドメディア運営を心がけてはいかがでしょうか。







