健康や美容に関する商材を取り扱う場合、薬機法についての理解を深めなければいけません。薬機法を把握せずにコンテンツマーケティングを実施すると、罰金だけではなく、炎上やブランド毀損などの事業存続を脅かすリスクが生じる可能性があります。
本記事では、コンテンツマーケティング運用担当者に向けて、薬機法の基礎知識や注意が必要な施策、違反しないためのポイントなどを解説します。ぜひ記事を参考に、薬機法に違反しないコンテンツマーケティングを推進してください。
コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
コンテンツマーケティング担当者が知っておくべき薬機法とは

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品などの品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止を目的にした法律です。
製造や表示はもちろん、販売や広告の掲載内容などについても細かく定められているため、医薬品や化粧品などを取り扱う企業の担当者は、適切に理解したうえでコンテンツマーケティングを実施しなければいけません。
▼e-GOV法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」TOPページ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
薬機法を違反するリスク
薬機法違反の罰則規則は細かに定められています。SEOやWeb広告などで薬機法に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課されます。法律上の罰則はこれだけですが、副次的な損失も発生します。
例えば、商品回収する事態になった場合、回収費用の発生やこれまでの広告・キャンペーン費用の損失、さらにはオウンドメディア閉鎖のリスクまで生じるのです。薬機法に違反すれば、大きな信頼の低下を招き、会社存続が難しい状態になるでしょう。
コンテンツマーケティングの魅力は、ユーザーに有益な情報を提供することで、顧客との信頼関係を徐々に構築できることです。薬機法の違反により、積み重ねた信頼関係が修復不可能な状態になるまで崩れます。そのような事態を避けるためにも、事前の概要理解が大切です。
コンテンツマーケティングで薬機法の対象となる商材

コンテンツマーケティングで薬機法の対象となる商材一覧は以下の通りです。
・医薬品
・医薬部外品
・医療機器
・化粧品
・その他
以上の商材について詳しく見ていきましょう。
医薬品
薬機法における医薬品とは、下記の条件に該当するものです。
・日本薬局方に収められている物
・人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
・人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
簡単に要約すると、医薬品とは人や動物の病気の診断・治療・予防に使用されるものであり、機械器具ではないものです。例えば、医師の処方箋が必要な薬や解熱剤や胃腸薬などの一般医薬品などが該当します。
医薬部外品
薬機法における医薬部外品とは、下記の条件に該当するものです。
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
1.次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イー吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ローあせも、ただれ等の防止
ハー脱毛の防止、育毛又は除毛
2.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
3.前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
医薬部外品とは、人体に対する作用が緩和であり、安全性が高い製品のことです。具体例は、育毛剤や整腸剤、薬用化粧品などになります。さらに、一部のビタミン剤や歯磨き粉も医薬部外品に該当するため、多くのコンテンツマーケティング担当者やアフィリエイターが該当するジャンルだと考えられます。
医療機器
薬機法における医療機器とは、下記の条件に該当するものです。
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
医療機器の具体例だと、ペースメーカーやレントゲン装置などが挙げられます。しかし、コンタクトレンズや体温計、家庭用マッサージ器、電子血圧計なども医療機器に該当するのです。病院向けの医療機器を取り扱う企業は、自社製品が該当するかどうかの判断が分かりやすいですが、家庭用の医療機器を取り扱う場合はしっかりと確認しておきましょう。
化粧品
薬機法における化粧品とは、下記の条件に該当するものです。
身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
簡単に言えば、人の体を清潔にしたり、きれいに見せたりするものが化粧品に該当します。例えば、シャンプーやせっけん、香水、口紅、ファンデーションなどです。化粧品の定義は分かりやすいため、自身が該当するかどうかの判断はしやすいと思われます。
その他
ペットフードや雑貨などは薬機法では定義されません。しかし、「ニキビが治る」や「ノミ取り効果がある」などの効果を訴求して、広告やブログ記事で宣伝をすると、薬機法に抵触する可能性があるため、注意が必要です。
健康食品やサプリメントにも注意
薬機法が規制するのは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の4つであるため、健康食品やサプリメントは薬機法で定義されません。しかし、健康食品も雑貨と同様に、血行促進や神経痛の緩和などの効果を訴求した場合、薬機法に抵触するのです。
サプリメントの場合、国が特定の栄養成分として定めたものであり、定められた上・下限値の範囲内ならば「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用をもつ栄養素」などの表示が可能となります。
薬機法のNG表現例
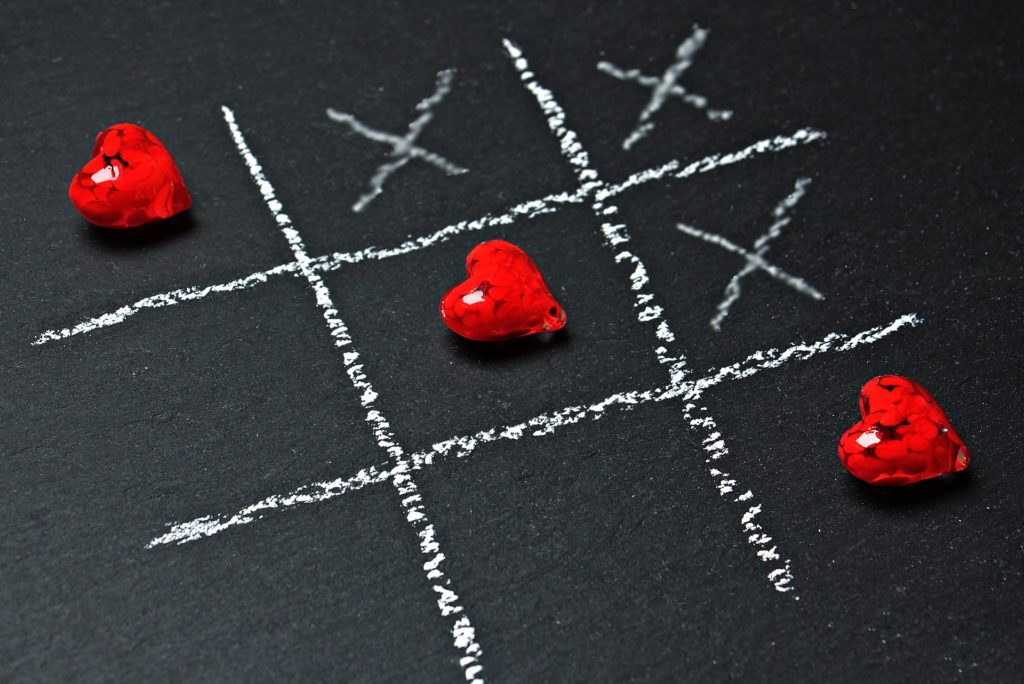
ここからは、化粧品・サプリメント・医薬品におけるNG表現例をご紹介します。具体的なNG例を理解したうえで、コンテンツ制作に取り組んでください。
化粧品
化粧品で訴求できる効果効能については、以下の56個に決められています。
“
1. 頭皮、毛髪を清浄にする。
2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
3. 頭皮、毛髪を健やかに保つ。
4. 毛髪にはり、こしを与える。
5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
7. 毛髪をしなやかにする。
8. クシどおりをよくする。
9. 毛髪のツヤを保つ。
10. 毛髪にツヤを与える。
11. フケ、カユミがとれる。
12. フケ、カユミを抑える。
13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。
14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
15. 髪型を整え、保持する。
16. 毛髪の帯電を防止する。
17. (汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。
18. (清浄により)にきび、あせもを防ぐ(洗顔料)。
19. 肌を整える。
20. 肌のキメを整える。
21. 皮膚を健やかに保つ。
22. 肌荒れを防ぐ。
23. 肌をひきしめる。
24. 皮膚にうるおいを与える。
25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。
26. 皮膚の柔軟性を保つ。
27. 皮膚を保護する。
28. 皮膚の乾燥を防ぐ。
29. 肌を柔らげる。
30. 肌にはりを与える。
31. 肌にツヤを与える。
32. 肌を滑らかにする。
33. ひげを剃りやすくする。
34. ひげ剃り後の肌を整える。
35. あせもを防ぐ(打粉)。
36. 日やけを防ぐ。
37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
38. 芳香を与える。
39. 爪を保護する。
40. 爪を健やかに保つ。
41. 爪にうるおいを与える。
42. 口唇の荒れを防ぐ。
43. 口唇のキメを整える。
44. 口唇にうるおいを与える。
45. 口唇を健やかにする。
46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
48. 口唇を滑らかにする。
49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
52. 口中を浄化する(歯みがき類)。
53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)
54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
56. 乾燥による小ジワを目立たなくする。
”
出典:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」
https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20200615_ADguide.pdf
原則として、この56項目の中から自社商材に適した効果を訴求するようにしましょう。また、37番の「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」や56番の「乾燥による小ジワを目立たなくする」などは、承認された効能効果に一定の条件が付いている「しばり表現」のため注意が必要です。例えば、「小ジワを目立たなくする」とだけ記載した場合、薬機法の違反となります。その他の、主なNG表現は以下の通りです。
・~専用
・高成分配合、デラックス処方などの誇大表現
・安全性は確認済み、赤ちゃんにも安心などの安全性を保障する表現
・臨床データや実験データなどの例示
・使用体験談
・刺激が少ない、低刺激
・強調表現
・No1や世界一などの最大級の表現
健康食品/サプリメント
健康食品やサプリメントは薬機法の定義はありません。しかし、広告で認められない表現が多々あれば、薬機法に抵触する表現もあるため注意が必要です。以下が健康食品/サプリメントの主なNG表現となります。
・肌がきれいになる
・美肌成分○○配合
・肌のくすみがとれる
・紫外線によるシミを防止
・育毛サプリ
・○○の痛みに効果的
・血圧の気になる方に
・疲れた体に
・筋肉へのダメージを考えて作られた
上記NG例に共通しているのは、体の変化を訴求していることです。体の変化を訴求した場合、医薬品とみなされ、薬機法に抵触してしまいます。
医薬部外品
医薬部外品でNGが多くなるのが美白化粧品です。美白やホワイトニング効果は薬機法の承認を受けていないため、下記のルールを守る必要があります。
“
・承認を受けた効果効能を基づく表現(例、日焼けによるシミを防ぐ)
・メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現
・しばり表現の併記
”
出典:薬事法ドットコム「薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲」
https://www.yakujihou.com/rule/bihaku/
逆にNGとなる表現は以下の通りです。
・肌本来の色が変化する表現
・すでにできたシミやそばかすをなくす表現
・承認を受けた効能効果以外のしみ・色素沈着に係る表現
・肌質改善をする表現
・効果を約束する表現
・最大級の表現
これらを踏まえたうえで、医薬部外品のNG表現を見ていきましょう。
・使うほどに肌が白くなる
・できてしまったシミ/そばかすに
・わきの下やひざの黒ずみの美白に
・シミができにくい肌に
・結果を感じる美白
・約束できる
・妊娠線や肉割れの予防に
薬機法に注意するべきコンテンツマーケティング施策

コンテンツマーケティングの中でも、特に以下3つの施策を展開する場合は、薬機法への注意が必要です。
・SEO
・リスティング/ディスプレイ広告
・SNS
以下では、それぞれの施策について解説します。
SEO
SEOとは、主にGoogleの検索結果画面に自社サイトを表示する施策のことです。Googleはユーザーの検索語句と関連性のあるコンテンツを抽出した後、信頼性や権威性などの複数シグナルを考慮し、最も役立ちそうなコンテンツを表示します。
特に、サイトや情報の信頼性は重要なランキング要因となっているため、薬機法の遵守が重要です。また、薬機法に違反した場合、訪問ユーザーとの信頼関係が壊れてしまうため、コンバージョン率の大幅な低下を招きかねません。正しい情報を発信するようにしましょう。
リスティング/ディスプレイ広告
リスティング/ディスプレイ広告とは、GoogleやYahoo!の検索結果、提携パートナーサイトやアプリの広告枠に配信するWeb広告のことです。リスティング/ディスプレイ広告の運用においては、広告表現に注意しましょう。不適切な表現の場合、広告の出稿が認められません。
Yahoo! JAPANによる「広告サービス品質に関する透明性レポート」(※1)では、2020年度上半期の広告非承認は約1億1千万件であり、非承認理由で多かったのは「最上級表示・No1表示」「薬用化粧品(医薬部外品)」「化粧品」の基準に抵触することでした。
リスティング広告/ディスプレイ広告は、大きな効果が認められる一方、適切に作成しなければ広告の出稿は許可されません。薬機法を押さえたうえで、広告クリエイティブを作成しましょう。
※1 出典:Yahoo! JAPAN「広告サービス品質に関する透明性レポート」
https://s.yimg.jp/images/marketing/article/blog/2020/1215/yj_ad_quality_report_202012.pdf
SNS
SNSは拡散性が高いため、企業にとって重要な認知・集客チャネルとなっています。しかし、企業の炎上事例が多々あるように、拡散性があるからこそ適切な情報発信をしなければいけません。万が一、薬機法に違反した情報発信をすると、あっという間に炎上し、ブランドの信用が大幅に低下してしまいます。
コンテンツマーケティングで薬機法に違反しないポイント

コンテンツマーケティングで薬機法に違反しないポイントは以下の通りです。
・誇大表現を使用しない
・言い換え表現を活用する
・専門家に監修してもらう
・マニュアル/ガイドラインを作成する
それぞれのポイントについて見ていきましょう。
誇大表現を使用しない
先にご紹介したYahoo! JAPANのレポートでも、最上級表示は広告非承認の理由で最も多く、全体の20%近くを占めます。円滑に広告を運用するためにも、客観的な根拠や調査結果がない場合は、最上級表示や誇大表現の使用は避けましょう。
言い換え表現を活用する
薬機法の違反を避けるためには、言い換え表現を上手く活用するのが有効です。例えば、「目元のしわ向けの化粧水」ではなく「気になる目元の化粧水」、「たるんだ肌へ」ではなく「ハリのない肌へ」など(言い換えの一例であり、必ずしもすべてのケースで正しい表現ではありません)。言い換え表現をする際は、薬機法が何を認めていて、何を許可していないのかを理解することが重要です。
専門家に監修してもらう
薬機法に抵触する商材を扱う場合は、専門家に監修してもらうのがおすすめです。ブログ記事やコンテンツなどを専門家にチェックしてもらえば、薬機法の違反を防止できるだけではなく、効果的な言い換え表現の提案もしてもらえます。
マニュアル/ガイドラインを作成する
薬機法を守るためには、自社でマニュアルやガイドラインを作成するのも有効です。使用しない表現や単語、チェックポイントなどをマニュアルに落とし込むことで、多くのメンバーが関わっていたとしても、薬機法を遵守したコンテンツ制作が可能となります。
薬機法に気を付けてコンテンツマーケティングに取り組もう
コンテンツマーケティングの強みは、顧客との信頼関係を構築できることです。しかし、薬機法に違反すれば、信頼関係は壊れ、事業存続が危ぶまれるほどの大きな損失が生じます。
「薬機法を知らなかった」ではすまされないので、薬機法に関連する商材を扱う場合は、気を付けてコンテンツマーケティングに取り組むようにしましょう。






