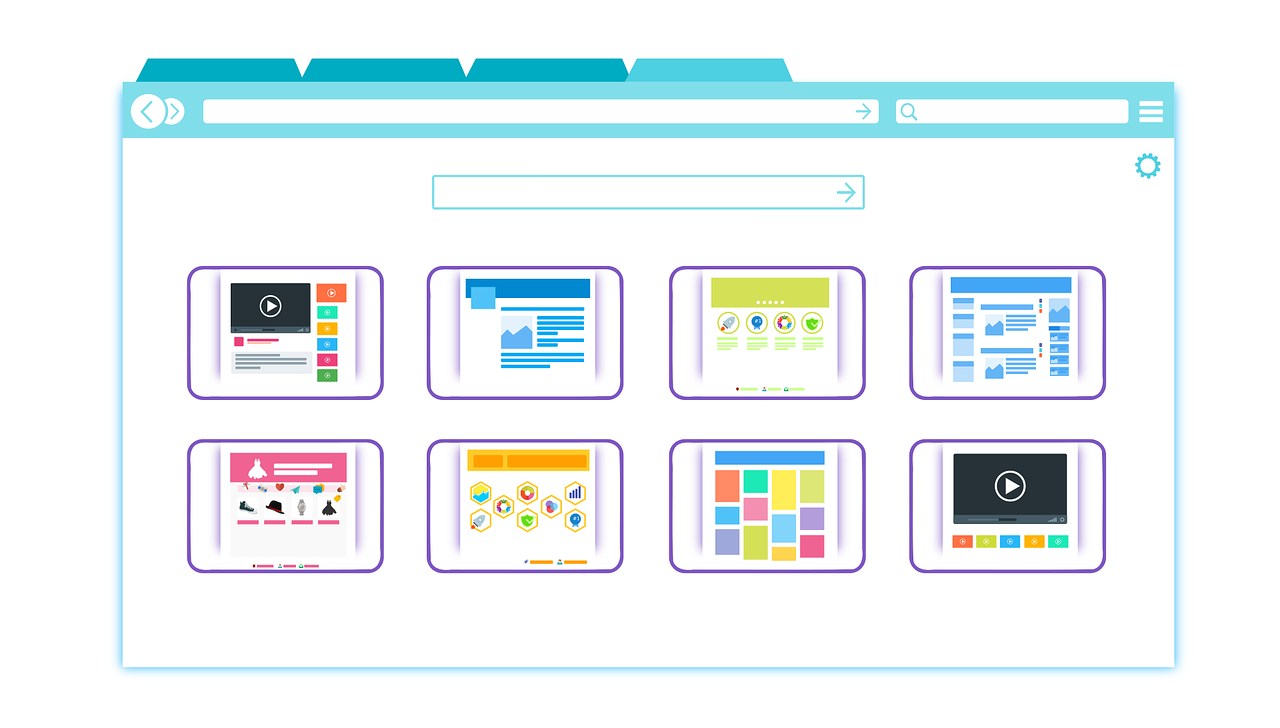コンテンツマーケティングの施策は多種多様ですが、Web上の活動が主流です。これからコンテンツマーケティングを実践するのであれば、自社のWebサイト制作は必須と言えます。
この記事では、コンテンツマーケティングにおけるWebサイトの種類を解説します。Webサイトの必要性や、悩み別の制作すべきサイトも紹介しますのでぜひご覧ください。
コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
コンテンツマーケティングとWebマーケティングの違いから理解しよう

コンテンツマーケティングと近い施策に「Webマーケティング」があります。コンテンツマーケティングにおけるWebサイトとWebマーケティングを混同すると、実施すべき戦略を間違えるかもしれません。まずは、両者の違いを理解することから始めましょう。
定義の範囲
そもそもコンテンツマーケティングは、コンテンツの制作・発信によりファンを作り購買を目指す手法です。オンライン上の活動がメインですが、オフライン上の施策も存在します。
対するWebマーケティングは、Web上で行うマーケティング施策全般の総称です。Web広告やSNS運営、メール配信といったWeb上の活動は、全てWebマーケティングに該当します。つまり、Webマーケティングの中に、コンテンツマーケティングで制作したWebコンテンツが含まれるイメージです。
制作するコンテンツの種類
Webマーケティングで扱うコンテンツは、インターネットで発信できるコンテンツに特化しています。テキスト主体の記事、動画、ホワイトペーパー、メルマガといった種類です。
コンテンツマーケティングは上記に加え、自社開催のセミナーや企業出版の書籍、パンフレットといったオフラインコンテンツも含まれます。Webマーケティングと混同してしまうと、「インターネットで閲覧できるコンテンツしか作らない」と勘違いするかもしれません。必要に応じてオフラインの制作物とWebサイトを連携し、幅広いユーザーに訴求しましょう。
コンテンツマーケティングにWebサイトが必要な理由

コンテンツマーケティングは、オンライン施策を中心に進めるのが一般的です。中でも、コンテンツ発信の中心地となるのが自社のWebサイトです。理由として、次の6つがあります。
1.新規顧客を集めやすい
2.会社の信頼性が上がる
3.採用ブランディングもできる
4.効果測定しやすい
5.機会損失を防げる
6.不要な問い合わせ対応を減らせる
それぞれの理由ごとに、Webサイトの必要性を説明します。
1.新規顧客を集めやすい
1つ目の理由が、新規顧客の集めやすさです。自社のWebサイトを中心としてオンライン上でコンテンツを発信するため、オフラインコンテンツのみより多くの人と接点を持てます。たとえば、自社の特定サービスに特化した「サービスサイト」を作り、リスティング広告と併用すれば、自社サービスのジャンルを比較検討しているユーザーを効率良く獲得できます。
他にも、記事型コンテンツを公開する「オウンドメディア」を運営すると、自然検索やSNSからの流入数が増えるでしょう。潜在層を獲得できるので、将来的な顧客への育成も可能です。新規顧客との接点を増やしたいのであれば、Webサイトの制作は必須と言えます。
2.会社の信頼性が上がる
自社のWebサイトがあるだけで、企業の信頼性が上がります。インターネットが普及した昨今、サービスや商品の購買を検討している会社の名前で検索する人は決して少なくありません。ホームページがない企業に不審なイメージを持つ人もいるので、自社のWebサイトは必要不可欠です。
企業の公式サイトとなる「コーポレートサイト」があれば、ユーザーの信用を獲得できます。チラシやCMとは異なり、Webサイトは閉鎖しない限りオンライン上に存在し続けます。長期にわたって認知度と信頼性を得られるため、Webサイトの必要性は高いです。
3.採用ブランディングもできる
コンテンツマーケティングの目的に、採用ブランディングを含む企業もあるでしょう。近年は、求人サイトへの求人広告の掲載だけでなく、自社メディアによる採用ブランディングも重要視されています。多くの求職者は応募前に求人企業の情報収集を行うため、簡単に確認できる自社サイトが必要です。
また、求人募集などの人事採用に特化した「リクルートサイト」を作るケースもあります。基本の求人情報に加えて詳しい働き方や従業員の声を掲載し、自社の魅力を効果的にアピールできます。
4.効果測定しやすい
Webサイトは、効果測定しやすい媒体です。アクセス解析ツールを使い、ユーザーの属性やサイト上の行動などのデータを取得できます。データにもとづいた客観的な分析が可能になり、マーケティング施策の成果を適切に検証できるでしょう。
設定したKPIに届かないほど効果が低いとわかれば早い段階で施策を修正し、効果が高い施策にはさらに予算をかけるといった素早い判断が可能です。Googleアナリティクスなどの無料ツールもあるので、規模が小さなコンテンツマーケティングでも充分に効果を測定できます。
5.機会損失を防げる
自社Webサイトは、機会損失の防止にも貢献します。自社Webサイトがない場合、自社の商品・サービスを検討しているユーザーがいても、インターネット上から申し込めず諦めてしまうかもしれません。競合他社に流れる可能性が高いため、インターネット上の申し込み経路は大切です。
他にも、「ホームページがない怪しい企業なのでは」「企業の公式情報がないと不安」といった心理的な懸念を招く恐れがあります。そもそも自社サイトがなければ、自社業界に関するキーワードの検索結果にも表示されず、オンライン上の顧客獲得競争に参加すらできません。
6.不要な問い合わせ対応を減らせる
自社のWebサイトがあると、不要な問い合わせの削減が可能です。顧客からの問い合わせはビジネスチャンスにつながるものの、中には自社のサービスサイトがあれば問い合わせ対応せずに済む質問もあります。FAQを用意すると、単純な質問に対応する手間を減らせるでしょう。
さらに、質問内容によっては、口頭だけでは説明しづらいサービスもあります。問い合わせ時に自社サイトを見てもらいながら説明すれば、スムーズに理解してもらえるでしょう。不要な問い合わせが減ると社員の業務効率も上がるため、サービスサイトの果たす役割は大きいです。
BtoBサイトとBtoCサイトの違い

コンテンツマーケティングを行う上でWebサイトは必須ですが、BtoB企業とBtoC企業では作るべきサイトの方向性は異なります。ここでは、以下4項目に分けてBtoBサイトとBtoCサイトの違いを確認しましょう。
1.コンテンツの違い
2.サイトデザインの違い
3.コンバージョンや目的の違い
4.顧客対応数の違い
項目ごとに、BtoBサイトとBtoCサイトの特徴を解説します。
1.コンテンツの違い
BtoBサイトのコンテンツは、企業担当者向けの内容です。担当者一人の判断でサービス利用を決めることはほとんどないため、社内の検討段階に引き上げてもらえる詳細な資料が必要でしょう。さらに、社内検討時に決済者の承諾を得られる合理的なコンテンツも必要です。導入事例やホワイトペーパーといったコンテンツも充実させましょう。
一方のBtoCサイトは、消費者個人の興味を引く記事や動画などのコンテンツを中心に提供します。BtoBに比べてリードタイムが短い上、購買を考える基準も「流行っているから」と合理的ではない場合もあります。潜在層を育てる内容だけでなく、即座に購買行動を促せるコンテンツも大事です。
2.サイトデザインの違い
BtoBサイトは、落ち着いたデザインが一般的です。インパクトのあるデザインよりも、自社サービスの説明や料金などの情報を伝えられるわかりやすさや、信頼性の高いイメージが重要視されます。
対するBtoCサイトは、目を引くおしゃれなデザインやアニメーション、派手な色使いなど多種多様です。購買意欲をかき立てるキャッチコピーや画像を用い、自社商品の魅力を短時間で伝えるデザインを採用します。
3.コンバージョンや目的の違い
BtoBサイトのコンバージョンは、問い合わせや資料請求による「リード獲得」を目的とするパターンが多いです。リード獲得の前段階として、記事を使った「集客」が目的になる場合もあります。BtoB事業は単価が高くリードタイムが長いため、サイト自体の目的が直接的に「購買」となるケースは少ないでしょう。リード獲得後は、リードナーチャリングと営業活動を経て商談へと繋げる仕組みです。
BtoCサイトは自然検索で集客し、ニーズを育てて「購買」へ誘導するケースが一般的です。検索ワードによっては、最初に到達したページから直接的に購買を狙う場合もあるでしょう。その他、コンテンツを通して自社に愛着を持ってもらう「ファン化」も目的となります。
4.顧客対応数の違い
BtoBサイトの顧客は企業であるためターゲットの母数が少なく、比例して問い合わせ数も多くありません。サービス成約後のアフターフォローなどの顧客対応も同様です。
一方のBtoCサイトは一般消費者が相手なので、サポート対応がBtoBサイトより多くなります。中でも、ECサイトは専用のコールセンターを設ける場合もあるでしょう。商品への問い合わせだけでなく、返品や交換の対応も必要になります。カスタマーハラスメントが起きる恐れもあるため、従業員を守るための対応マニュアル作成などの対策が重要です。
コンテンツマーケティングにおけるWebサイトの種類
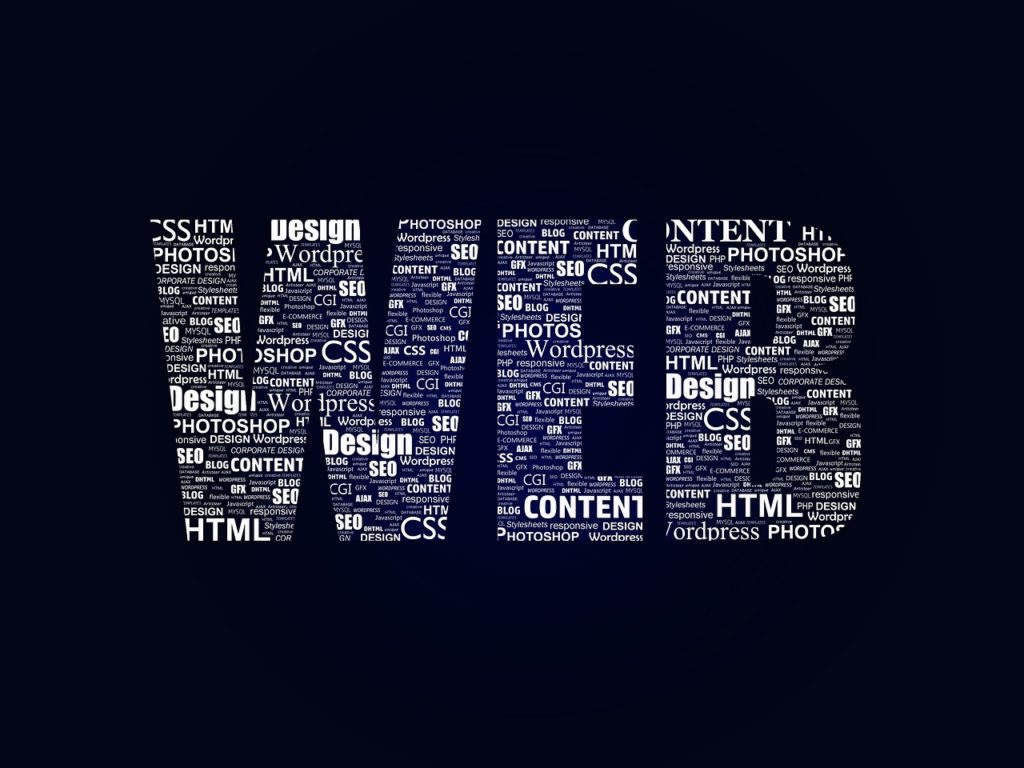
コンテンツマーケティングで制作するWebサイトは、多くの種類があります。主な種類は、次の7つです。
1.オウンドメディア(記事型メディア)
2.コーポレートサイト(企業ホームページ)
3.リクルートサイト(採用サイト)
4.ブランドサイト
5.サービスサイト
6.ランディングページ
7.ECサイト
各サイトの特徴や制作するコンテンツを紹介します。
1.オウンドメディア(記事型メディア)
オウンドメディアは、ブログ形式で記事を制作するサイトです。本来は「自社が保有するWebメディア」を指しますが、マーケティングでは記事主体の自社サイトを意味する場面が増えています。集客、ブランディング、リード獲得、認知度向上といったさまざまな目的に適しているため、多くの企業がオウンドメディアを構築しています。
制作するコンテンツ
オウンドメディアに掲載するコンテンツは、記事が主体になります。よくある記事の内容は、以下の通りです。
・ユーザーの悩みを解決する記事
・専門知識の解説・ノウハウ
・おすすめ製品やサービスの比較
・自社製品・サービスの紹介
・特集やコラム
・インタビュー
自社のターゲットが求める多様な記事を制作し、潜在層から既存顧客まで幅広く訴求できるメディアを作ります。
サイト運営のポイント
オウンドメディアを運営する上で、継続的な記事更新は欠かせません。新しい情報がないサイトには読者が定着せず、サイトの成功が難しくなります。読者の定着策として、内部リンクによる回遊率の向上も基本の施策です。また、記事コンテンツはSEO対策が必須ですので、基本のSEO対策について学び、検索上位を獲得できる記事を制作しましょう。
2.コーポレートサイト(企業ホームページ)
一般的に「企業ホームページ」と言われるサイトは、「コーポレートサイト」とも言います。「株式会社◯◯」と会社名で指名検索したユーザーが最初にたどり着く、企業の看板と言えるサイトです。自社に関する情報を広く掲載し、多くの人に自社の存在を認知してもらうために制作します。
制作するコンテンツ
コーポレートサイトは、自社の情報を伝えられる下記のコンテンツを作成します。
・会社概要
・事業内容
・採用情報
・IR情報
・ニュースリリース
・FAQ
これらの正しい情報を掲載し、自社に関心のある人に向けて発信します。
サイト運営のポイント
コーポレートサイトは企業の看板となるため、事業内容やターゲットに合うサイトデザインが求められます。サイトの訪問者には求職者や投資家も含まれ、顧客層だけではありません。「どこに何があるのか」が一目見てわかるような、わかりやすいUIデザインが重要です。更新情報が古いと会社の信頼性を損なう恐れもあるので、最新状態に保てる運営体制が必要になります。
3.リクルートサイト(採用サイト)
リクルートサイト(採用サイト)は、自社の採用活動に関する情報のみ扱うWebサイトです。コーポレートサイトの採用ページよりも、求職者に向けてさらに詳しく特化したコンテンツを届けます。採用活動の経費削減や採用後のミスマッチ防止を目的とし、恒常的にサイトを設置して自社が求める人材をアピールします。
制作するコンテンツ
リクルートサイトで制作する内容は、次の項目をご覧ください。
・採用情報(募集要項や選考フローなど)
・詳細な就労条件、福利厚生
・業務内容、一日のスケジュール、オフィス環境
・社員へのインタビュー
・企業理念や求める人物像
上記のコンテンツを記事や動画などの媒体で発信します。
サイト運営のポイント
求職者は慎重に就職先を見極めるために、リクルートサイトを閲覧します。求職者が知りたい情報をできる限り詳細に伝えると同時に、自社の魅力をアピールできるコンテンツ制作が不可欠です。また、顧客向けのサイトではないからといって、応募フォームや導線の設計を甘くしてはいけません。求職者が自社を知り応募に至るまでの心理や接点、行動を考え、適切な導線を構築しましょう。
4.ブランドサイト
ブランドサイトは、自社ブランドのイメージ訴求に特化したサイトです。ブランド内の商品やサービスを専門的に扱い、ブランドの価値を伝えます。ブランドサイトの目的は、ブランドの知名度向上や好感度およびファンの獲得です。ブランディングにより自社や商品・サービスに付加価値を与え、競合他社に負けない販売力を高めます。
制作するコンテンツ
ブランドサイトを運用する際は、主に下記のコンテンツを制作します。
・ブランドのコンセプトが伝わる動画や記事
・ブランドのキャッチコピー
・Webアニメーション
・ブランドに関するコラムや特集
ブランドサイトは、ビジュアルを駆使したコンテンツを多く制作します。ブランドイメージを伝えるためには、文章以外の動画や画像による訴求も必須となるでしょう。
サイト運営のポイント
ブランドサイトは、商品や料金といった機能性ではなく、ユーザーの感情面に訴えかける付加価値のアピールが大切です。「この製品でナチュラルな暮らしができる」などのイメージを持ってもらう必要があります。こうしたブランドイメージが付加価値となり、多少の価格差では他社に流れない強固なファンを獲得できるわけです。
5.サービスサイト
サービスサイトは、自社の特定サービスを詳しく紹介するサイトです。特定サービス専用のサイトを作ることで、ターゲットが求める情報のみを扱えます。サービスサイトのターゲットは、ニーズが明確な顕在層だけでなく潜在層も対象です。資料請求や問い合わせフォームを設置し、リード獲得や購買を目的としてサイトを開設します。
制作するコンテンツ
サービスサイトは、サービスの特徴を網羅できるコンテンツが必要です。
・サービスの特徴
・機能、料金プラン
・導入事例、お客様の声
・ホワイトペーパー、製品資料
・よくある質問、FAQ
・ダウンロードフォーム
・お問い合わせ、相談フォーム
サービスの情報をあますことなく伝え、コンバージョンに繋がる各種フォームも設置しましょう。
サイト運営のポイント
サービスサイトは基本のSEO対策のほか、リスティング広告による流入経路の確保も効果的です。リード獲得に繋がるホワイトペーパーは、検討段階ごとに適した資料を用意すると良いでしょう。潜在層には課題解決型、顕在層には導入事例型のホワイトペーパーを作成します。その他、各種フォームの入力で離脱を防ぐためのCTA最適化も必要です。
6. ランディングページ
ランディングページとは、商品やサービスの購買・申し込みに特化したWebサイトです。一般的には縦長のレイアウトで、商品やサービスの紹介から入力フォームまでの流れを1ページにまとめています。コンバージョン獲得に特化しているため、途中離脱に繋がる他ページへのリンクはほとんど存在しません。
制作するコンテンツ
ランディングページは、以下のようにコンバージョンに直結するコンテンツを制作します。
・商品やサービスの詳細
・魅力を強く訴求するテキスト
・お客様の声、体験談
・商品やサービスに関する疑問と回答
・よくある質問、FAQ
・購入方法
・ページ内からそのまま購買・申し込みできる入力フォーム
ランディングページは1枚のWebページで構成するので、ランディングページ自体がコンテンツでもあります。
サイト運営のポイント
ランディングページは、細かなペルソナ設定が重要になります。ペルソナの年齢や性別、抱えている悩みを仮定し、ペルソナが購買に至るまでのストーリーをランディングページに落とし込んでみてください。ランディングページの改善はヒートマップツールを使うと、ユーザーの関心が高い部分や離脱箇所が明らかになります。関心が高い場所にコンバージョンを設け、離脱箇所の設計を修正しましょう。
7.ECサイト
ECサイトは、自社で運営する通販サイトです。単なる通販サイトだけではなく、通販ページの他に特集記事などのコンテンツも充実させ、メディア化したECサイトも含みます。コンテンツで自社ECサイトへの愛着を持ってもらい、リピート率を上げる狙いです。同業他社への流入も阻止し、自社の利益を向上させられます。
制作するコンテンツ
ECサイトの運営には、次のコンテンツが必要です。
・商品情報
・カート
・検索フォーム
・商品に関する特集やコラム
・会員登録者ページ
商品の販売に特化しているので、制作コンテンツも商品に関する内容が中心になります。
サイト運営のポイント
ECサイトは、使いやすい機能が大切です。商品カテゴリーが乱雑で検索性が低いと、ユーザーはなかなか欲しい商品を見つけられません。他のECサイトへと流れてしまうので、わかりやすいサイト設計を心がけましょう。また、ECサイトはSNSと連携しやすいメディアです。たとえばアパレル系ECサイトであれば、自社SNSにコーディネートを投稿し、ECサイトへ誘導するといった導線を作れます。
コンテンツマーケティングにおけるWebサイトの一覧表

ここまで紹介した7つのウェブサイトについて、特徴を以下の一覧表にまとめました。
| サイトの種類 | 概要 | 制作コンテンツ | 運営のポイント |
| オウンドメディア
(記事型メディア) |
読者に有益な記事を発信しファン獲得や購買を目指す | 専門知識の解説、インタビュー、悩み解決などの記事 | SEO対策と継続的な記事制作が必須 |
| 企業ホームページ
(コーポレートサイト) |
企業の公式サイト。自社の認知度や信頼性の向上に必要 | 会社概要や事業内容、IR情報など、企業情報を広く掲載 | 顧客層、求職者、投資家といった誰が見てもわかりやすいサイト設計 |
| リクルートサイト
(採用サイト) |
自社の採用活動の専門サイト。採用精度の向上、コスト削減が目的 | 詳細な採用情報や働き方に関するコンテンツ | 求職者が求める情報を細かく掲載し、自社の魅力もアピール |
| ブランドサイト | ブランドイメージの訴求に特化し、ファンを増やす | ブランドコンセプトが伝わる動画など、ビジュアル重視のコンテンツ | 機能性よりも、感情面に訴求する付加価値のアピールが重要 |
| サービスサイト | 特定サービスの紹介に特化したサイト。リード獲得や購買が目的 | サービスの機能や料金、導入事例、ホワイトペーパーなど、サービスの詳細情報 | サービスの潜在層と顕在層を意識したコンテンツを用意 |
| ランディングページ | 商品の購買に特化した縦長のWebページ | 商品の詳細、お客様の声、購入フォームなど、購買に直結するコンテンツ | ターゲットを絞り込み、細かくペルソナを設定 |
| ECサイト | 自社で運営するECサイト。コラムや特集を掲載しメディア化 | 商品情報やカート、コラム・特集。商品に関する情報が中心 | 商品を探しやすいサイト設計が求められる |
コンテンツマーケティングを始める際は、制作するWebサイトの選定にぜひご活用ください。
【悩み別】コンテンツマーケティングで作るべきWebサイト
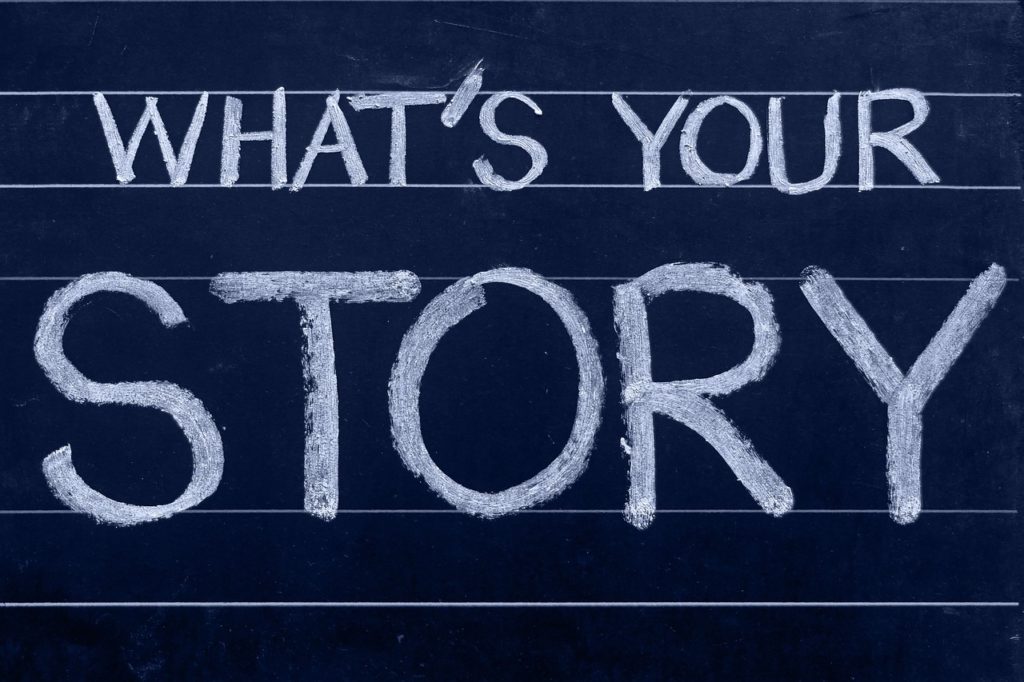
コンテンツマーケティングにおけるWebサイトの種類は多数あり、企業の目的によって作るべきWebサイトは違います。ここでは、どのサイトを選べばいいかわからない企業に向け、よくある悩みと解決策になるWebサイトを6パターン紹介します。
1.採用の精度を高めたい
2.価格競争による利益低下を食い止めたい
3.高額商材を売りたい
4.大手通販サイトで自社商品が埋もれている
5.自社イメージを損なわずにセールスを強化したい
6.BtoBビジネスの新規顧客がほしい
それぞれ解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.採用の精度を高めたい
採用後の求職者と自社のミスマッチを防ぎたいなら、リクルートサイトを作りましょう。企業の顔となるコーポレートサイトも必須です。リクルートサイトは、コーポレートサイトよりも採用に特化した内容を掲載できます。自社の理念や細かい業務内容などの情報を発信することで、求職者は「自分に合う企業であるか」を理解した上で応募してくれます。
入社後すぐの退社を防げる上に、採用コストの削減にもつながります。求める人材を詳しくアピールすれば、自社とマッチしない求職者の応募はおのずと減るでしょう。自社に合う人材の中から選考できるので、採用活動の期間短縮・人件費削減に繋がるわけです。
2.価格競争による利益低下を食い止めたい
価格競争が起きている業種であれば、ブランドサイトまたはオウンドメディアの構築がおすすめです。そもそも価格競争が起きるのは、競合間の商品に大きな性能差がなくなった業界です。性能による違いがなくなると、消費者は価格の安さを重視する傾向があるため価格競争が起きます。
こうした状況から抜け出すための施策の1つが、自社ブランドのファン獲得です。ファンは「このブランドの雰囲気が好き」といった理由で購入してくれるため、安価な他社製品に流れません。ブランドサイトやオウンドメディアのコンテンツでユーザーを集客し、自社を支えてくれるファンへと育成しましょう。
3.高額商材を売りたい
高額な製品やサービスを販売する会社におすすめなのが、オウンドメディアです。高額商材は値段が高い分ユーザーの検討段階が長く、自社に対する高い信用を得る必要があります。オウンドメディアでユーザーに有益な情報を発信し続け、信頼関係を構築しましょう。
また、高額商材は単価が高いため、オウンドメディア運営にかけた費用を回収しやすいです。質の高い記事コンテンツを継続的に制作するには、人員および費用のリソースが欠かせません。しかし、一度の成約で生まれる売上が高いため利益率も大きく、オウンドメディア運営の損益分岐点を低く設定できます。高額商材を扱う会社はオウンドメディア構築のメリットが大きいため、ぜひ取り組んでみてください。
4.大手通販サイトで自社商品が埋もれている
大手通販サイトなどのモール型ECサイトで自社商品が埋もれている場合、ECサイトの制作が向いています。ECサイトをメディア化し、オウンドメディアと同じように記事や動画を発信して固定ファンの獲得を目指しましょう。SNSとも相性が良く、商品情報の投稿からECサイトへの流入経路を確保できます。
ただし、個人情報を多く扱うため、情報流出を防ぐ体制が必須です。システム面のセキュリティ対策だけでなく、ECサイト運営スタッフへのセキュリティ教育も大切になります。セキュリティ対策にかかる費用は決して低くないので、企業規模によってはパッケージによるECサイト構築だと運営維持が難しいケースもあります。コストを重視する場合、比較的安価なASPカートを検討しましょう。
5.自社イメージを損なわずにセールスを強化したい
「セールスを強化したいけど、ブランドイメージに悪影響が出るかも」とお悩みであれば、ランディングページを作りましょう。Webサイト全体でセールスを強化すると押し売り感が強くなり、ユーザーに「思っていたイメージと違う」と反感を持たれてブランドイメージが崩れる恐れがあります。
ランディングページは、リスティング広告などで流入した特定のターゲットにしか見られません。ランディングページでセールスを強化しても、ブランド全体のイメージは損なわれないわけです。オープンな場所であるブランドサイトでイメージ訴求を徹底しつつ、ランディングページも併用してブランディングと売上確保の両立を図りましょう。
6.BtoBビジネスの新規顧客がほしい
BtoBビジネスの顧客層を広げたい場合、サービスサイトを制作しましょう。多くの企業担当者が自社に導入するサービスを選定する際、Webサイトを情報源の1つとします。コーポレートサイトのみではサービスに関する情報が不足するほか、「IR情報」「採用情報」といった顧客に不要な情報が多くなります。コーポレートサイトから分離すれば、顧客への訴求に特化したサイト設計が可能です。
とはいえ、新規事業をのぞき、BtoBビジネスでサービスサイトを作っていない企業は少ないかもしれません。現時点で制作していない、あるいは制作予定がないなら、サービスサイト制作を検討してみてください。
コンテンツマーケティングにおけるWebサイトの制作方法
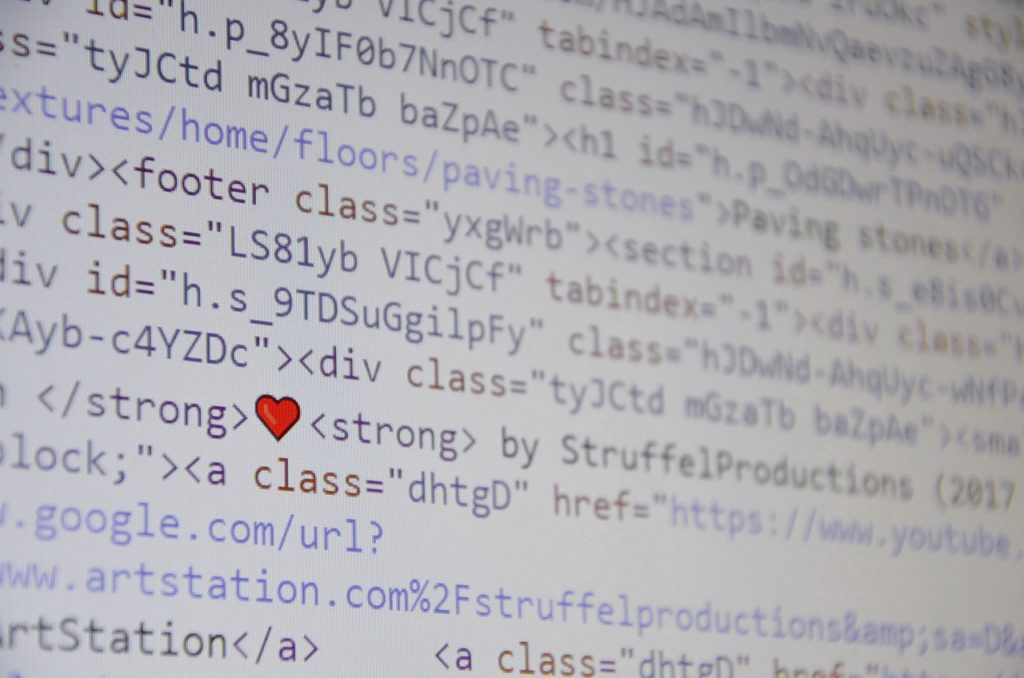
コンテンツマーケティングで運営するWebサイトの種類を決めたら、実際にWebサイトを制作します。Webサイトの構築手段は、基本的に「CMSを利用」か「ゼロベースで開発」の2択になるでしょう。どちらを選ぶ場合でも、以下3つのいずれかの方法でWebサイトを制作します。
1.自社制作する
2.フリーランスに依頼する
3.Web制作会社に外注する
それぞれの特徴を紹介します。
1.自社制作する
コストを抑えたい場合におすすめなのが、WordPressなどのCMSを使った自社制作です。高度な開発スキルがなくても着手できるため、簡単にWebサイトを制作できます。CMSの中でもWordPressはユーザー数が多く、無料テンプレートが豊富です。WordPressの利用自体も無料なので、スモールスタートしたい企業に向いています。
予算に余裕があるなら、開発者を採用して自社制作するケースもあります。この場合はCMSの利用に加え、HTMLやCSS、JavaScripによるゼロベースの開発も可能です。人件費や開発費がかかりますが、Webサイトの制作・運営・メンテナンスを完全内製化できます。開発チームと自社内で意思疎通できるため、サイト制作後の修正・改善作業がスムーズになるでしょう。
2.フリーランスに依頼する
フリーランスのエンジニアに依頼するのも、選択肢の1つです。フリーランスはヒアリングから開発まで1人で行っているため、後述のWeb制作会社よりもコミュニケーションが取りやすくなります。見積もりや要件定義の判断が早く、料金も抑えやすいです。「自社開発は難しいけど、予算もあまり割けない」といった事情がある企業に適した方法と言えます。
ただし、フリーランスの技術力やコミュニケーション能力は個人差が大きいです。たとえ優れたスキルを持っていても、1人で稼働しているため案件を引き継げる人員がいません。ゆえに、怪我などの事情により、納期の延期や納品されないリスクがあります。優秀なフリーランスを見極めるのはもちろんのこと、リスクを理解した上での依頼が大切です。
3.Web制作会社に外注する
もっとも高額になるのが、Web制作会社への外注です。費用が高くなる分、無料・有料CMSによる構築、ゼロベース開発に幅広く対応できます。柔軟なデザインを実装できるので、独自性の高いWebサイトの制作が可能です。高品質なWebサイトを望み、マーケティング予算にも余裕がある企業におすすめの方法です。
Web制作会社に委託する際は、自社がWebサイトに求める機能やデザインをヒアリングしてもらい要件定義を進めます。要件定義にもとづいてWeb制作を行うので、マーケティング戦略の方向性と異なるWebサイトにならないよう明確に要望を伝えましょう。
Webサイトは自作と外注のどちらが良い?
Webサイトの制作方法は、事業の規模や将来的な拡張性も考えて選びましょう。たとえば、無料CMSを使った自社制作は、「コーポレートサイトのみほしい」といった小規模なコンテンツマーケティング向けです。将来的に拡張する予定があっても、小さなオウンドメディアから始めたい場合にも当てはまります。
一方、コンテンツマーケティングに本格的に取り組むなら、Web制作会社への依頼がおすすめです。中でも、高度なデザインやセキュリティが必要なサイトは、非IT企業による自社制作は難しいでしょう。
Webサイトを制作する際のポイント

コンテンツマーケティングでWebサイトを制作する際は、下記5つのポイントに注意しましょう。
1.Webサイトの目標を決める
2.コンテンツとデザインはターゲットを意識する
3.外注先は複数の会社を比較する
4.過剰な装飾を避ける
5.SEO対策を欠かさない
ポイントごとに、なぜ気をつけるべきか説明します。
1.Webサイトの目標を決める
必ず決めるべきなのが、Webサイトの目標です。Webサイトの種類に加えて「誰に何をしてもらうためのサイトなのか」を決め、「サイト経由の売上◯円」といった具体的な目標数値を定めましょう。さらに、中間目標としてKPIも必要です。月間PV数やCVR(コンバージョン率)などの数値を細かく設定し、Webサイトの目標達成に近づけているのか検証します。
目標やKPIがあれば、制作すべきコンテンツの種類やサイト設計で迷走するリスクを抑えられるでしょう。目標数値を達成できなくても、アクセス解析ツールの数値から改善の方向性を立てやすくなります。Webサイトの目標は、サイト設計から運用まで施策立案の方針になるため、必ず明確化しましょう。
2.コンテンツとデザインはターゲットを意識する
Webサイトのデザインは、コンテンツマーケティングのターゲットを意識して作りましょう。コンテンツマーケティングのターゲットとは、すなわち自社の顧客層です。自社の顧客層に共感されない・見づらいデザインは避け、どのようなデザインが自社イメージに合うか入念に調査しましょう。
たとえば、ユーザーアンケートなどの定性調査・定量調査で、デザイン案の感触を確かめる方法があります。サイトに掲載するコンテンツも同様に、ターゲット目線の情報発信が重要です。自社の顧客層に無関係な内容を制作しても意味がありません。ペルソナを設定し、顧客が知りたいと思う情報を届けましょう。
3.外注先は複数の会社を比較する
Web制作を外部に委託するのであれば、複数の会社から比較検討しましょう。会社によって強みは違うので、過去の実績、ヒアリングの丁寧さや提案力、プロジェクトの管理体制、費用、運用後のフォローなどの要素をチェックします。たとえば、同業他社の事例がある会社は、業界に関する知識をある程度持っているためスムーズなやり取りが期待できます。
なお、外部に発注をかける際は、見積もりの依頼時に提出する「RFP(提案依頼書)」を可能であれば作成しましょう。Webサイト制作の目的や求める機能などの情報をまとめた資料ですので、自社の要望を正確に反映した提案をしてもらえます。
4.過剰な装飾を避ける
Webサイトの過度な装飾や演出は、サイトが見づらくなる一因になります。アニメーションは視線誘導に効果的ですが、必要以上に使いすぎないよう注意が必要です。過剰なアニメーションはユーザーの操作を邪魔し、ページの読み込み速度を低下させます。ページから途中離脱してしまうため、アニメーションの実装は慎重に行いましょう。
文字のフォントや色も、やみくもに装飾するのはおすすめできません。あまりにも派手な色合いだと視認性が落ちるばかりか、「ダサい」「古い」とブランドイメージを崩す恐れがあります。記事が主体のオウンドメディアの場合、文字が読みづらいと読者は定着してくれません。サイトのトーン&マナーを決め、ルールに沿った文字装飾を行いましょう。
5.SEO対策を欠かさない
SEO対策のメインは記事の文章となりがちですが、Webサイトの構造自体のSEO対策も重要です。一例として、以下の施策があります。
・ナビゲーションを設置する
・パンくずリストを表示する
・XMLサイトマップを作成する
・ページの内容を示すシンプルなURLにする
上記とは反対に、やってはいけないSEO対策も存在します。「自動生成したテキストを使用する」「SEOキーワードを隠しテキストで羅列する」「有料リンクを購入して被リンクを増やす」といった手法です。SEO対策を施す際は、やってはいけない行為に手を出さないよう注意してください。
コンテンツが充実しているWebサイトの強み

Webサイトの完成後は、コンテンツ制作に取り組みましょう。コンテンツが充実しているWebサイトには下記6つの強みがありますので、継続的な制作が大切です。
1.長期的な集客が可能になる
2.予期しない流入を得られる
3.ユーザーのニーズを掘り起こせる
4.既存顧客のアフターサポートに活用できる
5.営業活動にも役立つ
6.大変だからこそ差別化できる
1つずつ詳しく確認しましょう。
1.長期的な集客が可能になる
コンテンツが増えるほど、長期的に集客できます。自社サイトに掲載しているコンテンツは、削除しない限り消えません。SNSなどのフロー型メディアや第三者が運営しているメディアと異なり、自社サイトに蓄積されます。
豊富なコンテンツがあれば、検索エンジンからの流入や被リンクの獲得、他メディアの紹介といった経路が増えるでしょう。中でも、検索上位のコンテンツは集客力が高く、リライトを重ねることで制作から数年経っても新規ユーザーとの接点として機能し続けます。
2.予期しない流入を得られる
コンテンツが充実しているWebサイトは、予期しない流入を得られる機会も多くなるでしょう。コンテンツの数に比例して、ユーザーとの接点が増えるからです。ユーザーの中には、コンテンツを評価してSNSにシェアしてくれる人もいるでしょう。Twitter・Instagram・FacebookなどのSNSでコンテンツが拡散されれば、思わぬルートからの流入を得られるわけです。
コンテンツの専門性が深ければ、第三者メディアや個人ブログからの被リンクも得られるかもしれません。被リンクは新たな流入経路になるだけでなく、ドメインパワーの強化にも繋がります。サイト全体が上位表示されれば、予期しない流入がさらに生じやすくなります。
3.ユーザーのニーズを掘り起こせる
豊富なコンテンツは、ユーザーニーズの掘り起こしにも貢献します。自社サイトに辿り着くユーザーは、明確に欲しい製品を比較している顕在層だけでなく潜在層もいます。
具体的には、脆弱性診断サービスを扱う企業のオウンドメディアに「セキュリティ対策 企業」といった疑問解決のために流入する潜在層もいるわけです。サイトのコンテンツが充実していれば、以下の流れでニーズを育てられます。
企業が行うセキュリティ対策の解説→必要な対策の判断には脆弱性診断がおすすめ→脆弱性診断とは→おすすめの脆弱性診断サービスの比較→自社の脆弱性診断サービスへ誘導
コンバージョンを獲得するには、コンテンツ同士の内部リンクによる潜在層のニーズ育成が欠かせません。
4.既存顧客のアフターサポートに活用できる
充実したコンテンツは、既存顧客のアフターサポートにも活躍します。商品購入後の顧客は「バイヤーズリモース」と呼ばれる心理になりやすいです。バイヤーズリモースとは、購入後に「やっぱり買わないほうがよかったかも」と不安を抱いている状態です。バイヤーズリモースが高まると、顧客は商品を返品・キャンセルしてしまいます。
バイヤーズリモースの解消には、顧客に安心してもらう施策が必要です。購入商品の活用方法やメンテナンス、アレンジといった役立つ記事や動画を発信すれば、顧客のアフタフォローになります。満足度が上がればリピーター化も狙えるため、既存顧客に対するコンテンツ拡充も重要な施策です。
5.営業活動にも役立つ
サービスサイトのコンテンツが充実していると、営業活動にも役立ちます。機能や料金といった基本事項やよくある質問などの内容は、サービス導入を検討している顧客はある程度事前に閲覧してくれます。顧客は自社サービスに関する一定の知識を得ているので、問い合わせや商談がスムーズに進むでしょう。
また、商談中もサービスサイトの紹介ページやホワイトペーパーを使って、効率的に営業できます。制作したコンテンツを営業部門に活用してもらうには、営業部門が使いやすいようなコンテンツ整理も大切です。ホワイトペーパーや導入事例などの資料は、ストレージなど利用しやすい場所にアップロードしておくと良いでしょう。
6.大変だからこそ差別化できる
コンテンツマーケティングはWebサイト制作やコンテンツ作成など、非常に作業が多い施策です。数ある作業の中でも、コンテンツ制作を大変に感じる企業は多いと思われます。そのため、実際にコンテンツ制作に取り組み、継続できる企業は少ないでしょう。多くの企業が諦める中、めげずに取り組むからこそ競合他社との差別化を図れるわけです。
オウンドメディアであれば、自社の記事でさまざまなキーワードの検索上位を独占することで、メディアの地位を確立できます。強力な集客が可能になり、業界内で優位に立てるでしょう。Webサイトにコンテンツを増やすのは大変な作業ですが、その分だけ得られるリターンも大きい施策です。
Webサイトのアクセス数を増やすコツ

Webサイトやコンテンツを制作する際、アクセス数をKPIに設定するケースは多いのではないでしょうか。記事のおわりに、アクセス数を増やすコツを7つ紹介します。
1.ユーザーファーストなコンテンツを作る
2.ユーザーにストレスを与えない
3.更新頻度を下げない
4.スマートフォンの閲覧に対応する
5.オフラインの流入経路も設ける
6.必要に応じて広告も併用する
7.競合分析やアクセス解析で改善する
詳しいポイントを見てみましょう。
1.ユーザーファーストなコンテンツを作る
基本となるのが、コンテンツ作りです。自社製品のコンバージョンページだけでなく、ユーザーが知りたい内容や役に立つ情報を伝えるコンテンツを作成しましょう。
ユーザーファーストなコンテンツはSEO対策としても重要です。そもそもSEOの観点を抜きにしても、ユーザーは知る価値のないコンテンツを閲覧しません。仮に閲覧しても、期待していた内容と違えば早々に途中離脱し、再来訪もしないでしょう。被リンクの獲得やSNSの共有も生じず、思いがけずアクセス数が伸びるきっかけも起きません。ユーザーにとって有益なコンテンツの提供が、アクセスを増やす大前提となります。
2.ユーザーにストレスを与えない
ユーザーにストレスを与えないサイト設計も重要です。情報の位置がわかりやすく操作がスムーズなサイトは、ページの離脱率も低くなります。関連記事の回遊率も高まるので、アクセス数が増加します。一方で以下の項目に当てはまるサイトは、ユーザーがストレスを感じやすいです。
・文字のサイズが小さすぎる・大きすぎる
・文字と背景色の組み合わせが悪く見づらい
・画像が大きすぎる・多すぎる
・広告の位置が閲覧の邪魔になる
・カテゴリがわかりづらい
・表示速度が遅い
問題を抱えているサイトは多くのユーザーが離脱し、アクセス数が伸びないでしょう。
3.更新頻度を下げない
更新頻度が低いWebサイトは、読者が定着しません。再訪問しても更新されていない可能性が高く、わざわざアクセスしようと思わないためです。アクセス数が増えないばかりか、「この会社はもう閉業しているのでは」とサービスの問い合わせをためらわせてしまい、機会損失を招くかもしれません。
良質なコンテンツでも、リライトせずに最終更新日を数年前のまま放置していると、検索順位が下がる傾向があります。こまめなリライトや新規コンテンツの追加、新着情報の更新を行い、更新頻度を一定以上に保ちましょう。
4.スマートフォンの閲覧に対応する
Webサイトを閲覧するのはPC利用者だけではないため、スマートフォンの閲覧にも対応が必要です。スマートフォンから閲覧した際にレイアウトが崩れたり、文字が小さくなったりすると、サイトの視認性は非常に悪くなります。せっかく訪問してくれたユーザーが離脱し、再訪問も期待できません。
Webサイトを設計する際は、端末ごとに最適なレイアウトを自動的に表示する「レスポンシブデザイン」を採用しましょう。どの端末でも快適に閲覧できるので、スマートフォンやタブレットのユーザーを逃す心配がありません。
5.オフラインの流入経路も設ける
Webサイトへの流入は、オフラインの経路も大切です。インターネットの経路のみ想定しがちですが、オフラインの経路を設ければWeb上で接点を持てない人にも自社サイトへたどり着いてもらえます。
たとえば、既存顧客に送付するカタログやパンフレット、DMにWebサイトへ繋がるQRコードを載せると良いでしょう。アクセス数の増加に加え、既存顧客へのアフターフォロー用コンテンツへ誘導すればリピート率の向上も図れます。セミナーやイベントで配る資料にもURLを掲載すると、アクセス数アップに効果的です。
6.必要に応じて広告も併用する
Webサイトへ直接繋ぐ広告も、必要に応じて併用しましょう。リスティング広告やSNS広告を出稿すると、Webサイトへの流入を増やせます。リスティング広告は検索結果の上部に表示されるので、検索ボリュームが多いキーワードであるほど流入数の増加が見込めるでしょう。
ただし、単なるアクセス増加のみを目的として広告を出稿するのは、建設的ではありません。「誰にどのような導線で何を購買してほしいのか」を設計し、広告のターゲティング設定を行いましょう。
7.競合分析やアクセス解析で改善する
既存コンテンツの改善も、Webサイトのアクセス数を増やすために欠かせない作業です。アクセス解析ツールを用いると、改善に役立つ客観的なデータを得られます。具体的には、ユーザーの使用デバイスや属性、流入経路、直帰率や閲覧数が高いページなどのデータです。
一例を挙げると、「アクセス数と直帰率が高いページ」は、せっかく集客できているのに他のページへ誘導できていないとわかります。内部リンクの導線が失敗している、もしくはタイトルと内容が乖離しているかもしれません。また、競合サイトの上位記事やサイト構造も分析し、良い点は自社サイトに取り入れましょう。
コンテンツマーケティングはWebサイトの情報発信が重要な施策
コンテンツマーケティングで制作するWebサイトは、オウンドメディアやコーポレートサイト、ブランドサイトなどの種類があります。それぞれのサイトは制作目的や掲載するコンテンツが違うため、マーケティング施策の目標に合わせた選択が重要です。
制作したWebサイトを中心に情報発信し、売上アップやブランディングなどの目標達成を目指しましょう。