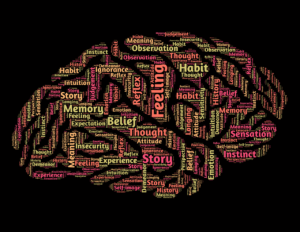Web記事中心のコンテンツマーケティングを行う際、必要な記事数を知りたいと思う人もいるのではないでしょうか。しかし、コンテンツマーケティングは量よりも質が大事な施策です。焦らず質が高い記事を作り、着実に増やしましょう。
この記事では、良質な記事数を増やすメリットを解説します。記事制作時の避けるべきポイントやリライト方法なども紹介しますので、記事の執筆をする際にはぜひお役立てください。
コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
コンテンツマーケティングに必要な記事数は決まっている?
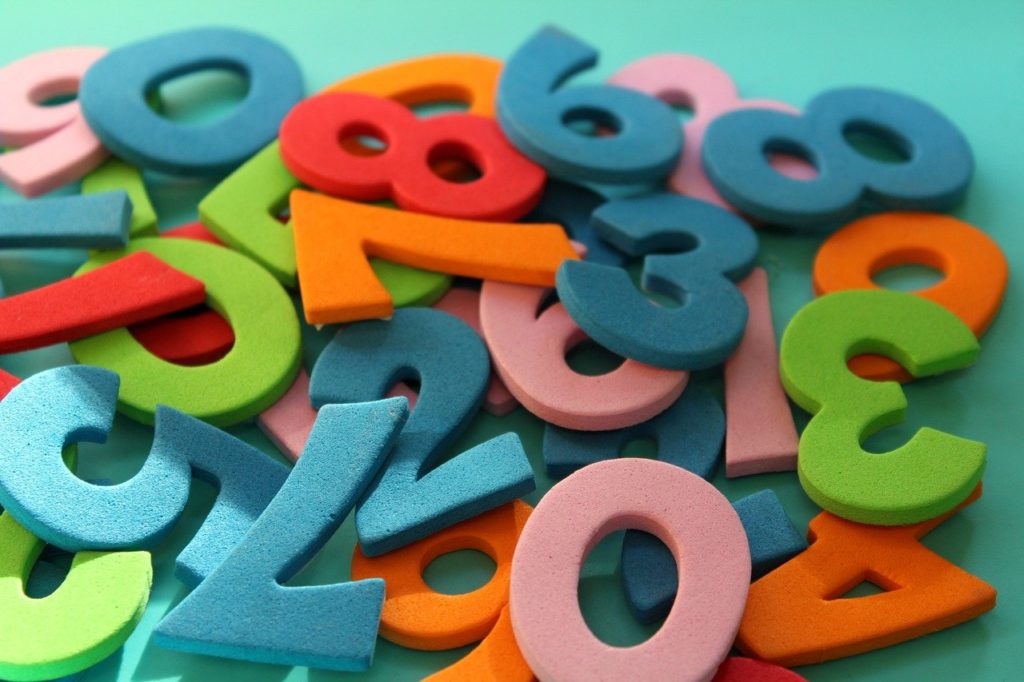
結論から伝えると、コンテンツマーケティングに必要な記事数は決まっていません。コンテンツマーケティングで記事を作る際、多くの企業がSEO対策をするかと思います。インターネット上にはSEOに関する定説が溢れており、記事数に関するセオリーも多数存在します。そのため、「100記事は必要と言っているサイトを見たよ?」と疑問に思う方もいるでしょう。
しかし、いずれの定説も、検索エンジンを提供するGoogleの公式見解ではありません。Googleは、SEOに効果的な記事数を一切明言していないからです。Googleが非公表にしている以上はすべて憶測に過ぎないため、定説の記事数にこだわりすぎるのは得策とは言えません。中には実績を元に伝えている記事もあると思いますが、サイトの状況や狙うキーワードによって、一概に同じ結果になるとは限りませんので注意してください。
「記事数が大事」と言われる理由
Googleの公式見解がないにもかかわらず、「100記事書く」といった記事数にこだわる定説が見られるのはなぜでしょうか。よくある理由が、「記事を書く練習になる」と「アクセス数を増やす」の2つです。個人ブログなら記事を量産して練習しても問題ないですが、企業の戦略で行うコンテンツマーケティングを練習台にするのはおすすめできません。
一方、アクセス数の増加はコンテンツマーケティングにおいても大切です。アクセスを増やす手段として「月間10記事公開する」と目標設定しても良いですが、目的化しないよう気をつけましょう。記事の量産を目的とせず、質を重視した記事作りが重要です。
Googleの評価基準は記事数ではなく「記事の質」
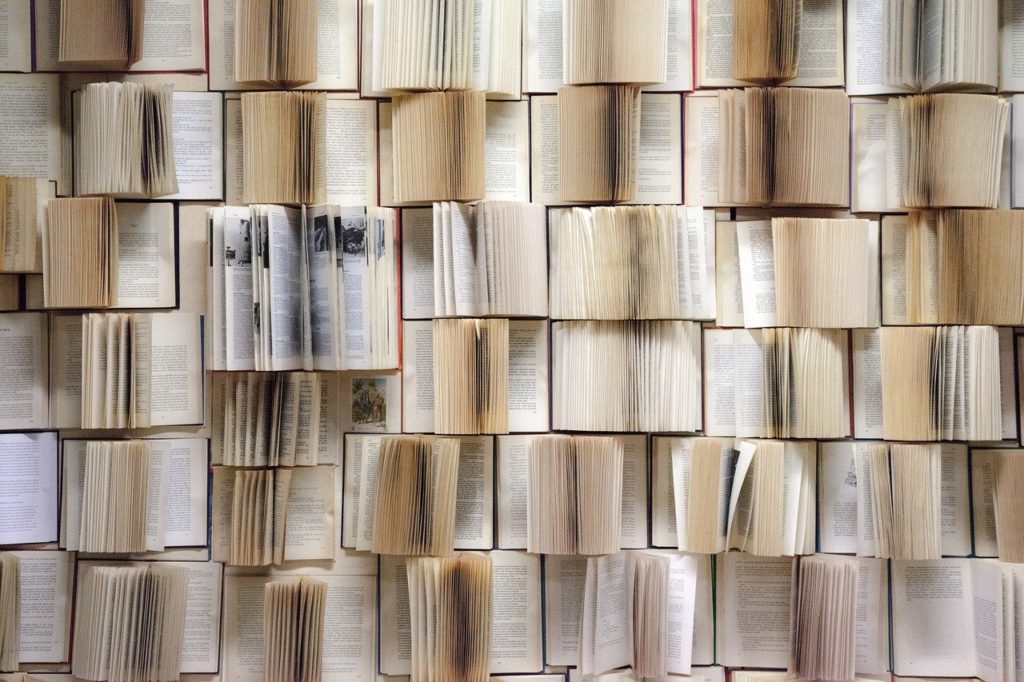
コンテンツマーケティングの記事制作で大切なのは、記事数ではなく記事の質です。実際にGoogleは、「低品質な記事の掲載順位を下げ、高品質な記事の順位を上げる」と発表しています。
さらに、検索エンジンのアルゴリズムは非公表ですが、Googleは「SEOスターターガイド」にてコンテンツを最適化させる方法を示しています。Googleの公式見解にもとづき、高品質な記事の3つの特徴を見ていきましょう。なお、アルゴリズムやGoogleポリシーは流動的ですので、2022年現在の情報である点にご注意ください。
参考:Google検索セントラル「SEOスターターガイド」
https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=ja
1.検索意図を満たす内容
1つ目のポイントは、ユーザーの検索意図を満たす内容です。「ユーザーは何を知りたくて検索しているのか?」と検索意図を考え、疑問に応えられる内容を提供します。基本事項として、わかりやすい文章力と構成が大切です。
加えて、ユーザーの検索に使用する単語「検索クエリ」を想定しましょう。たとえば、ダイエットの停滞期に悩むユーザーの中で、ある程度知識がある人は「ダイエット 停滞期」と検索します。停滞期の概念を知らない人は、「ダイエット 体重 減らなくなった」といった検索クエリを使用するでしょう。さまざまなユーザーの検索クエリを想定して内容に盛り込み、疑問解決に役立つ情報を提供することで記事の評価が高まります。
2.専門的で信頼できる記事
記事の専門性と信頼性の高さも、評価に繋がる重要な要素です。オウンドメディアの方向性や目的を統一して、特定のジャンルに絞って記事を制作しましょう。オウンドメディアの運営者を明らかにし、サイト自体の信頼性を上げることも大切です。
また、必要に応じて、記事の根拠となる資料を明確に示しましょう。仮に自動車業界の市場規模を解説するならば、市場規模の数値や調査年度を参照したレポートを出典元として明記します。根拠を示さないと、読者は「この数字はどこから来たの?」と疑問に思うかもしれません。高度な専門知識を扱う記事の場合、専門家に監修してもらう方法もおすすめです。
3.オリジナルの情報
コンテンツの評価を高めるには、記事のオリジナリティも求められます。競合メディアと同じキーワードで記事を制作するにしても、自社ならではの独自の内容を盛り込みましょう。オリジナルの情報を提供すればオウンドメディア自体の価値が高まり、新たな読者獲得にも繋がります。
独自性を上げるためのよくある手法が、一次情報の提供です。具体的には、専門家へのインタビューや観光地の現地取材が該当します。その他、特定テーマに関するアンケートの実施も、一次情報としての価値が生まれます。
高品質な記事なら記事数は無関係?
質の高い記事の特徴を3つ紹介しましたが、ビッグキーワードであるほど単一ページでは上位表示が難しい傾向があります。つまり、Googleはオウンドメディア全体の必要記事数は公表していないものの、キーワードによっては上位表示に必要な関連記事数が存在する可能性があるわけです。
SEOツールによっては、「上位表示させるために最低限必要な関連記事数」を分析・予測できるものがあります。たとえば、株式会社オロパスのSEOツール「Pascal (パスカル)」は、キーワードごとに上位記事を解析し、必要な記事数の傾向予測が可能です。キーワードによって、記事数が一切無関係ではない可能性がある点に留意しましょう。キーワードによっては記事の数も順位に影響を与えることがあるでしょう。
コンテンツマーケティングで良質な記事数を増やすメリットは?

SEOの観点から、単純に記事数が多くても評価には繋がらないと説明しました。しかし、良質な記事数を増やす意味がないわけではありません。良質な記事の増加により、得られる4つのメリットを解説します。
1.多くのユーザーを集められる
高品質な記事が多いほど、ユーザーとの接点が増えます。コンテンツマーケティングは、ターゲットのニーズを想定し、検索するであろうキーワードで記事を制作するのが基本です。記事数が増えた分だけ、さまざまなニーズを持つユーザーに自社メディアへ訪問してもらえるわけです。質の高い記事は検索順位も高くなりやすいので、流入数もさらに増えるでしょう。
2.導線設計が豊富になる
Webサイト内の記事数が増えれば、記事同士の内部リンクも豊富になります。購買や資料請求などのコンバージョンへさまざまな経路で導線設計を組めるため、成果獲得に繋がるでしょう。コンバージョン以外にも、読者にとって価値のある記事同士で内部リンクを増やせます。読者の定着・ファン化にも効果的ですので、良質な記事数の増加は大切です。
3.サイトのドメインが評価される
高品質な記事が多いサイトは、ドメインパワーが強くなります。ドメインパワーとは、名前の通りWebサイトのドメインの力を表す用語です。Googleが公式に定義した言葉ではありませんが、ドメインパワーが強いサイトのコンテンツは上位表示されやすくなります。新規記事でもすぐに集客できるため、良質な記事を増やしてドメインパワーを強めることが重要です。
4.検索エンジン以外の流入も見込める
質の高い記事があれば、検索エンジン以外の流入経路も拡大するでしょう。たとえば、読者によるSNSへの投稿・拡散や、第三者サイトからの被リンクといった経路です。また、Googleは「Googleが掲げる10の事実」(※1)にて、被リンクも記事の質を評価するポイントに含まれる旨を表記しています。流入経路の増加は記事の評価向上や広告費の削減にも繋がるので、良質な記事作りを心がけましょう。
※1 出典:Google「Googleが掲げる10の事実」
https://about.google/philosophy/?hl=ja
記事数を増やす際に避けるべきポイントは?

記事数を増やす際は、低品質な記事と評価されないように気をつけましょう。さらに、記事の品質に加え、マーケティング上の注意点もあります。まとめて、記事数を増やす際に避けるべきポイントを5つ説明します。
1.ツールによる自動生成
人間が書かず、自動生成ツールによって生み出した文章を掲載してはいけません。自動生成した文章の中で、文法は正しくても単語の組み合わせがおかしいものを「ワードサラダ」と呼びます。かつては、被リンクを自作自演するためにワードサラダを用いるケースがありました。
しかし、現在Googleは自動生成したコンテンツや、質の低い不自然な被リンクを得ているページは検索結果へ表示しない対策を行っています。機械翻訳したまま正しい日本語に直していない文章も該当しますので、注意しましょう。
2.検索キーワードの乱用・隠しテキスト
SEOを意識しすぎるあまり、ユーザーが検索しそうなキーワードを無意味に使うのは避けましょう。無関係な単語の羅列のほか、同じ単語の不自然な繰り返しも当てはまります。文章が読みづらくなる上にGoogleの「品質に関するガイドライン」違反となり、検索順位が下がる可能性があります。SEOキーワードは、自然な文章の範囲で使用しましょう。
SEOキーワードを読者に見えないように細工する「隠しテキスト」も、ガイドライン違反です。ただし、画像を説明する「alt属性」のような隠すべきテキストは問題ありません。
3.文章の無断転載
他のサイトの文章をコピーし、そのまま使ってはいけません。独自性がないためユーザーが読む価値がなく、Googleからの評価が下がります。さらに、Web上のテキストは著作権法における「著作物」にあたりますので、著作権の侵害行為にもなります。
とはいえ、資料やレポートの文章をそのまま使いたい場合もあるでしょう。そうしたケースでは著作権法上の「引用」の決まりを守れば、第三者の文章を自社メディアに掲載できます。「出典元の表記」など複数の決まりがありますので、詳しくは文化庁の案内「著作物が自由に使える場合」をご覧ください。
参考:文化庁「著作物が自由に使える場合」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
4.コンテンツ同士の重複
内容がほとんど同じ、あるいは完全に同じ記事の制作も避けるべきポイントです。Googleからの評価が分散される上に、ユーザーはどちらを読むべきか迷うでしょう。こうした重複コンテンツによる評価分散を「キーワードカニバリゼーション」と言います。
コンテンツマーケティングはメディアの方向性に沿って記事を制作するため、うっかりネタ被りしてキーワードカニバリゼーションを起こすかもしれません。重複コンテンツに気づいたら、「1つのコンテンツにまとめる」「どちらかの構成を変える・内容を追加する」といった方法で修正しましょう。
5.検索ボリュームが多い記事ばかり作らない
検索ボリュームが多いキーワードはそれだけ需要がありますが、そうした記事だけ作るのはおすすめできません。自社のターゲット・ペルソナが求める情報を仮定し、検索ボリュームが少なくてもニーズがある「ロングテールキーワード」にもとづいた記事も制作してみてください。ロングテールキーワードとは、3〜4単語で構成される検索クエリです。もちろん、検索ボリュームが多い記事も必要ですので、どちらもバランスよく制作しましょう。
関連するキーワードを網羅的に対策することも重要です。
安定して記事数を増やすならSEOツール活用がおすすめ

記事数はオウンドメディア全体の評価に直接関係はしないものの、コンテンツマーケティングにおいて継続的な記事制作は大切です。安定して新規コンテンツが公開されないメディアにはユーザーが定着しません。ユーザーのファン化が進まず、利益が生まれづらくなります。継続的に良質な記事数を増やすなら、SEOツールの導入がおすすめです。
SEOツールでできること
SEOツールは、検索順位の上昇を狙う記事作りを支援するツールです。主に、以下の機能があります。
・SEOキーワードの選定
・競合分析
・アクセス解析
・検索順位チェック
・内部診断
・キーワードに必要な関連記事数の予測
ひと口にSEOツールといっても、提供ベンダーごとに機能が違います。各機能の特化ツールや総合ツール、無料で使える簡易ツールなどがありますので、導入する際は必要な機能があるサービスを選びましょう。
SEOツールのメリット
SEOツールを導入するメリットとして、記事制作の効率化が挙げられます。SEOツールを使わない場合、担当者は競合サイトの分析、検索ボリュームの調査、ユーザーニーズの把握などの作業を自身で行わなければいけません。SEOツールは検索キーワードの選定に関する作業を自動化できるため、作業時間の大幅な短縮を見込めるでしょう。
さらに前述の通り、キーワードの中には関連記事がないと上位表示されない単語も存在すると考えられます。「上位表示に必要な関連記事数」を予測できるSEOツールを使えば、単独では上位表示が難しいキーワードでも適切な施策が可能です。「せっかく良い記事を書いたのになぜか検索順位が上がらない」といった事態を回避したい場合は、記事数予測に対応しているSEOツールを選びましょう。
そもそも人員不足で記事数を増やせない場合は?

SEOツールを導入しても、人員不足が理由で安定して記事数を増やすのは難しいケースもあります。コンテンツ制作が滞ると、コンテンツマーケティング自体に悪影響が出るでしょう。予算に余裕があるなら、外部委託を検討してみてはいかがでしょうか。主な委託先を3つ紹介します。
1.コンテンツマーケティング代行会社
1つ目の委託先が、コンテンツマーケティング代行会社です。SEO記事の制作から運用代行、効果検証・改善まで、コンテンツマーケティングの施策全般を依頼できます。コンテンツ制作のみなど、部分的な依頼も可能です。また、企画段階からコンサルティングとして携わり、戦略設計を提案してくれる会社もあります。
2.記事制作代行会社
記事制作代行会社には、SEO記事の制作に関する部分のみを依頼します。キーワード選定、構成・ライティング、校閲、画像作成など、記事制作業務をトータルで任せられます。SEO記事制作のプロが記事を作るため、専門性・独自性ともに高いコンテンツを自社メディアで継続的に発信できるでしょう。
3.クラウドソーシングサービス
クラウドソーシングサービスを利用し、ライターを募集する方法もあります。基本的に、応募してくるのは個人ライターです。ライターと直接やりとりするので依頼作業がスムーズになり、代行費用も抑えやすい方法と言えます。ただし、ライターによりスキルの差が激しいので、テストライティングを実施して慎重に見極めましょう。
順調に記事数が増えたらリライトも行おう

公開している記事が増えたら、リライトも並行して行いましょう。Googleアルゴリズムのアップデートや新規競合の出現といった要因により、公開した記事の検索順位は変動します。検索結果1位の記事でも下位に転落する可能性があるため、既存記事の定期的なリライトが重要です。
全記事のリライトは不要
既存記事の調整が大事とはいえ、全記事のリライトは不要です。たとえば、検索順位が高い記事や、安定してコンバージョンが発生している記事はそのままで良いでしょう。ただし、情報鮮度や誤字脱字の確認・修正は適宜必要になります。主にリライトすべき対象は、次のどちらかに当てはまる記事です。
・検索順位が低い
・検索順位は高いのにクリック率(CTR)が低い
上記の記事は、Web解析ツールやSEOツールを使うとスムーズに発見できます。
リライトの方法
リライトの前提として、読者の疑問を解決できる内容であるかが重要です。競合記事と比較して不足している情報があれば追加し、「この記事を読んでも疑問解決にならず、さらに検索しなくてはいけない」状況を防ぎましょう。また、オリジナリティの付与も忘れてはいけません。コンテンツを充実させた上で、以下の技術的なポイントをチェックしてみてください。
・検索意図に沿ったタイトルへの変更
・記事の内容をまとめたディスクリプションの追加・変更
・読者が読みたい位置にジャンプできる目次の作成
・記事本文への共起語の追加
・文字量の調整
・更新日の追加
・内部リンクの設置
上記のリライト実施後は、効果検証を必ず実施しましょう。
リライト後は効果検証が必須
リライトの方向性が正しいのかを検証するため、Web解析ツールで数値を確認してください。もっとも重要な項目が、検索順位の変動です。順位が上昇すればリライトの効果が出たと言えるので、しばらくは順位変動を静観しましょう。反対に、順位が下降した場合はただちにリライト前の記事に戻し、同じく順位変動をチェックしてください。
その他、クリック率、コンバージョン率、直帰率といった数値を確認して、リライト前後の状態を比較します。「どういったリライトによりどんな効果が生まれたのか」を分析し、仮説を立てましょう。仮説を他の記事のリライトに活かして効果検証を重ねることで、新規記事作成のノウハウを蓄積できます。
リライト以外の改善点も確認する
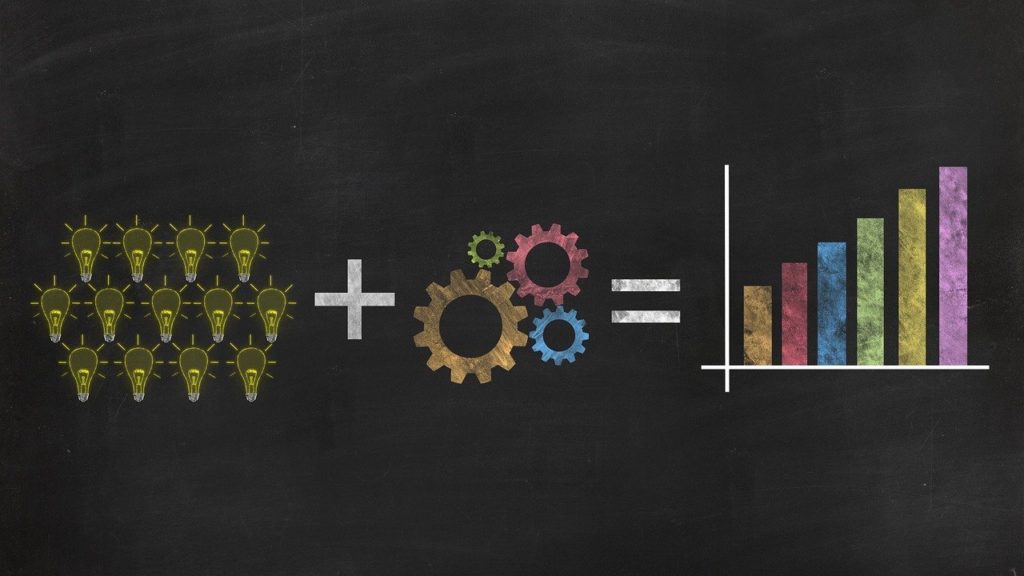
リライトは、テキストを重点的に見る施策です。リライト以外にも改善点がないか、定期的に確認しましょう。たとえば、サイトデザインやUI設計が見づらいと、直帰率の上昇やコンバージョンの伸び悩みを招きます。CTAボタンの配置を見直したり画像を最適化したりして、全体的に見やすいデザインに改善しましょう。
Webサイトの改善には、ユーザーの行動が可視化される「ヒートマップツール」が役立ちます。ユーザーの離脱地点や熟読地点がわかるので、客観的な改善策を実施できるでしょう。制作した良質なコンテンツを多くの人に届けるには、リライトとWebサイト改善の両方を進めることが大切です。
サイトのゴールである「問い合わせ」や「資料ダウンロード」など、結果を検証しながら、リライトを行いましょう。
コンテンツマーケティングは質の高い記事を増やすことが重要
コンテンツマーケティングで成果を出すには、記事の質を重視しましょう。「月に10記事制作する」と記事数の目標を設定するのは問題ありませんが、記事の量産が目的化しないよう注意してください。良質な記事を増やすことを念頭に置き、読者にとって価値のあるコンテンツを作りましょう。公開した記事は放置せず、リライトによる検索順位の維持・上昇が重要です。