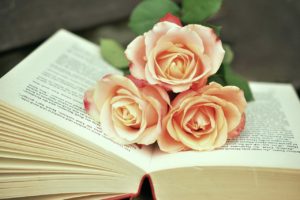コンテンツマーケティングを実践していく上で、1つのコンテンツの文字数はどれぐらいが良いのでしょうか。インターネット上には文字数に関するさまざまな情報や資料があり、迷われる人も多いでしょう。さらに検索エンジンで上位表示されるためにはSEO対策も必要です。
この記事ではコンテンツマーケティングに最適な文字数を調べている方に向けて、上位表示されるために必要な文字数とSEOとの関係、検索エンジンの仕組みなどを解説します。
コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事でまとめていますのでご参照ください。
コンテンツの文字数はSEOに関係する?

コンテンツマーケティングにおいて重要な役割を果たすオウンドメディアには、WEBサイトやブログなどがあります。これらのコンテンツは、検索エンジンで上位表示されることで、検索するユーザーの目にとまりやすくなり、集客や売上アップにつながります。
そのためコンテンツマーケティングにはSEO対策が必要ですが、コンテンツ自体の文字数はSEOに影響するのか気になるところです。結論から言えば、文字数の多さだけが直接SEOに影響するようなことはありません。
Google社でスポークスマンとしての役割をはたしているジョン・ミューラー氏(John Mueller)はコンテンツの文字数について次のように発言しています。
・Googlebotは単にコンテンツの文字数や単語数を数えているわけではない
・短い記事でも長いディスカッションのきっかけになり、検索ユーザーが探し当てる場合もある
Googleをはじめとする検索エンジンはコンテンツの文字の多さではなく、クオリティを重視する傾向にあります。しかし、記事の種類によっては情報の網羅性が必要になることがあるため、結果、文字数を多くすべきこともある点に注意しましょう。コンテンツの種類やキーワードによって、適切な文字数は異なります。多めの文字数がベターなことも短めの文字数がベターなことも、どちらもあるのです。
文字数に関するさまざまな定説

コンテンツマーケティングにおいてSEO対策に効果的といわれる文字数にはさまざまな定説が存在します。初心者のうちは、定説にそってコンテンツ制作を進めがちですが、定説が必ずしも正解ではない点に注意が必要です。検索エンジンでは、検索するユーザーにメリットのある質の高いコンテンツが優先され、上位表示の可能性が高まります。そのため、次のような点を意識してコンテンツ制作をすすめましょう。
・競合サイトを参考にする
・WEBサイトなどで最も重要なキーワードを前半に入れる
・必要に応じて専用ツールで分析する
世間的によく言われる定説には次のようなものがあります。
Web製作の会社やSEOコンサルタントの方のセミナーなどで、以下のようなことを聞いたことはありませんか?
・上位表示を目指すには1記事につき文章は2,000~4,000文字程度は必要
・コンテンツのタイトルの文字数は、PCで30~32文字、スマートフォンで30~41文字が最適
1記事の文字数にはさまざまな定説があり、実際に上位表示されているコンテンツの文字数が関係している可能性はあります。タイトルの文字数は、デバイスによって表示サイズが異なり、当該文字数であればすべてのテキストが画面上に表示されるのが大きな理由とされています。しかし、あくまでも仮説に過ぎず、Googleが公表しているデータではないことに注意しましょう。
※あくまでも定説の一つです
文字数の多いコンテンツがSEOに有利といわれるのはなぜ?

すでにご紹介したように、文字数の多さだけが直接的にSEOに影響することはありませんが、長文コンテンツやロングコンテンツと呼ばれる文字数が5,000文字や1万文字などのコンテンツは検索エンジンで上位表示されることが多い傾向にあります。
文字数の多いコンテンツが上位表示される理由には次のようなことが可能性として考えられます。
・質の高いコンテンツは文字数が多くなる
・共起語や関連ワードを入れると文字数が多くなる
・画像や動画よりも文字が重要視される
・多くの被リンクを得られる
それぞれについて詳しく解説します。
質の高いコンテンツは文字数が多くなる
Google社によると専門性、権威性、信頼性のある質の高いコンテンツが検索にとって重要とされています。検索ユーザーが知りたい情報を網羅すると、おのずとコンテンツの文字数は多くなります。
例えば「コンテンツマーケティング」のキーワードで検索するユーザーの場合、知りたい情報は、「コンテンツマーケティングとは」という簡単なものから、「コンテンツマーケティング 事例」や「コンテンツマーケティング 戦略」など内容は多岐にわたります。そのため、ある程度の文字数が必要になるのです。
また、SEO対策には直接的には影響するかどうかは不明ですが、情報量が多く内容が充実しているコンテンツは、ユーザーのページ滞在時間も長くなります。ページ滞在時間が長くなると、次のようなメリットがあります。
・オウンドメディアなどで自社が提供するサービスや商品の認知度が上がる
・サイトの直帰率が低くなる
・内部リンクを踏んでもらえる可能性が高まる
ただし、文字数だけが多くて質が低いコンテンツに対しては、Google社では次のように発表しています。
「Googleでは、無断複製されたページや、オリジナルのコンテンツがほとんどなくユーザーにとって価値のないページを表示することでランキングに入ろうとするドメインに対して、処置を取ります」(※1)
検索ユーザーのニーズを汲み取り、なおかつオリジナルのコンテンツを制作することが大切なのです。
※1 出典:【Google 検索セントラル】質の低いコンテンツ
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/thin-content
共起語や関連ワードを入れると文字数が多くなる
特定のキーワードとともに検索される可能性が高い共起語や関連キーワードをコンテンツに含めると、自然に文字数は多くなります。「コンテンツマーケティング」の共起語には「マーケティング」「ユーザー」「顧客」「自社」「企業」「必要」「SEO」などが挙げられます。関連キーワードは、「事例」「成功事例」「企業」「費用」「WEBマーケティング」「とは 簡単に」「戦略」「必要性」などです。
「コンテンツマーケティング」について知りたいユーザーは、これらのキーワードも同時に検索することが多いため、コンテンツに含めればユーザーの疑問や問題を解決でき、検索エンジンの評価も上がる可能性が高まります。複数のキーワードを組み合わせると、結果的に文字数は増えるので、自然と上位表示されやすくなるといえるでしょう。
共起語や関連キーワードは無料ツールでも選定できますが、ユーザーのニーズをより正確に把握するためには、分析ツールやキーワード選定サービスなどを利用するのがおすすめです。
文字のカウントや共起語の含有率などを調査する際にもSEOツールを利用すると良いでしょう。競合サイトよりも文字数が多くなっているか、競合サイトが利用している共通言語を使用しているかなど、確認することができます。
画像や動画よりも文字が重要視される
Google社のジョン・ミューラー氏は、画像や動画コンテンツにおいても常にテキストが必要と述べています。視覚的に分かりやすい画像や動画コンテンツはユーザーの目をひく可能性は高くなりますが、検索エンジンの評価を得るためには文字も必要なのです。
Googleのアルゴリズムでは画像や動画を言語化して評価の対象とします。しかし、このアルゴリズムではコンテンツを提供する側の意図が正確に伝わるとは限りません。画像や動画をコンテンツに使用する場合は、あわせて文字での解説も不可欠といえます。
文字中心のコンテンツに画像を入れる場合は、内容に即した関連性の高いものを選びましょう。SEOについて書かれたコンテンツであれば、「SEO」とテキストの入った画像やパソコンの画像など、SEOを連想させる画像が好ましいでしょう。
ただし、画像をタイトルや見出し代わりに使用するのは避けましょう。タイトルや見出しに含まれるキーワードは検索エンジンの評価に影響する可能性が高いためです。Google社でも次のように発表しています。
「画像にテキストを埋め込むことは避けてください。特に、ページ見出しやメニュー項目などの重要なテキスト要素は埋め込まないでください。これは、すべてのユーザーがアクセスできるわけではないためです(また、ページ翻訳ツールも画像では動作しません)。ユーザーがコンテンツに最大限アクセスできるよう、テキストは HTML形式で作成し、画像に代替テキストを設定してください」(※2)
あわせて次のような方法をとるとSEO対策として十分となる可能性が高まります。
・画像のファイル名を変更する
・alt属性(代替テキスト)を記述する
画像提供サイトなどからダウンロードした画像のファイル名は、初期設定ではアルファベットと数字の組み合わせになっているのが一般的です。しかし、意味のない英語と数字の羅列では検索エンジンのクローラーに認識してもらえません。「コンテンツマーケティング」に関する画像であれば「content-marketing.jpg」のように関連するファイル名に変更すると良いでしょう。
alt属性(代替テキスト)は、通信事情などで画像が表示できなかった時にどのような画像なのかを説明するためのテキストです。また、ファイル名と同様に検索エンジンのクローラーが認識してもらうための目的も持っています。
Googleの検索画面をイメージした画像の場合は「Googleの検索画面」といった簡潔に内容が分かるテキストが良いでしょう。
※2 参照:【Google 検索セントラル】Google 画像検索でのおすすめの方法
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/google-images?hl=ja
多くの被リンクを得られる
クオリティが高く上質でユーザーから信頼される長文のコンテンツは、他のサイトからの被リンクを得られやすい傾向にあります。被リンクの多さはWEBサイトのブランディングやドメインパワーの向上につながります。また、質の良いサイトからの被リンクを得られれば、検索エンジンからも評価され上位表示の可能性が高まります。
Googleを始めとする検索エンジンのクローラーは、リンクをたどって情報を登録するため、多くの被リンクを得ているサイトはクローラーに見つけてもらいやすくなるのです。被リンクを得るために、正確な情報が多く含まれるコンテンツ作成を意識していきましょう。
検索キーワードによって最適な文字数は異なる

文字数の多いコンテンツが必ずしも上位表示されるとは限りませんが、高品質なコンテンツにはある程度の文字数が必要です。検索エンジンでは、ユーザーの検索意図にマッチしたコンテンツが上位表示されるため、検索キーワードによって最適な文字数は異なります。
例えばその日の気温や天気を知りたい場合、端的に正確な情報を伝えればユーザーのニーズは満たされるため、少ない文字数でも良い可能性があります。しかし、専門的な知識が必要だったり検索ニーズが多岐にわたったりする場合、さまざまな情報を網羅している長文コンテンツが有利といえるでしょう。
ただし定説にある「何文字以上」や「何文字以下」などのように、決まった文字数にとらわれないよう注意しましょう。コンテンツマーケティングにおいて検索上位を目指すなら、検索キーワードやコンテンツを掲載するタイミング、競合記事の状況、Googleアルゴリズムの変動、ターゲットなどさまざまな要因を加味して文字数を決めると良いでしょう。
検索エンジンに評価されるために必要なこと

キーワードによって、コンテンツに最適な文字数が異なることを解説しました。コンテンツマーケティングでは検索ユーザーにとって有益な情報を提供することが非常に重要です。具体的には次のようなコンテンツが望ましいとされています。
・専門性の高い情報
・ユーザーの検索意図を汲み取る
・ユーザビリティを重視
これらを意識したコンテンツは、ユーザーだけでなく検索エンジンからの評価も高くなる可能性があります。それぞれについて詳しく解説します。
専門性の高い情報
どのようなジャンルにおいても専門性の高い情報を網羅していると、質の高いコンテンツと認めてもらえる可能性が高くなります。一般的にその分野において権威のある人が書いたコンテンツや大企業が発信するコンテンツは、専門性が高く、信頼できる情報を掲載しているといえるでしょう。
特定のキーワードやテーマについて知見がない人がコンテンツ制作に関わる場合は、信頼できる一次情報を参考にすると良いでしょう。しかし、コピーコンテンツとみなされるような内容のない情報は、かえってマイナス評価になる可能性があります。Google社が質の高いコンテンツとしてみなす基準には次のようなものがあります。
・同じトピックや類似のトピックに対してキーワードのバリエーションをわずかに変えただけの、重複している記事や冗長な記事が含まれていないか
・コンテンツが多数のクリエイターへの外部委託によって大量に制作されているために、または複数サイトの大規模なネットワークに拡散されているために、個々のページまたはサイトのプレゼンスが低下していないか
・記事が短すぎないか、不完全でないか、有用な詳細情報が不足していないか
(※3)
特に外部リソースにコンテンツ制作を依頼する際には気をつけましょう。またGoogleでは2022年現在、良質なコンテンツを評価するために「E-A-T」という基準を設けています。
・E:Expertise(専門性)
・A:Authoritativeness(権威性)
・T:Trustworthiness(信頼性)
Googleでは特別な訓練を受けた検索品質評価者がこれらの観点から、アルゴリズムが正しく機能しているかをチェックしています。
※3 参照:【Google 検索セントラル】質の高いサイトと見なされるもの
https://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality?hl=ja
ユーザーの検索意図を汲み取る
検索ユーザーの検索意図を正確に把握することも非常に重要な点です。ユーザーの視点にたって考えて「どんな情報を知りたいのか」を的確に把握しましょう。例えば「足 ツボ」と検索するユーザーの中には、足のツボのマッサージの方法などの基本的な情報を知りたい人からマッサージ店を探している人、足ツボグッズを探している人など、さまざまです。検索意図を把握できていれば、ぞれぞれのユーザーに対して効果的なアプローチができるでしょう。
ユーザーが検索するキーワードについて、月にどれくらいの量が検索されているかなどの情報もコンテンツ制作に役立ちます。Google Search Consoleなどでも分析が可能ですが、難しい場合は専門家に相談するのも良いでしょう。
ユーザビリティを重視
コンテンツマーケティングでは、サイトのユーザビリティ=使いやすさも検索上位を目指すためには欠かせない要素です。分かりやすいコンテンツ作り以外にも、ユーザーがストレスを感じずに閲覧できるサイト設計を心がけましょう。具体的には次のような点が挙げられます。
・読みやすいテキストやフォント
・サイトマップや目次の設置
・ページの表示速度
・専門用語を多用しない
・画面遷移がスムーズ
・どのデバイスでも読みやすいサイトを作る
これらはあくまでも一例ですが、ユーザビリティを向上させることでコンテンツの評価も上がるでしょう。
知っておきたい検索エンジンの仕組み

オウンドメディアなどのアクセス数アップを目指すためには、検索エンジンの評価の仕組みを理解しておきたいものです。Googleの仕組みを例に詳しくご紹介します。
検索順位が決まる仕組み
Googleで検索した時に表示される順位は次のような流れで決まります。
1.クローリング
2.インデックス
3.検索結果の表示
クローリングとは、クローラーと呼ばれるロボットがインターネット上のリンクをたどってWEBサイトをスキャンするプログラムを指します。GoogleではGooglebotがインターネット上を巡回して、HTMLファイルやPHPファイル、PDFなどあらゆる情報を収集します。
インデックスは、クローラーが収集した情報を大規模なデータベースに登録することを指します。インデックス登録されることで検索画面にサイトが表示されるようになります。新しいコンテンツがインデックス登録されているかどうかは、Google Search Consoleなどで確認できます。
このインデックス登録した情報をもとに、コンテンツの評価が行われ、ユーザーの検索キーワードに関連性の高い順に検索結果に表示されるのです。
検索アルゴリズムの仕組み
Googleでは、検索順位を左右する要因として5つの条件を挙げています。なお、Googleのアルゴリズムは常に変わっていくため、今回ご紹介する要因以外にも追加や変更がなされる可能性があります。今後の動向にも注意しておきましょう。
・検索クエリの把握
ユーザーの検索クエリの背後にはどんな意図があるのかを把握して、意図に合ったコンテンツを上位表示させます。
・コンテンツの関連性
コンテンツを分析して、ユーザーの検索クエリに合った情報が掲載されているかを評価します。
・コンテンツの質
専門性、権威性、信頼性の高いコンテンツを評価します。
・ウェブサイトのユーザビリティ
コンテンツのユーザビリティを評価します。
・コンテキストと設定
ユーザーが住んでいる国や地域のコンテンツを優先的に表示させます。
これらの要因を意識して、上質なコンテンツを増やすことで検索エンジンの評価を上げていきましょう。
コンテンツマーケティングの文字数はツールを活用して決めよう!
コンテンツマーケティングでは検索上位を獲得するために最適な文字数の定説はさまざまです。しかし、実際にはGoogleアルゴリズムの変動や上位表示を狙いたいキーワード、ターゲットなどによって最適な文字数は異なり、緻密な分析が必要になります。
分析ツールやSEOツールなどを活用して、コンテンツ制作をすすめる上で最適な文字数を決め、質の高いコンテンツを制作しましょう。