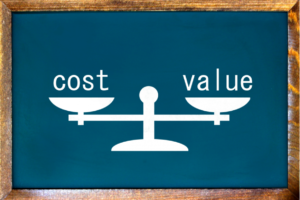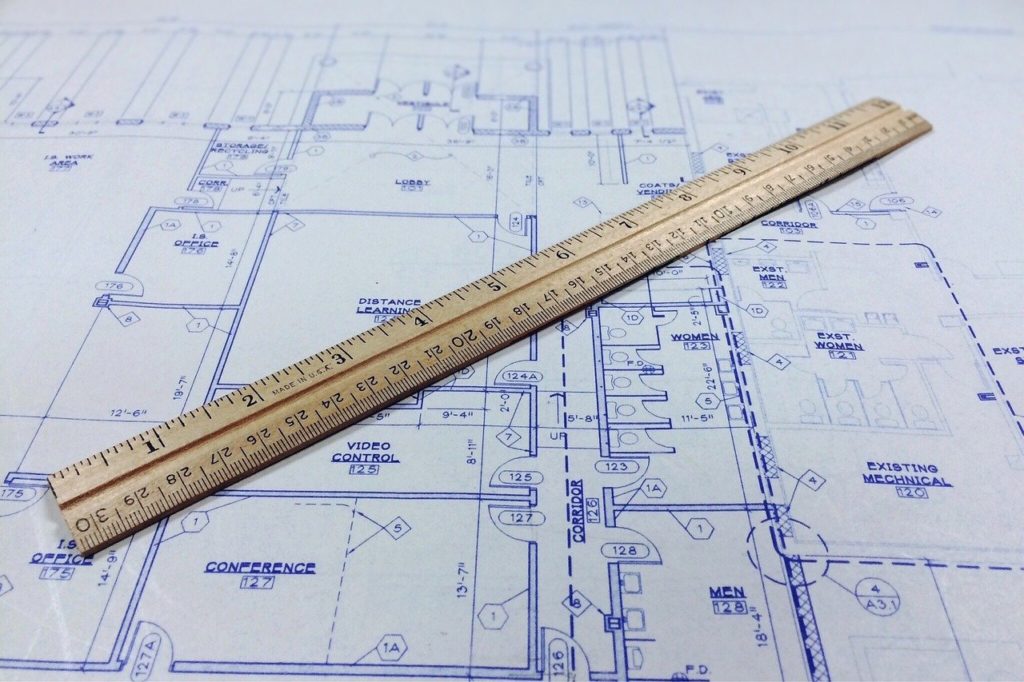成果につながるオウンドメディア運用方法とは
公開日:
更新日:
オウンドメディアは一般に、企業が自ら運営するメディアのことを指します。その目的としては、自社の商品やサービスの認知度を高めるブランディング、シェアの拡大、優秀な人材を採用するための戦略の一環など様々です。有名企業でいえば例えば株式会社資生堂などが非常に洗練されたオウンドメディアを展開しており、中小企業においても多くの企業が取り組む施策となっています。
その理由として、一般的な広告費よりも安く済むというものが挙げられます。しかし実際にオウンドメディアを開設しても、うまく運用できず、期待したような効果が得られなかったり、更新が滞ってしまうケースも多いようです。
そこで今回は既にオウンドメディアを開設している企業担当者様を対象とした、効果的なオウンドメディアの運用方法についてご紹介いたします。
オウンドメディアについて知りたい方は以下の記事もご参照ください。
オウンドメディアの運用に求められるポイント

現在、多くの企業がオウンドメディアを使ったブランディング戦略を取るようになりました。そのため、競合と差をつけるためには運用がポイントになります。
オウンドメディアを使って本格的な成果につなげたい場合、手の空いた人が取り組むような業務運用体制では思うような結果は得られません。
ここではオウンドメディア運営に関する4つのポイントを切り口に、オウンドメディアを成功に導くコツをご紹介しましょう。
SEO対策がなされた記事(コンテンツ)制作
オウンドメディアの記事を想定するターゲットに読んでもらうためには、検索上位に上がってこなければいけません。いくら良質な記事だったとしても、目に触れなければ成果(商品の購入やメルマガ登録、資料請求など)にはつながりにくいのです。
検索上位に上がるためには、読者が読みやすいように目次を配置したり、適切なキーワード選定を行った上でそれらのキーワードをうまく文章中に盛り込むなどのSEO対策が不可欠です。検索エンジンに最適化された記事を作るには、記事執筆者の“勘”に任せるのではなくきちんとチームで対応していくことが重要になるでしょう。
SEO対策はオウンドメディア運営の基礎になるものといっても過言ではありません。きちんと対策を行うことがオウンドメディア成功のカギになるのです。
コミュニケーション体制(コミュニケーションツール)
オウンドメディアを運営する場合、それ自体で完結させるのではなく、SNSやメルマガなども活用して相乗効果を狙いましょう。
漫然と記事を投稿していくだけではターゲットに届きません。多様なコミュニケーションツールを使ってコンテンツを拡散しましょう。
特にSNSを使った情報発信は、有用な情報や興味を引く内容であればユーザーが自分のアカウントを使ってさらに拡散して新規顧客が訪れるようになることも期待できます。サイト自体の被リンクが増えればSEO評価も高まり好循環が生まれることでしょう。
スケジュール管理
オウンドメディアの記事は定期的に更新し続ける必要があります。
「何かネタになるようなことがあったらその都度書く」とか「書ける時間のある人がとりあえず何かを発信する」といったあいまいなルールで運用していては、せっかくのオウンドメディアも効果を上げることが難しくなります。
例えば、週に5記事投稿されることもあれば1記事も投稿されないこともあるようでは読者は自然と離れていってしまうでしょう。
きちんと各担当者とスケジュールを決めて、ユーザーへ“新しい発見(=オウンドメディアでのポジティブな体験)”を提供し続けることが重要です。
評価(PDCAを回す)
オウンドメディアをスタートしてしばらくの間は記事も少なく、あまり重要なポイントではありませんが、コンテンツが十分に揃ってきたら必ずやらなければいけないことがあります。それが、各コンテンツの評価を行うことです。
オウンドメディアに投稿されたコンテンツがユーザーの求めているものかどうかをGoogle Analyticsなどを使って分析し、効果が芳しくない場合は改善しましょう。
例えば流入数やCV数、ページの掲載順位、訪問ユーザーの動き(滞在時間等)などを分析し、記事内容の見直しやキーワードの追加を行います。予め決めておいたKPIを達成できているかといった評価も重要です。
こうした分析・改善は流行が目まぐるしく変わっていく現代社会においては定期的に行うべきものになります。最初から完璧を目指す必要はありませんが、一度分析を行って改善ができたとしても、それで終わりになるわけでもないのです。
あまりこまめに分析を行うようでは、十分なデータが蓄積されておらず手間になるだけですが、ある程度時間をおいたらPDCAを回すことは忘れずに行いましょう。
▼オウンドメディア運用時の戦略・考え方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
コンテンツを制作するときに押さえておきたいポイント

オウンドメディアの運用とはコンテンツの運用といっても過言ではありません。コンテンツの良し悪しでオウンドメディアの効果がまったく変わってきます。社内の理解を得た上で全社的に取り組むことが理想です。
運用という観点から見た場合、コンテンツの方向性を決めることで、その後の制作の手間が軽減されるだけでなく、メディアに統一性を与えることができるでしょう。
ここではコンテンツ制作において押さえておきたいポイントをまとめてみました。
どういう情報を発信するか
オウンドメディアではどんな情報を発信していけばいいのでしょうか。それは大きく分けて2つあります。
ひとつはユーザーの求める情報です。例えば自社が今度展開する新しいサービスに関連する記事であれば、サービスの概要だけに留まらず、そのサービスがどんな課題を解決してくれるのか、既存のサービスとくらべてどんなところが優れているのかを具体的に想像できるような記事にすれば、そのサービスを知りたいと思って訪れた人は満足するでしょう。
ユーザーのニーズに合致した記事をいつも発信することができれば、自社への信頼性を高めるだけでなく、リピートして訪れてくれるようになることでしょう。
もうひとつは、自社の“公式情報”であることに価値がある情報です。
例えば新製品のレビュー記事で、ユーザーがブログで発信する情報は、ユーザー目線の良し悪し分析という点では読者の参考になります。しかし不確かな情報(例えば「女性が使うにはちょっと重い」とか「カバンに入れるには大きい」といったもの)や、業界への不理解があったりして、読者に混乱を与えてしまう可能性もあります。
これに対して企業が発信する“公式情報”で重さや大きさをきちんと数字で伝えたり、その業界で活躍するプロ目線から見た情報というものは、ユーザーにとって「公式が言っているのだから間違いない」という安心感も相まって価値のある情報となります。
上記のような内容に、先にも触れたSEOとしてのキーワードを盛り込んでいくことで、ターゲットの目に触れやすい記事を制作することができるでしょう。
読み手(ペルソナ)を設定する
文章を書くときは誰に向けた内容なのか、常に読者を意識することが重要ですが、オウンドメディアにおいてもそれは同じです。どんな人に見てもらいたいか、ターゲットのペルソナを設定することによって、“ユーザー”が求める情報を絞り込むことができます。
漠然と「当社のお客様」ではなく、「当社製品を愛用する30代のキャリアウーマン。営業職。既婚者で子どもは二人。最近はフィットネスに興味を持っている……」といった具合に具体的な人物像を設定することで、オウンドメディアでどんな情報を発信すればいいか“当たり”をつけやすくなります。
こうしたペルソナ設定を行う際、同時にカスタマージャーニーマップなどを作成するのも広報戦略として効果的です。オウンドメディアをどんなタッチポイントにしていくかの指針とすることもできるでしょう。
メディアの未来像を想定し、軸のブレない運用をする
オウンドメディアは基本的に以下のような流れで作っていくのが一般的です。
①コンテンツの充実:まずは質よりも量を充実させメディアとしての体裁を整えます
②ブラッシュアップ:コンテンツを分析しPDCAを回します
③テーマ性の強化:いわゆるビッグワードでも上位表示を目指せるサイトになるようオウンドメディア全体を通したテーマ性を強化していきます
ペルソナの設定にも関連しますが、メディアの方向性を決めてコンテンツを充実させていく過程で、テーマ性がポイントになります。①の段階でテーマをガチガチに決めてしまうとなかなか手につかなくなりスタートダッシュが切れません。②の段階で意識し、③に備えるくらいの認識でいいでしょう。
「このメディアは何がテーマになっているか」が明確になっていると、そのテーマに関することを知りたい人が集まるメディアづくりができるというわけです。
詳細なものでなくてもいいので、オウンドメディアの長期的なビジョンを想定し、テーマを持たせることで「今何をするべきか」の指標とすることができるでしょう。
オリジナリティの追求
SEO対策のキーワードを羅列しただけだったり、検索上位記事の焼き直しのようなコンテンツでは、良質なコンテンツとはいえませんし、他サイトとの差別化もできていないことになります。
読み手の悩みや課題が解決されるものや、公式情報だからこそ価値があるものを発信するようにしましょう。「このオウンドメディアでないと知ることができない情報がある」ということは大きな強みになります。
つまり、自社だからこそ書けるオリジナル情報(独自性)の発信を心がけることが、ターゲットを誘引するポイントになるのです。
▼オウンドメディア立ち上げ時の注意点・考え方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
効果的なコンテンツを提供するために重要なこと

コンテンツ制作の大まかな方針を固めたら、個々のコンテンツの効果も最大化を目指したいところです。そのための答えを見つけるためのヒントをご紹介しましょう。
顧客の求めるものを知る
オウンドメディアのターゲットになる人は、自社の顧客か、将来的に顧客となる見込みのある人でしょう。であるならば、顧客の求めるものを知ることが、オウンドメディアの読者の求めるものを知ることにつながります。
ではどうやって顧客の求めるものを知ればいいのでしょうか。
例えば、顧客へマーケティングリサーチを行うことは、ユーザーの生の声だけに、求めるものをダイレクトに知ることができるでしょう。
しかし、顧客が自分の求めているものに気づいていない(言語化できていない)ということもあります。そういう場合は、営業担当者へヒアリングするのがおすすめです。「こういうことをいうお客さんが多い」と、ズバリ答えを知ることができる場合もあれば、営業担当者が営業時に感じていることを分析することで、顧客が求めている情報が浮き彫りになることもあります。
記事にするネタがないからといって、それまでの記事とは毛色の違う雑記を混ぜたり、無理に流行に迎合するような記事で軸をぶれさせないようにしましょう。
▼オウンドメディアにおける効果的なコンテンツづくりについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
運用に必要な体制構築こそオウンドメディア成功のカギ

ここではオウンドメディアを効率よくかつ効果的に運用するために必要な体制と、それぞれの役割を解説します。
会社の規模によってはこれらを少人数でこなさなければならないこともあるかもしれません。しかし可能であれば、各役割を適材適所に別の人間が担当することで、より洗練されたオウンドメディアを展開することができるでしょう。
エディター
オウンドメディアの編集長的なポジションです。
企画、構成、取材先などの手配、原稿の編集作業、入稿までの進行管理などを行います。
全体を俯瞰できる広い視野が求められると同時に、取材先とのコミュニケーション能力や原稿のミスに気づける細やかさも必要です。
記事制作者が兼ねている会社もあるかもしれませんが、単純にやることが多くて大変なだけでなく、自分が書いた記事を客観的な視点で編集することは思った以上に難しいものです。できれば別の人間が行うか、せめて記事執筆からしばらく時間を置いて冷静な目で見られるようにする必要があるでしょう。
記事制作者
多くの人が違和感なくスラスラと読める文章を書くのは、意外と技術のいるものです。伝えたいことをきちんと言語化できる訓練をしたことのある人が担当するようにしましょう。
「自社の製品に詳しい人間=自社の製品の魅力を人に伝えられる人間」とは限りません。製品に詳しくなくても、詳しい人間に取材し文章にまとめられる人間が執筆するほうが、結果としてターゲットに伝わるし制作の効率もいいでしょう。
また、コンテンツにはビジュアルも重要な要素になります。特に製品紹介や開発者へのインタビューなどでは、対象の魅力を引き出した写真があれば記事に説得力を与えることでしょう。
昨今のカメラは性能が上がっているので、素人でもそれなりの写真が撮れますが、100の言葉よりも1の映像がターゲットに刺さることもあります。写真もプロのカメラマンか、それに準ずる技術的に覚えのある人が担当したいものです。
サイトメンテナンス担当
最初から完璧なサイトなど存在しません。使いにくいところや見にくいところは、その都度改善していかなければいけません。
例えばGoogle Analyticsなどを使って分析し、自社で設定したゴール(問い合わせや資料請求)にユーザーがたどり着いていない場合、記事ではなくサイトのデザインに問題がある可能性が考えられます。そのほかにもスマホでの表示がうまくできていなかったり、フォントが読みにくかったりと、ユーザビリティに配慮した改善が必要なケースも考えられます。
こうした課題が浮き彫りになったとき、サイトをメンテナンスする担当者も成果をあげるためのオウンドメディア運用には欠かせません。
効果測定者
公開された記事の反響を分析する担当者も必要です。先に触れたように、オウンドメディアのコンテンツにはPDCAが欠かせません。
定期的に確認し、必要があれば記事に内容を加筆したり、キーワードの見直しを行ったりします。
サイトのメンテナンスもそうですが、多くの人は作ることには注力しますが、できた後の改善はあまり力を入れないケースが多く見られます。裏返せば、ここを疎かにしないことが競合との差をつけるポイントになるので、効果測定者も重要なポジションといえるでしょう。
▼オウンドメディア記事制作、必要となる記事制作者についてや、効果測定の話題は以下の記事でも詳しく解説しています。
SEOツールで運用の作業を省力化

これまで見てきたように、オウンドメディアを運用することはたくさんの労力を要します。
特に、やみくもにやっても効果が薄いSEO対策は運用における大きな負担になります。しかし最近ではこの工程を省力化できる「SEOツール」と呼ばれる手段が注目を集めています。ここではこの支援ツールでどんな作業を省力化できるのかをご紹介します。
キーワード選定
自社のオウンドメディアを検索上位に来させるためには、各記事においてキーワードを文章中に盛り込んでいかなければいけません。
このとき、重要かつ難しい作業がキーワードの選定ですが、SEOツールを使えば、検索上位に来るために必要なキーワードを自動で選定、一覧することができます。
例えば当記事で言えば「オウンドメディア」とか「運用」が重要なキーワードとなるのは想像しやすいと思いますが、もちろんそれ以外のキーワードも盛り込まなければSEO対策がなされた記事とはいえません。どんなキーワードを盛り込むかがWEBライターの腕の見せどころなのですが、属人的になりやすい作業といえます。
SEOツールはこうした選定作業を自動化できるので、企画・構成を考えるときはもちろん、文章執筆における負担も大幅に削減することができます。記事のSEO的なクオリティを標準化することもできるでしょう。
記事のクオリティチェック
執筆できた記事をSEOツールの分析にかければ、SEO対策ができているかのチェックができます。
経験と勘だけでSEO対策をやっていた方も、客観的な指標を得られます。記事執筆者に修正してもらう際にも、指示を明確にすることができるでしょう。
定期評価後のリライト作業効率化
前述したように、記事を公開したら定期的に分析ツールなどを用いて効果測定を行わなければいけません。その際、デザインや内容だけでなくSEO的にも修正が必要なケースが想定されます。
SEOツールを使えば、記事でSEO対策が不足している部分を簡単に可視化することができるので、リライト作業もスムーズに行うことができるでしょう。
運用を外注するという選択肢もある

オウンドメディアの運用省力化という点では、外部の力を借りる外注という選択肢も検討する価値があります。
ここでは外注することのメリット・デメリットや、外注時のポイントなどをご紹介します。
外注のメリット・デメリット
外注することのメリットは、自社で担当者のリソースを確保する必要がないこと、プロが執筆することで一定の記事クオリティを維持できることなどが挙げられます。
逆にデメリットは、外注費(コスト)が必要なこと、求めるゴールや記事の雰囲気など外注先と認識のすり合わせが重要であることなどが挙げられます。
外注するときのポイント
今回の記事はオウンドメディア開設からある程度時間が経過している企業の担当者を想定して執筆していますが、外注する場合、可能であればオウンドメディア立ち上げ時から外注先の制作会社へ相談するようにしましょう。
コンセプトを土台からしっかり固めることができますし、立ち上げ後も認識のすり合わせができているので軸がブレずに運用していくことができるでしょう。
このほか、制作会社から上がってくる構成案は詳細にチェックすることをおすすめします。記事化した後の大幅な変更は別料金となる可能性があるというコスト面だけでなく、執筆を担当するライターの混乱のもととなり、制作が遅れてしまうリスクもあります。既にご紹介したように、オウンドメディアは定期的な更新が求められるので、制作の遅れはスケジュール管理上避けたいところです。
一部だけ外注するのもおすすめ
外注する際は、リソースを割くことが難しい部分だけお願いするという手もあります。
例えば編集的な工程は自社で行い、それに合う記事を実績のあるライターとカメラマンへ外注するようなケースが考えられます。もちろん、この場合もライター、カメラマンと認識のすり合わせが不可欠です。“段取り八分”ということばがあるように、事前の準備が非常に大切であることはいうまでもありません。
そして記事が上がってきたら、必ずチェックしましょう。修正指示を出す場合も、どうして修正が必要なのかまで伝えることで、次に依頼するときの仕事をスムーズに進められるようになります。
▼オウンドメディア制作・運用の外注については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
オウンドメディアを外注運用する際のコスト

外注する場合、きちんとしたオウンドメディアを立ち上げからすべてやってもらおうとすると初期費用として100~200万円程度かかるといわれています。もちろん、担当してもらう内容や求めるクオリティなどによって費用は変わるので、あくまで目安と考え、詳細は問い合わせましょう。
運用を任せる場合、月に20記事で月額10万円を切るところもあれば、50万円を超えるケースもあります。
これは運用内容のきめ細かさが関係します。記事制作だけでなく、各種メンテナンスや戦略提案などまで行うと当然コストが高くなります。また、記事が取材や調査を伴う手間のかかるものになると、これも高コストになります。
問い合わせの際は、他社事例などを参考に自社がどれくらいのクオリティを必要としているのか確定させておかないと“オーバースペックな運用”で余計なコストがかかってしまうかもしれません。しかし、コストを気にして必要最低限なクオリティを担保することばかりに注力すると顧客獲得という目的につながらなくなってしまいます。
外注する場合は、自社体制のどの部分が不足しているのかきっちりと把握したうえで、必要な工程だけを頼むようにするのがコストを抑えるコツです。ただし、保守はA社、レポーティングはB社、記事制作はC社といったように、もっとも安い会社に任せようと、各工程をバラバラに発注すると、認識のすり合わせがうまくいかず、ちぐはぐな印象になってしまう可能性があります。外注する工程はできるだけワンストップで依頼するのがおすすめです。
▼オウンドメディアに関するさまざまな費用については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
運用は継続することが大切
オウンドメディアは効果があらわれるのに時間がかかるケースが多いブランディング手法です。しかし自社が考える理想的なブランドイメージを提供できる方法としては優れた威力を発揮するでしょう。
そのためには目的を明確化し、丁寧かつ効率的な運用をノウハウを蓄積しながら長期スパンで続けていかなければいけません。これには幅広い知識と多大な労力が必要となるため、社内の(必要であれば社外も含めた)適材適所で工程を分担し、チームとして取り組むのがおすすめです。
特に定期的な見直しは、個々の記事というミクロ視点だけでなく、メディアのデザインや構成まで含むマクロ視点でも行う必要があり、複数の目でチェックすることで効率的かつ高い精度でブラッシュアップができるでしょう。